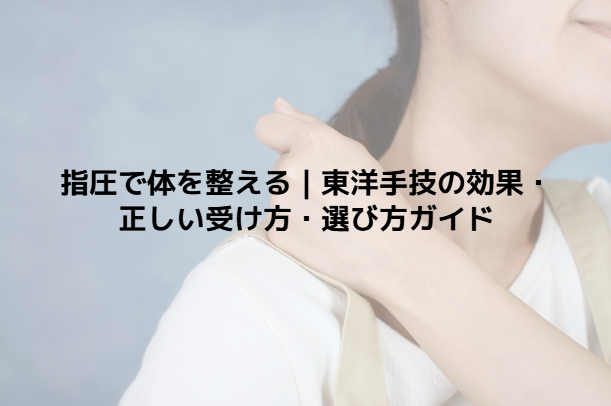五十肩 症状とは?どういった肩の状態を指すのか

五十肩とは「肩関節周囲炎」と呼ばれる状態
「五十肩(ごじゅうかた)」とは、正式には**肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)**と呼ばれています。
名前の通り、肩の関節のまわりに炎症が起こり、肩を動かすと痛みが出たり、動かしづらくなったりする状態を指します。
特に40代後半〜60代の方に多く見られ、「加齢による変化のひとつ」とも言われています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
一般的に、五十肩の初期は突然肩に痛みを感じることが多く、「腕を上げるとズキッとする」「服を着替えるときに肩が引っかかる」といった違和感が始まりのサインになるケースもあります。
ただし、すべての肩の痛みが五十肩ではなく、肩腱板損傷や関節リウマチなどの別の疾患の場合もあるため注意が必要です。
肩が痛いだけじゃない?日常動作で現れる症状
五十肩の症状は単に「肩が痛い」というだけではなく、**動かしにくさや夜間の痛み(夜間痛)**なども特徴的です。
例えば、以下のような動作で痛みを感じる人が多いと言われています。
- 髪を結ぶ、ドライヤーを使う
- エプロンの紐を後ろで結ぶ
- 洗濯物を干す、上の棚に手を伸ばす
- シャツやジャケットを着るときに肩が引っかかる
これらの動作で痛みが出るのは、肩関節を支える筋肉や腱(けん)、関節包と呼ばれる膜が炎症を起こしているためとされています(引用元: https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
また、**夜寝ているときにズキズキと痛む「夜間痛」**も五十肩の代表的な症状のひとつです。
この痛みのせいで眠りが浅くなり、疲れが取れにくくなる方も少なくありません。
五十肩と肩こりの違い
「肩が重い」「動かすと痛い」と聞くと、肩こりと混同されがちですが、五十肩とは別の状態です。
肩こりは筋肉の血行不良や姿勢の乱れが原因で、揉むと一時的に軽くなることが多いのに対し、五十肩は関節そのものに炎症が起きているため、強く揉むと痛みが悪化することもあると言われています(引用元: https://toyohashi-seikotsuin.com/contents/blog/gokata/ )。
また、五十肩の場合は「腕を動かせる範囲(可動域)」が狭くなるのが特徴です。
無理に動かすと激痛が走るため、安静にしつつ専門的な施術やストレッチで少しずつ動きを取り戻すことが望ましいとされています。
放置すると動かなくなる?進行のサイン
初期の痛みを「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、肩関節の動きがどんどん悪くなり、**腕を上げたり後ろに回したりする動作が制限される(拘縮期)**へと進むことがあります。
この状態になると、日常生活の動作が大きく制限され、改善まで数ヶ月〜1年以上かかるケースもあると言われています。
そのため、「肩を動かすと痛い」「寝返りで肩がズキッとする」などの違和感を感じた時点で、早めに整骨院や専門機関へ相談することが大切です。
早期に適切なケアを行えば、痛みの悪化や関節の硬直を防ぐサポートができるとされています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
#五十肩 #肩関節周囲炎 #夜間痛 #肩こりとの違い #肩の動かしづらさ
五十肩 症状の進行ステージとそれぞれの特徴

炎症期(急性期)|強い痛みと夜間痛が出やすい時期
五十肩の最初の段階は炎症期(急性期)と呼ばれ、肩関節の内部で炎症が起きている状態を指します。
この時期は、ちょっとした動作でもズキッと痛みが走ったり、夜寝ているときに夜間痛が強く出たりするのが特徴です。
特に「寝返りを打った瞬間に激痛が走る」「腕を上げようとしても途中で止まってしまう」といった症状が多く見られます。
この段階では、無理に肩を動かすと炎症が悪化する可能性があるため、冷却や安静を優先することが大切だと言われています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
炎症期の痛みは数週間〜2か月ほど続くことがあり、夜間の痛みが続くことで睡眠不足やストレスにつながるケースもあるようです。
拘縮期(慢性期)|痛みは減るが動かない時期
次に訪れるのが**拘縮期(こうしゅくき)**です。
炎症が落ち着き始めると痛み自体は少しずつ軽くなりますが、その代わりに「肩が動かない」「引っかかる感覚が残る」と感じる方が増えます。
これは、炎症の影響で肩の関節包が縮こまり、可動域(動かせる範囲)が制限されてしまうためです。
例えば、
- 髪を結ぼうとして腕が上がらない
- 背中のファスナーを閉められない
- エプロンの紐を後ろで結べない
といった日常の動作が難しくなるのがこの時期です。
また、肩を動かすと「突っ張るような痛み」や「ゴリゴリ感」を覚える人もいます。
無理に動かそうとせず、専門家のもとで少しずつ可動域を広げるリハビリや施術を行うことがすすめられています(引用元: https://sato-seikotsuin.com/frozen-shoulder/?utm_source=chatgpt.com )。
回復期|動かせる範囲が戻ってくる時期
最後の段階は回復期です。
炎症や関節の硬さが徐々に改善し、腕を動かせる範囲が少しずつ広がっていく時期と言われています。
この段階では、「肩を回すと少し痛いけれど、以前より上げやすくなった」と感じる人が増えてきます。
ただし、回復期といっても完全に元通りになるまでには時間がかかることが多く、数か月〜1年程度の期間が必要になることもあります(引用元: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%A9%E9%96%A2%E7%AF%80%E5%91%A8%E5%9B%B2%E7%82%8E?utm_source=chatgpt.com )。
リハビリやストレッチをサボってしまうと可動域が戻らないこともあるため、痛みの程度を見ながら継続的なケアが重要です。
ステージごとのケアの目安
| ステージ | 主な症状 | ケアのポイント |
|---|---|---|
| 炎症期 | 強い痛み・夜間痛・腫れ | 無理に動かさず冷却と安静を中心に |
| 拘縮期 | 痛みは減るが動かしづらい | 温めて血流促進・ストレッチで可動域拡大 |
| 回復期 | 動きが改善・軽い痛み | 定期的な運動・姿勢改善で再発防止 |
このように、五十肩は「痛みが強い→動かない→動くようになる」という段階を踏むのが特徴です。
それぞれの時期に合わせたケアを行うことで、肩の動きをスムーズに取り戻しやすくなると言われています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
#五十肩 #炎症期 #拘縮期 #回復期 #肩関節周囲炎
五十肩 症状が出る肩の動作・痛みパターン

日常の中で感じる「動かすと痛い」瞬間
五十肩は、特定の動作をしたときに「ズキッ」と痛みを感じるのが特徴の一つです。
たとえば、髪を結ぶ、洗濯物を干す、上着を着る、背中に手を回す——こうした腕を上げたり、後ろへ回す動きで痛みが出やすいと言われています。
中でも多いのが「結帯動作(けったいどうさ)」と呼ばれる動きです。
これは、手を背中に回してエプロンの紐を結ぶ、ポケットに手を入れる、といった日常的な姿勢。
このとき、肩の前側や上腕の付け根あたりに鋭い痛みや張りを感じる場合、五十肩のサインである可能性があります(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
また、初期の段階では「肩を動かすと痛い」だけでなく、「動かさなくてもズキズキする」「夜に疼く」といった症状も見られます。
これは、炎症によって関節内部に熱がこもり、神経が刺激されているためだと考えられています。
夜間痛の特徴と注意点
五十肩の中でも多くの人が悩まされるのが、**夜間痛(やかんつう)**です。
夜中にズキズキとした痛みで目が覚めたり、寝返りを打つだけで肩に激痛が走るケースも少なくありません。
この痛みは、横になったときに肩の血流が滞りやすくなることや、炎症による内部圧の上昇が関係していると言われています(引用元: https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
夜間痛が続くと、睡眠不足やストレスによって自律神経が乱れ、さらに肩の回復が遅くなることもあるようです。
そのため、寝る姿勢を工夫することもケアの一つ。
痛む肩を下にせず、クッションやタオルで腕を少し持ち上げると、負担が減って眠りやすくなると言われています。
動作ごとの痛みの出方
五十肩では、痛みが出る動作によって炎症の部位や進行具合を推測できることがあります。
| 動作の種類 | 痛みを感じる部位 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| 腕を前に上げる(屈曲) | 肩の前〜上部 | 初期に痛みやすい |
| 横に上げる(外転) | 肩の外側〜上腕 | 肩を横に開くとズキッと痛む |
| 背中に回す(結帯動作) | 肩の前部・上腕前面 | 髪を結ぶ・エプロンを結ぶ時に痛む |
| 寝返り・横向き姿勢 | 肩の奥 | 夜間痛・圧迫による痛み |
こうした痛みのパターンを自覚しておくことで、どの程度進行しているのかを把握しやすくなります。
ただし、症状が左右で異なる場合や、しびれを伴う場合は、神経や腱の損傷がある可能性もあるため注意が必要です。
痛みを我慢して動かすのは逆効果
「少し動かしたほうが良い」と考えて、痛みをこらえて無理にストレッチする方もいますが、急性期にそれを行うと炎症が悪化することがあります。
特に、夜間痛が強いときや肩を上げるだけで激痛が出るときは、まず冷却と安静を優先し、痛みが落ち着いてから可動域を広げる運動を取り入れることがすすめられています(引用元: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%A9%E9%96%A2%E7%AF%80%E5%91%A8%E5%9B%B2%E7%82%8E?utm_source=chatgpt.com )。
痛みがあるうちは、無理に動かすよりも体を休めることが回復への近道だと考えられています。
また、整骨院や医療機関で炎症の程度を確認し、状態に合わせた施術やストレッチを行うことが重要です。
「痛み方の違い」で見分けるポイント
五十肩の痛みは、鈍い痛みが続くケースもあれば、動かした瞬間に鋭い痛みが出ることもあります。
前者は炎症が落ち着きつつある拘縮期、後者は炎症が強い急性期であることが多いと言われています。
つまり、「どんな動きで、どんな痛み方をするか」を観察することで、自分の状態をある程度把握できるのです(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
#五十肩 #夜間痛 #肩の動かしづらさ #肩の可動域制限 #肩関節周囲炎
五十肩 症状を悪化させる要因と早期チェックポイント

放置すると悪化する「動かさない習慣」
五十肩の症状を悪化させる最大の要因のひとつが、肩を動かさないことです。
痛みがあると自然と動かさなくなりますが、実はその“安静のしすぎ”が関節をさらに硬くしてしまうことがあると言われています。
関節の動きを支える「関節包」や「腱」「筋膜」は、使わない時間が長くなると縮こまり、可動域が狭くなっていくのです(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
また、肩をかばって反対側の肩や首に力が入りすぎることで、姿勢の歪みや筋肉のアンバランスが起こり、痛みが長引くケースもあります。
痛みが強い急性期は無理に動かす必要はありませんが、炎症が落ち着いてきたら、軽いストレッチや可動域を保つ動きを少しずつ取り入れることが大切だと言われています。
姿勢の悪さ・巻き肩・猫背も悪化の原因に
長時間のデスクワークやスマートフォン操作で猫背や巻き肩の姿勢になっている方は、五十肩を悪化させやすい傾向があるとされています。
背中が丸まると肩甲骨の動きが制限され、肩関節に余計な負担がかかりやすくなるためです。
特に、パソコン作業で腕を前に出したままの姿勢を続けると、肩の前側が硬くなり、炎症を起こしやすくなります(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
日常生活では、
- 背もたれに深く座り、頭が前に出ない姿勢を意識する
- 肩甲骨を軽く引き寄せて胸を開く
- スマホを目線の高さに上げて使う
といった工夫で、肩の負担を軽減できるとされています。
姿勢を整えることが、肩の炎症を防ぐ第一歩になります。
冷え・血行不良による筋肉の硬直
「寒い季節になると肩が痛む」「冷房の風に当たると肩がこわばる」という方も多いでしょう。
実は、冷えによる血行不良も五十肩を悪化させる原因の一つと考えられています。
血流が滞ると筋肉や腱に酸素や栄養が届きづらくなり、老廃物が溜まりやすくなります。これが、痛みや炎症を長引かせる要因になるのです(引用元: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%A9%E9%96%A2%E7%AF%80%E5%91%A8%E5%9B%B2%E7%82%8E?utm_source=chatgpt.com )。
特に冷房の効いたオフィスや寝室では、首や肩を直接冷やさないよう注意が必要です。
軽く羽織るものを準備したり、入浴や温タオルで血流を促すことが、肩の回復を助けるサポートになると言われています。
加齢と筋力低下の関係
五十肩は名前の通り、40代後半〜60代の方に多く見られる症状です。
これは、年齢とともに肩の筋力や柔軟性が低下することで、関節への負担が増えるためだとされています。
特に「棘上筋(きょくじょうきん)」や「棘下筋(きょくかきん)」といった肩のインナーマッスルが弱くなると、関節を安定して支えにくくなり、炎症を起こしやすくなります(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
そのため、痛みが落ち着いたら、肩甲骨まわりを動かす軽い体操やストレッチを習慣にすることが重要です。
筋肉を使うことで血流が改善し、再発予防にもつながります。
早期にチェックしたい「危険サイン」
次のような症状がある場合は、五十肩が進行している、または別の疾患が関係している可能性があります。
- 腕がまったく上がらない・服を着る動作ができない
- 安静にしていてもズキズキと痛む
- 夜中の痛みで眠れない
- 手や指にしびれが出ている
こうしたサインがある場合、自己判断せず整骨院や医療機関での触診・検査を受けることがすすめられています。
早い段階で状態を把握し、適切なケアを始めることで、痛みの長期化を防げると言われています(引用元: https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
#五十肩 #悪化要因 #姿勢改善 #冷え対策 #早期ケア
五十肩 症状と勘違いしやすい肩の病気・整骨院/医療機関の使い分け

五十肩と間違えやすい「肩の病気」
肩の痛みがあると、多くの人が「五十肩かもしれない」と思いがちですが、実際には似た症状を持つ別の疾患も多く存在します。
そのため、痛みの原因を正しく見極めることが大切だと言われています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
代表的なものとしては以下のような疾患が挙げられます。
| 病名 | 主な特徴 | 見分けのポイント |
|---|---|---|
| 肩腱板損傷(けんばんそんしょう) | 腱板(筋肉と腱の集合体)が傷つき、腕を上げると強い痛み | 力を入れて腕を上げられない・クリック音がする |
| 石灰沈着性腱炎 | 腱の中に石灰(カルシウム)が溜まって炎症 | 突然激痛が走り、夜も眠れないほど痛む |
| インピンジメント症候群 | 肩の骨と腱がぶつかって炎症 | 上腕を上げると痛む・特定の角度で引っかかる |
| 頚椎症性神経根症 | 首の神経が圧迫される | 肩〜腕にかけてしびれやだるさが出る |
これらの症状は五十肩と似ていますが、痛む部位や発症のきっかけ、痛みの出方が異なるのが特徴です。
たとえば、腱板損傷は転倒やスポーツなどの“外的要因”で起こることが多く、しびれを伴う場合は首や神経が関係していることもあります(引用元: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%A9%E8%85%BA%E6%9D%BF%E6%90%8D%E5%82%B7?utm_source=chatgpt.com )。
五十肩の可能性が高いのはこんな症状
一方で、以下のような特徴がある場合は五十肩の可能性が高いと言われています。
- 特にケガをした覚えがないのに肩が痛くなった
- 肩を動かすとズキッと痛み、動かさなければ落ち着く
- 夜に痛みが強くなり、寝返りを打つと起きてしまう
- 少しずつ腕が上がらなくなってきた
これらは、**肩関節周囲の炎症と関節包の拘縮(こわばり)**によって起こる典型的な五十肩の症状です(引用元: https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
特に「動かすと痛い」「可動域が狭くなってきた」という場合は、早めに整骨院や医療機関で相談するのが安心です。
整骨院でできるサポート
整骨院では、五十肩の原因を「関節の炎症」だけでなく、「姿勢・血流・筋肉のバランス」などの観点から分析します。
施術では、固まった筋肉をゆるめて血流を促す手技や、肩甲骨の動きを改善するストレッチなどを行うことが多いです。
また、痛みの強さや動きの制限に応じて、自宅でできるセルフケアや姿勢のアドバイスを受けられることもあります。
こうしたアプローチによって、日常動作の改善や再発防止をサポートできると言われています(引用元: https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/ )。
医療機関(整形外科)で検査が必要なケース
次のような症状がある場合は、整形外科などの医療機関で**画像検査(レントゲン・MRI)**を受けることがすすめられています。
- 痛みが急に強くなった
- 肩に腫れや熱感がある
- しびれや感覚の鈍さが出ている
- 3か月以上経っても改善が見られない
これらは、五十肩ではなく腱や神経に異常がある可能性もあるため、原因を正確に確認してから施術やリハビリを行うことが重要です(引用元: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%A9%E9%96%A2%E7%AF%80%E5%91%A8%E5%9B%B2%E7%82%8E?utm_source=chatgpt.com )。
どちらに行くべき?整骨院と病院の使い分け
| 状況 | おすすめの相談先 |
|---|---|
| 軽い痛み・違和感が出たばかり | 整骨院(姿勢・血流改善中心) |
| 急な激痛・夜も眠れない | 医療機関(炎症や石灰沈着の可能性) |
| 痛みが落ち着いてきたが動かしづらい | 整骨院・リハビリ併用 |
| しびれや力が入らない | 整形外科(神経検査が必要) |
このように、痛みの強さ・経過・しびれの有無によって相談先を選ぶのがポイントです。
「どちらに行けばいいかわからない」ときは、まず整骨院で状態を確認し、必要に応じて医療機関を紹介してもらうのも良い方法です。
まとめ
五十肩と似た症状を持つ疾患は多くありますが、痛みの性質や経過を正しく見極めることが早期改善につながります。
無理をせず、早めに専門家へ相談することで、関節の可動域を保ちつつ痛みを軽減するサポートが期待できると言われています。
「ただの肩こりかも」と思っても、長く続く痛みには注意し、体のサインを見逃さないようにしましょう。
#五十肩 #肩腱板損傷 #整骨院と病院の違い #肩関節周囲炎 #肩の痛み