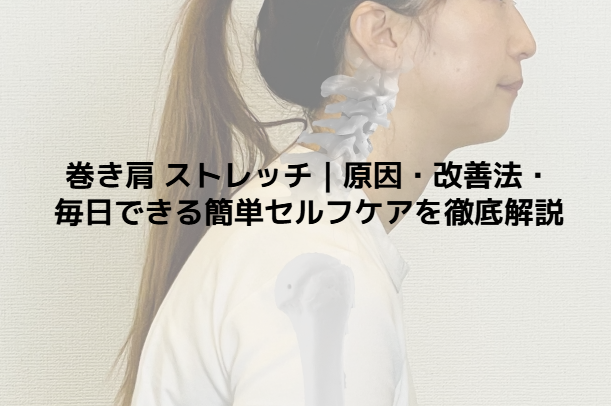巻き肩とは?姿勢の崩れが引き起こす体の不調

最近、「写真を見たら自分の肩が前に出ていた」「姿勢が悪いと言われた」という経験はありませんか?
それはもしかすると“巻き肩”かもしれません。
巻き肩とは、肩が体の前方に出て、胸が丸まり、背中が広がったような姿勢を指すと言われています。
一見、軽い姿勢の崩れに見えますが、放置すると肩こりや首の痛み、さらには頭痛や呼吸の浅さなど、さまざまな不調につながることがあるのです。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/
巻き肩になる背景:現代人の生活習慣に潜む落とし穴
巻き肩の主な原因として、デスクワークやスマホ操作の時間が長いことが挙げられます。
長時間、前かがみ姿勢でいると、胸の前にある「大胸筋」や「小胸筋」が縮み、背中の「僧帽筋」や「菱形筋(りょうけいきん)」が引き伸ばされて弱くなると言われています。
つまり、前側の筋肉が縮み、後ろ側が引っ張られてバランスが崩れる状態です。
このアンバランスが続くと、肩が自然と前に入り込み、結果として巻き肩姿勢が定着してしまいます。引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/posture
巻き肩が引き起こす体の不調
「肩が少し丸まっているだけ」と思いがちですが、巻き肩は首や肩まわりに常に緊張がかかった状態を作ります。
首の後ろの筋肉(後頭下筋群)や肩甲骨まわりの筋肉がこわばり、慢性的な肩こりや頭痛の原因になるケースもあると言われています。
また、胸郭(きょうかく:肋骨まわりの構造)が狭くなることで呼吸が浅くなり、疲れやすさや集中力の低下にもつながることがあります。
見た目にも猫背やストレートネックのような印象を与え、姿勢全体が老けて見えることもあるのです。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939
放置せず、まず「意識」を変えることが第一歩
巻き肩は、筋肉の緊張や日常姿勢が主な原因であるため、自分の姿勢を意識することが改善の第一歩です。
鏡の前で肩の位置をチェックし、耳・肩・骨盤が一直線になるように意識するだけでも、体のバランスは少しずつ変わっていきます。
整骨院では、姿勢の検査を通してどの筋肉が硬く、どの部分が弱いかを見極め、ストレッチや筋肉調整を行うことがあると言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/
まとめ:巻き肩は“現代病”のひとつ
巻き肩は特別な人だけに起こるものではなく、誰にでも起こり得る「現代人の姿勢トラブル」だと言われています。
日々のちょっとした姿勢のクセや生活習慣の見直しが、改善への大きな一歩になります。
まずは自分の肩の位置を意識してみることから始めてみましょう。
#巻き肩 #ストレッチ #姿勢改善 #肩こり予防 #デスクワーク姿勢
巻き肩になる主な原因とは?筋肉と生活習慣の関係

「なぜ自分は巻き肩になってしまったのだろう?」と感じたことはありませんか?
実は、巻き肩の多くはケガや病気ではなく、毎日の姿勢や筋肉の使い方のクセから生まれると言われています。
無意識のうちに続けている動作が、少しずつ肩や背中の筋肉バランスを崩していくのです。
胸の筋肉が硬く、背中の筋肉が弱まる
巻き肩の最大の原因は、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮み、肩を前に引っ張ってしまうことにあります。
スマホやパソコン作業では、手を前に出す姿勢が続くため、胸の前側が常に緊張しがちです。
一方で、背中側の「僧帽筋」や「菱形筋」など、肩甲骨を引き寄せる筋肉は使われにくくなり、次第に弱くなる傾向があります。
この前後のアンバランスが“肩が前に出た状態”を作り、巻き肩姿勢が定着してしまうと言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/
デスクワーク・スマホ操作が与える影響
現代社会では、長時間のデスクワークやスマホ操作が避けられません。
特にノートパソコンを使うと、目線が下がり、背中が丸まりやすくなります。
スマホを長時間見続ける“スマホ首(ストレートネック)”も、首から肩にかけての緊張を強める原因のひとつです。
その結果、肩甲骨が外側へ広がり、自然と肩が内に入り込んでいくと言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/posture
呼吸の浅さも巻き肩を悪化させる
意外かもしれませんが、「呼吸の浅さ」も巻き肩と関係しています。
胸まわりの筋肉が硬くなると、胸郭(きょうかく:肋骨まわりの骨の構造)が広がりにくくなり、呼吸が浅くなります。
浅い呼吸が続くと、体がリラックスできず、常に前傾姿勢になりやすい状態が続いてしまうのです。
深い呼吸を意識することが、胸を開く筋肉をやわらげ、巻き肩改善につながるとも言われています。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939
日常動作のクセが「慢性的な姿勢」をつくる
鞄をいつも片方の肩にかける、腕を組むクセがある、足を組んで座る——こうした“ちょっとしたクセ”も肩の歪みを作る要因になります。
左右どちらかの筋肉ばかりに負担がかかると、肩の高さや向きがズレていき、片方の肩だけが前に出ることもあります。
整骨院などでは、そうしたクセを含めて体全体のバランスを見て調整を行うことがあると言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/
「筋肉のバランス」が姿勢の土台
巻き肩は、一部の筋肉が悪いわけではなく、「使いすぎ」と「使わなすぎ」の差が大きいことが原因です。
胸の筋肉をゆるめ、背中をしっかり動かすことが、正しい肩の位置を取り戻す第一歩です。
生活習慣の見直しとストレッチを組み合わせることで、肩のラインが自然と開いていくことも多いと言われています。
#巻き肩 #ストレッチ #姿勢改善 #胸の筋肉 #スマホ姿勢
巻き肩を予防するための「日常姿勢」のポイント

「ストレッチしても、気づいたらまた肩が丸まってる…」
そんな経験、ありませんか? 実は巻き肩は、ストレッチよりも“日常の姿勢”の積み重ねが大きく影響していると言われています。
つまり、日々の姿勢を少し意識するだけでも、巻き肩を防ぐことができるのです。ここでは、日常で意識したい姿勢のコツを紹介します。
デスクワーク中は「背中」より「骨盤」を意識
巻き肩の人は、「背筋を伸ばそう」と意識してもすぐ疲れてしまうことが多いです。
それは、背中だけで姿勢を保とうとしているからです。
実は正しい姿勢をキープするには、骨盤を立てることが最も重要だと言われています。
椅子に深く腰をかけ、坐骨(お尻の骨)が座面にまっすぐ当たるように座ると、自然に背筋が伸びて胸も開きやすくなります。
この骨盤の角度ひとつで、巻き肩の負担がぐっと減ることもあります。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/
スマホ操作は「顔を下げず、目線を下げる」
スマホを見るとき、つい顔を下に向けてしまいますよね。
その姿勢が続くと、首の後ろが引っ張られ、肩が前に出る“スマホ巻き肩”を引き起こすと言われています。
ポイントは、スマホを目の高さに近づけること。
手を少し高く構えて操作すれば、自然と背筋が伸びて肩の位置も整いやすくなります。
また、長時間のスマホ使用は避け、30分に1回は軽く肩を回すなど、動きを入れるとさらに効果的です。引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/posture
立ち姿勢は「耳・肩・くるぶしが一直線」
立っているときの姿勢も、巻き肩に影響します。
正しい立ち姿勢は、横から見たときに「耳・肩・くるぶし」が一直線になることが目安です。
肩が少しでも前に出ると、胸が縮み背中に負担がかかります。
仕事中や通勤時に姿勢が崩れやすい人は、壁に背中をつけて立ち、頭・背中・お尻が壁につくか確認してみましょう。
慣れないうちは少し違和感がありますが、これを「ニュートラルポジション」として覚えることで、姿勢感覚がリセットされていきます。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939
呼吸を深くするだけでも姿勢が変わる
姿勢を意識する上で見落としがちなのが「呼吸」です。
胸や肋骨まわりが硬くなると、呼吸が浅くなり、上半身が前傾しやすくなります。
そこで意識したいのが、「胸を開いて、鼻から吸って、ゆっくり吐く」呼吸法。
深い呼吸を続けることで、胸の筋肉がやわらぎ、自然と肩が後ろに引かれやすくなると言われています。
姿勢を整えるためには、呼吸を整えることも大切なのです。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/
姿勢は「習慣」でつくられる
巻き肩の予防は、特別な運動よりも日々の小さな意識がカギです。
デスクワークの合間に肩を回す、座るときに骨盤を立てる、呼吸を深くする——
これらを「無意識でできる状態」に近づけていくことが理想だと言われています。
#巻き肩予防 #姿勢改善 #デスクワーク姿勢 #スマホ巻き肩 #呼吸法
巻き肩を改善するためのストレッチ3選:自宅でできる簡単セルフケア

「姿勢を正したいけど、どんなストレッチをすればいいの?」
そんな声をよく耳にします。巻き肩は、特定の筋肉の緊張と弱化が原因になっているため、ストレッチでバランスを整えることが大切です。
ここでは、自宅で気軽に行える巻き肩改善ストレッチを3つ紹介します。どれも特別な道具は必要なく、日常のすきま時間にできる内容です。
壁を使った「胸開きストレッチ」
まず試してほしいのが、壁を使ったシンプルなストレッチです。
やり方は、壁に片手をつき、体を反対方向にゆっくりとひねります。胸の前側(大胸筋)が伸びる感覚があればOKです。
呼吸は止めずに、ゆっくり鼻から吸って、口から吐くのを意識しましょう。
このストレッチを続けることで、前に引っ張られていた肩が少しずつ後ろへ戻りやすくなると言われています。
ただし、痛みを感じるまで無理に伸ばすのはNGです。引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretch
タオルを使った「肩甲骨寄せストレッチ」
次におすすめなのが、タオルを使った肩甲骨のストレッチです。
両手でタオルの端を持ち、背中の後ろで上下に引っ張るように動かします。
背中の真ん中あたりが「キュッ」と締まるような感覚があれば、正しくできています。
この動きは、肩甲骨を内側に寄せる筋肉(菱形筋や僧帽筋)を目覚めさせ、“開いた肩”を元の位置に戻すサポートになると言われています。
巻き肩姿勢が長い人ほど、最初は少し動かしづらいかもしれませんが、無理のない範囲で続けることがポイントです。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/
床でできる「仰向け開胸ストレッチ」
最後は寝ながらできるリラックスストレッチです。
ヨガマットやバスタオルを丸めて背中の下(肩甲骨のあたり)に置き、両腕を左右に広げて仰向けになります。
胸が自然に開き、肩が床に沈むような感覚があれば、姿勢改善に効果的と言われています。
このストレッチは、胸郭を広げて深い呼吸を促すため、呼吸が浅い人にもおすすめです。
テレビを見ながらでもできる簡単な方法なので、継続しやすいのも魅力です。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939
ストレッチは“続けること”が大事
どのストレッチも1回で劇的に変わるわけではありません。
毎日の生活に取り入れ、筋肉のバランスを整えることが、正しい姿勢への近道です。
「ながらストレッチ」でも構わないので、1日数分でも継続する意識を持つことが大切だと言われています。
#巻き肩ストレッチ #姿勢改善 #肩甲骨 #開胸 #猫背解消
巻き肩を改善するための「筋トレ習慣」:正しい姿勢を支える体づくり

「ストレッチをしても、また肩が前に戻ってしまう…」
そんな人に必要なのが、“姿勢を支える筋肉”を鍛えることです。
巻き肩は、筋肉のバランスが崩れている状態なので、弱くなった背中まわりを強化してあげることが重要だと言われています。
ここでは、姿勢を安定させるための代表的な筋トレを紹介します。
肩甲骨を寄せる「リバースプランク」
床に座り、手を体の少し後ろに置いて指先を前に向けます。
そこから、かかとを押し出すようにしてお尻を持ち上げ、頭からかかとまでを一直線に保ちます。
このとき、肩甲骨をしっかり寄せる意識を持つことがポイントです。
背中や腕の後ろ側の筋肉(広背筋・上腕三頭筋)が刺激され、肩を開く力を取り戻すと言われています。
最初は10〜15秒でも十分なので、無理のない範囲で継続していきましょう。引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/posture
ゴムバンドを使った「ローイング運動」
背中の筋肉を効果的に鍛える方法として、「チューブローイング」もおすすめです。
ゴムバンドを足に引っかけ、両手で持って肘を後ろに引きます。
このとき、肩がすくまないように意識しながら、肩甲骨を真ん中に寄せるイメージで動かすのがコツです。
猫背や巻き肩が気になる人にとって、背中の意識を取り戻すきっかけになると言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/
下半身の安定も「巻き肩改善」に効果的
意外かもしれませんが、巻き肩は肩だけでなく体幹や骨盤の安定性にも関係しています。
腹筋やお尻の筋肉(大殿筋・中殿筋)を鍛えることで、背骨を支える力が増し、自然と上半身の姿勢も整いやすくなります。
特に、片足立ちの姿勢をキープするようなバランストレーニングは、体の軸を安定させる効果があると言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/
筋トレは“姿勢リセット”のためのスイッチ
ストレッチが「ゆるめる」なら、筋トレは「支える」ためのアプローチです。
どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることが、巻き肩改善の近道です。
筋トレを続けることで姿勢を保つ筋肉が育ち、気づいたときに肩が自然と開く姿勢を維持しやすくなると言われています。
自分に合ったペースで続けよう
無理なトレーニングは逆効果になることもあるため、体の様子を見ながら少しずつ進めることが大切です。
1日5分でも構わないので、ストレッチと筋トレを習慣化し、正しい姿勢を“体が覚える”状態を目指しましょう。
#巻き肩改善 #姿勢リセット #肩甲骨トレーニング #体幹強化 #筋トレ習慣