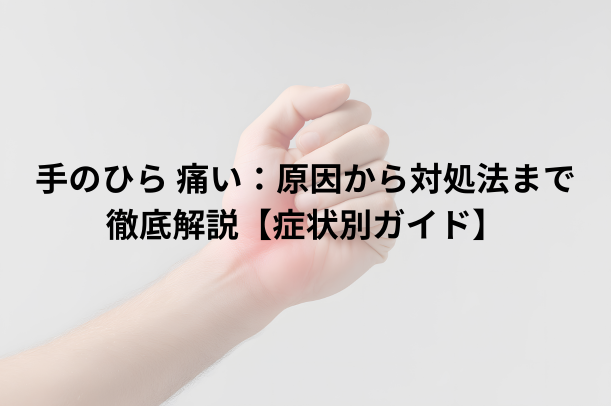「手のひらが痛い」とは? 症状と主な見え方パターン

部位ごとに異なる痛み方と特徴
「手のひらが痛い」といっても、どの位置が痛むかによって原因は変わると言われています。
たとえば親指の付け根側がズキッと痛む場合は、腱鞘炎や母指CM関節の炎症が関係していることが多いとされます。
一方で手のひらの中央あたりに鈍い痛みがある場合は、筋肉や腱の使いすぎ、あるいは神経の圧迫による違和感が関与しているケースもあるようです。
また、手首寄りの痛みでは、ドケルバン病や手根管症候群などの疾患が考えられるとも言われています(引用元: Medical Note、Ubie)。
痛みの種類と感覚の違い
痛みの出方にも個人差があります。
「鋭く刺すような痛み」「重だるい鈍痛」「ピリピリとしびれる感覚」など、同じ“痛み”でも感じ方がさまざまだと言われています。
動かしたときに強く出る場合は腱や関節の負担、安静時にうずくような痛みは神経や炎症による可能性があると考えられています。
痛みが出るタイミングや強さをメモしておくと、来院時に原因を見つけやすいとも言われています(引用元: くすりの窓口)。
併発しやすいサインと注意点
手のひらの痛みには、ほかの症状を伴うケースも少なくありません。
たとえば「腫れ」や「熱感」は炎症反応のサインとされ、「指の動きが制限される」「朝方にこわばる」「夜になるとズキズキする」といった特徴もみられることがあります。
こうした症状が続くと、慢性的な腱鞘炎や神経障害の前触れとなることもあるため、早めに専門家へ相談することがすすめられています。
また、痛みが片手だけでなく両手に広がる場合は、関節リウマチなど全身性の疾患が関与することもあると言われています(引用元: 済生会HP)。
#手のひらの痛み
#腱鞘炎対策
#神経圧迫症状
#整骨院アドバイス
#早期ケアの大切さ
痛みの原因(疾患・状態別の分類)

使いすぎ・反復ストレス型の痛み
手のひらの痛みの中でも特に多いのが、使いすぎによる炎症や腱の負担と言われています。パソコン作業やスマートフォン操作、家事や育児などで指や手首を繰り返し動かすことで、腱や腱鞘に炎症が起こりやすくなるそうです。代表的な疾患には「腱鞘炎」「ドケルバン病」「ばね指」などが挙げられます。これらは指を動かすたびに痛みや引っかかり感が出るのが特徴で、進行すると指が曲がったまま動かしづらくなることもあるとされています。早めに負担を減らし、炎症を悪化させないようにすることが大切と言われています(引用元:沢井製薬 健康サイト、宝塚リハビリ病院)。
神経圧迫型の痛み
手根管症候群は、手のひらから指先にかけて「しびれ」や「夜間の痛み」が出る代表的な神経圧迫疾患とされています。手首にある“手根管”というトンネル部分で正中神経が圧迫されることで起こると言われており、長時間のデスクワークやホルモン変化、糖代謝の乱れなどが関係するケースもあるようです。初期は「親指・人差し指・中指のしびれ」から始まり、進行すると物をつかみにくくなることも報告されています(引用元:メディカルノート、済生会HP、日本整形外科学会)。
関節・変性疾患型の痛み
年齢とともに関節の軟骨がすり減り、変形や炎症が起こることで痛みが出るケースもあります。特に**母指CM関節症(親指の付け根の関節痛)**は中年以降の女性に多く見られると言われており、ペットボトルのふたを開ける動作などで痛みが出やすいのが特徴です。関節の変性は自然な老化現象とも関係しているため、痛みが強いときは無理をせず、専門家による触診や検査で状態を確認することがすすめられています(引用元:世田谷かくた整形外科 成城学園前院)。
外傷・骨折系の痛み
転倒やスポーツで手をついたときの橈骨遠位端骨折や舟状骨骨折なども、手のひらの痛みとして現れることがあるそうです。痛みが強く、腫れや変形を伴う場合は、骨や靱帯の損傷が疑われると言われています。また、軽い打撲や捻挫であっても、炎症や腫れが長引くと慢性的な痛みに変わることもあるため注意が必要です。骨や関節の損傷は見た目では判断が難しいことが多く、レントゲンやMRIなどの検査が行われるケースもあります(引用元:メディカルノート)。
その他・まれな原因
比較的まれですが、ガングリオン(関節液が袋状にたまる良性のしこり)や、関節リウマチ・膠原病などの全身性疾患が原因となる場合もあると言われています。これらは手のひら以外の関節や全身の倦怠感を伴うこともあり、放置すると他の関節にも広がる可能性があると考えられています。
また、末梢神経や脊髄の障害によって手の痛みが出るケースもあり、神経内科やリウマチ専門医での評価が必要になることもあるそうです(引用元:湘南リウマチ膠原病内科、阿部整形外科、ドクターズ・ファイル)。
#手のひらの痛み
#腱鞘炎予防
#神経圧迫症状
#関節変性ケア
#ガングリオン注意
症状パターン別チェックリストであなたの痛みを判別

痛む時間帯をチェック
手のひらの痛みが夜間や明け方に強く出る場合、手根管症候群の可能性があると言われています。特に、夜中に「手がしびれる」「目が覚めるほどズキズキする」といった訴えが多いのが特徴です。これは、睡眠中に手首が自然に曲がることで正中神経が圧迫されるためと考えられています。朝起きたときに「指がこわばる」「手を振ると少し楽になる」ような感覚がある場合は、神経の通り道に負担がかかっている可能性があるとされています(引用元:済生会HP)。
指や手を使うと痛むかどうか
「家事やスマホ操作をしていると痛みが出る」「ペンを握るとズキッとする」といった動作時の痛みは、腱や腱鞘に負担がかかっているサインかもしれません。特に親指側の手首から手のひらにかけて痛む場合は、腱鞘炎やドケルバン病と呼ばれる炎症が関係していることが多いと言われています。痛みが強いときは無理をせず、手の使い方を見直したり、休息を取ることが改善の第一歩になるとされています。
腫れや熱感があるかどうか
手のひらが赤く腫れて熱を持つ場合、炎症が起きている可能性があると言われています。局所的な炎症では腱鞘炎や打撲が疑われますが、両手に対称的な腫れがあるときは関節リウマチなどの自己免疫疾患の初期症状であることも考えられます。こうした変化が続くときは、安静だけでなく専門家による触診や血液検査で原因を確認することがすすめられています。
動かしにくさ・引っかかり感があるか
「指を伸ばそうとしても引っかかる」「パチンと鳴るような違和感がある」ときは、**ばね指(弾発指)**と呼ばれる症状が考えられています。これは、指を動かす腱が通るトンネル(腱鞘)が狭くなり、腱がスムーズに滑らなくなる状態だそうです。進行すると痛みだけでなく、指の動き自体が制限されることもあるため、早めのケアが大切とされています。
痛みが広がる・しびれを伴うか
痛みが手首から指先、あるいは腕まで広がる場合は、神経の圧迫や炎症が原因の可能性があると考えられています。しびれや感覚の鈍さを伴うときは、神経系のトラブル(手根管症候群や頚椎由来の神経障害)に関連しているケースも報告されています。特にしびれが続く場合は、早めに専門的な評価を受けることがすすめられています。
外傷の有無やきっかけを振り返る
転倒や重いものを持ち上げた直後に痛みが出た場合は、打撲や骨折などの外傷による痛みの可能性があるとされています。初期は軽い痛みでも、数日後に腫れや内出血が目立ってくるケースもあるため注意が必要です。もし痛みが長引く、または手を動かせないほど強い場合は、整形外科などで画像検査を受けることがすすめられています。
#手のひらの痛み
#症状セルフチェック
#腱鞘炎サイン
#神経圧迫注意
#手根管症候群
自宅でできる対処法とセルフケア

安静のとり方・負荷を避ける工夫
まずは手を使いすぎないことが基本です。痛みを感じたときは、その手の動きをなるべく抑え、休ませる時間を増やすことが薦められています。たとえば、家事やスマホ操作などを連続して行わず、こまめに休憩を入れるよう意識するのがいいでしょう。ユビーでも「手を繰り返し動かす動きを避け、負荷を軽減することが重要」と説明されています(引用元:ユビー Q&A「手のひらが痛い場合の治療や予防方法」)症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie
また、痛みを感じる動作(重いものを持つ、手首を捻る、指を強く曲げるなど)はできるだけ控えるようにします。負担がかかりにくい道具の使い方、例えば物を持つときは手首をまっすぐにする、肘を体に近づけて使うなどの工夫も有効です(引用元:ハレバレ プラス「手指と手首の痛み対策」)ハレバレ プラス
ストレッチ・マッサージ・手指運動の具体例(注意点付き)
手首や指先を軽く伸ばすストレッチは、血行促進や筋緊張の緩和に働くと言われています。たとえば、片手を前に伸ばし、もう片方の手で指先を引き下げるようにゆっくり刺激を加えるなど。ユビーのQ&Aにも「指や手首を軽く動かすストレッチ」が即効性のある対処法として紹介されています(引用元:ユビー Q&A「手の指のしびれに対して自分でできる即効性のある対処法」)症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie
マッサージでは、手のひら・指間・手首前腕にかけて優しく揉むことで筋肉のこわばりを取るイメージです。ただし、痛みが強いときには無理に押しすぎないことです。刺激が強すぎると逆効果になるケースもあります。
手指運動としては、握ったり開いたりをゆっくり繰り返す運動や、指一本ずつ軽く反らしたり曲げたりする運動もおすすめです。ただし、痛みが悪化するようなら中止した方がよいでしょう。
冷湿布・温湿布・市販の鎮痛剤の活用法(使ってよい場合・注意点)
痛みや腫れが明らかに出ているときは、冷湿布(保冷剤や氷を包んだタオルなど)を15〜20分程度あてて、炎症を抑えるほうがよいことがあります。一方で、痛みが慢性的・鈍痛傾向で、炎症が落ち着いてきた段階では温湿布や温めるケアで血流を促すことも効果が期待されます(引用元:リハサク 手根管症候群対処法)rehasaku.net
市販の鎮痛剤(非ステロイド性消炎鎮痛薬)入りの湿布や外用薬は、局所の痛みを和らげる手助けになる可能性があります。ただし、連続使用しすぎないようにすること、また過剰に使うと副作用が出やすくなることには注意が必要です。皮膚の状態を見ながら使うべきだと言われています。
装具・サポーターの使い方(手首固定・親指固定など)
痛みがあるときは、手首や親指を安定させる装具・サポーターを併用すると負荷が軽くなるケースがあります。手首を曲げすぎないように保持するタイプや、親指の付け根を支える形のものが市販されています。特に夜間、無意識に手首を曲げてしまう人には、夜用固定タイプが使われることもあるようです(引用元:リハサク 対処法)rehasaku.net
ただし、装具やサポーターを使うときは、きつく締めすぎて血流を妨げないようにすることが重要と言われています。痛みが変わらない/悪化するようなら使用を中止し、専門家に相談を検討したほうがよいでしょう。
日常生活の改善(手の使い方・休憩タイミング・姿勢・道具選びなど)
普段の生活習慣をちょっと見直すだけでも、痛みの悪化を防ぐ助けになるかもしれません。
たとえば、キーボードやマウス操作時に手首を反らせないよう、肘近くで使う、パームレストやクッションを使って手首の安定を補うといった工夫が有効と言われています(引用元:ハレバレ プラス)ハレバレ プラス
また、重い物を持つときは手を伸ばさず体に近づけて持つ、連続作業は30分〜1時間に一度は休憩を入れて手を振る、ゆるめるといったやり方も有効です。
さらに、手首・指だけでなく、肩〜首の張りをほぐす運動を取り入れることで、腕全体の血流や神経の流れを改善する助けになると考えられています(引用元:ハレバレ プラス)ハレバレ プラス
#手のひら痛みケア
#自宅セルフケア
#手首ストレッチ
#サポーター活用
#日常動作見直し
受診すべき目安と医師での診断・治療の流れ

受診を考えるタイミング
手のひらの痛みが2週間以上続く、または徐々に悪化している場合は、自己判断で放置せず、早めの来院がすすめられています。特に「物を握ると痛い」「手を使うとしびれる」「関節が変形してきた」などのサインがあるときは、腱や神経、関節の異常が隠れていることもあるそうです。
また、「夜になると痛みで目が覚める」「朝にこわばりを感じる」といった症状も注意が必要とされています。これらは炎症や神経圧迫の初期サインの可能性があり、整形外科やリウマチ科での早期検査が勧められています(引用元:メディカルノート、メディエイドオンライン)。
何科を受診すべきか
痛みの原因によって、来院先の選び方も変わります。
- 整形外科:腱鞘炎、手根管症候群、関節炎など、骨・筋肉・腱に関わる症状。
- リウマチ科:手の関節に左右対称の腫れやこわばりがある場合。
- 神経内科:しびれや感覚低下など神経由来の痛みが疑われるケース。
- 皮膚科:湿疹や発疹を伴う場合。
症状がどれに当てはまるかわからないときは、まず整形外科を訪ねるのが一般的だと言われています(引用元:くすりの窓口)。
医師が行う検査・診断手順
来院すると、まず問診と触診によって痛みの部位や範囲、経過を確認します。そのうえで必要に応じて画像検査(X線・MRI・超音波)や神経伝導検査を行い、筋肉・腱・神経の状態を詳しく調べる流れが多いようです。
特に神経障害が疑われる場合は、しびれの有無や感覚の範囲を細かく確認し、手根管症候群や頸椎の関与なども含めて判断されることがあるとされています(引用元:メディカルノート)。
治療オプション(保存療法・投薬・注射・手術など)
多くのケースでは、まず保存療法(安静・ストレッチ・湿布・装具使用)が選ばれる傾向にあります。痛みや炎症が強い場合は、消炎鎮痛薬の内服や局所への注射などで炎症を抑える方法も取られるそうです。
それでも改善が見られない場合や、神経圧迫が進行しているケースでは手術による除圧を検討することもあります。ただし、ほとんどの人は保存的なアプローチで改善することが多いと言われています(引用元:メディカルノート)。
治療を受ける上での注意点・予後
検査後は、日常生活での動作改善も並行して行うことが重要です。痛みが軽くなっても、すぐに負担をかけすぎると再発しやすいと言われています。手の動きや姿勢、使う道具を見直しながら、少しずつ動かす範囲を広げるようにしましょう。
また、慢性的な症状ほど改善には時間がかかる傾向があるため、焦らず専門家のアドバイスを継続的に取り入れることが大切だとされています(引用元:メディエイドオンライン)。
#手のひら痛み
#受診タイミング
#整形外科検査
#手根管症候群
#保存療法