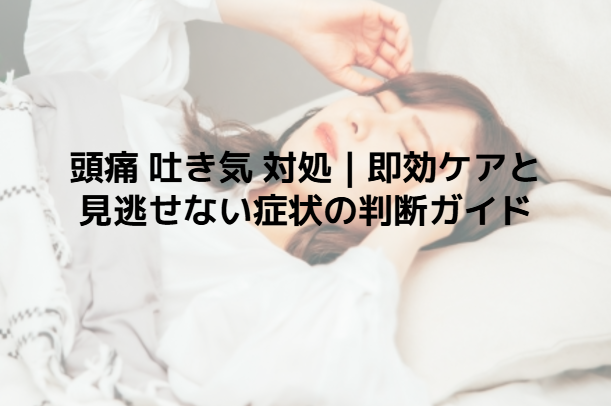頭痛に吐き気を伴うとき、考えられる原因とリスク

「頭がズキズキして気持ち悪い」「吐き気まで出てきて仕事にならない」──そんな経験をしたことがある人は少なくありません。
頭痛に吐き気を伴うときは、単なる疲れや寝不足だけでなく、体の中で何らかの異常が起きているサインの場合もあると言われています。
ここでは、主な原因と注意したいリスクについて整理してみましょう。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
片頭痛による吐き気
頭痛と吐き気が同時に起こる代表的な原因が「片頭痛(偏頭痛)」です。
片頭痛は、脳の血管が一時的に拡張し、その周囲の神経を刺激することで痛みを感じると言われています。
このとき、脳の興奮や血管の変動が自律神経に影響し、吐き気や光・音への過敏反応を伴うことも多いとされています。
特徴としては、「ズキズキと脈打つような痛み」「片側だけの痛み」「安静にしても治まらない痛み」が挙げられます。
発作の前に視覚の異常(チカチカする光や視野の欠け)が出る人もおり、これを「前兆あり片頭痛」と呼ぶケースもあります。
引用元:https://medicalook.jp/sleep-lack-headache/
緊張型頭痛が悪化したケース
首や肩の筋肉がこわばることで起こる「緊張型頭痛」も、吐き気を伴うことがあります。
姿勢の乱れや長時間のデスクワーク、睡眠不足などが続くと、筋肉のこわばりが神経を刺激し、血流が悪化することで痛みが強まると言われています。
通常は「締め付けられるような痛み」が特徴ですが、長引くことで自律神経が乱れ、吐き気や目の疲れ、集中力の低下を感じる人も多いようです。
このタイプの頭痛はストレスとも関係が深く、リラックスや姿勢改善が対策のポイントになると言われています。
引用元:https://www.kango-roo.com/learning/1209/
くも膜下出血や脳腫瘍などの重大疾患のサイン
頭痛と吐き気が突然強く現れ、「今までにない痛み」を感じるときは、脳に関わる疾患の可能性も否定できません。
代表的なものに「くも膜下出血」や「脳腫瘍」「髄膜炎」などがあり、これらは命に関わるケースもあるとされています。
特に以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関に相談することがすすめられています。
- バットで殴られたような激しい痛み
- 急に吐き気・嘔吐が止まらない
- ろれつが回らない、手足のしびれがある
- 意識がもうろうとする
これらは単なる片頭痛とは異なり、早期の検査・施術が必要なサインと考えられています。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
自律神経やホルモンバランスの乱れも影響
女性の場合、ホルモンバランスの変動(生理周期・排卵期など)により頭痛と吐き気が同時に起こることがあると言われています。
また、睡眠不足やストレス、気圧の変化によって自律神経が乱れると、脳血流の調整がうまくいかず、頭痛や吐き気が出やすくなることもあります。
特に季節の変わり目や気候変動が激しい時期は、体がストレスを受けやすいため注意が必要です。
放置せず、原因を見極めることが大切
頭痛に吐き気を伴う状態は、体が「休みたい」「助けてほしい」と訴えているサインとも言われています。
一時的な疲れであっても、繰り返すようなら早めに専門家に相談し、原因をしっかり確認することが大切です。
正しい対処と生活リズムの見直しで、多くの場合は改善が期待できると言われています。
#頭痛と吐き気 #片頭痛 #緊張型頭痛 #くも膜下出血リスク #自律神経の乱れ
最初にやるべき即効対処(セルフケア)

「頭痛と吐き気が同時にきたらどうすればいいの?」──そんなとき、まず大切なのは“無理をしないこと”です。
無理に動いたり、我慢して仕事や家事を続けてしまうと、痛みや吐き気がさらに強くなることもあると言われています。
ここでは、つらい症状が出たときに自宅で試せる即効性のある対処法を紹介します。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
暗く静かな場所で休む
片頭痛や緊張型頭痛の多くは、光や音などの刺激で症状が悪化する傾向があります。
そのため、まずは照明を落とし、静かな環境で横になることがすすめられています。
カーテンを閉めて明るさを抑え、スマホやパソコンの画面は見ないようにしましょう。
「少し目を閉じて深呼吸するだけでも落ち着いた」と感じる人も多いようです。
吐き気が強いときは、上半身を少し起こすような体勢で休むと楽になることがあります。
引用元:https://medicalook.jp/sleep-lack-headache/
冷却と温熱の使い分け
頭痛のタイプによって、「冷やす」「温める」のどちらが良いかは異なります。
ズキズキと脈打つような片頭痛の場合は、こめかみや首を冷やして血管の拡張を抑えると痛みが落ち着きやすいと言われています。
一方で、締めつけられるような緊張型頭痛では、肩や首まわりを温めて血行を良くすることが効果的とされています。
冷却にはタオルに包んだ保冷剤を、温熱には蒸しタオルを活用すると手軽です。
どちらも“やりすぎない”ことが大切で、10分程度を目安に行うのがおすすめです。
引用元:https://www.kango-roo.com/learning/1209/
水分補給と軽い食事で回復を促す
吐き気があるときは水を飲むのもつらいかもしれませんが、脱水が進むと血流が悪化して頭痛が強まることがあると言われています。
無理のない範囲で、常温の水やスポーツドリンクを少しずつ摂るようにしましょう。
また、空腹状態も吐き気を悪化させる原因のひとつとされています。
消化のよいおかゆやバナナなどを少量口にするだけでも、体が落ち着きやすくなります。
深呼吸と姿勢の調整
痛みや吐き気があると、無意識のうちに呼吸が浅くなり、筋肉がこわばる傾向があります。
ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐き出す「深呼吸法」を意識することで、副交感神経が働き、リラックスしやすくなると言われています。
また、座っている場合は、猫背にならないよう背筋を伸ばして肩の力を抜くと、首の緊張が軽減されやすいです。
吐き気が強いときは、頭を少し前に倒すと楽になるケースもあります。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
ツボ押しやストレッチで血流を促す
後頭部のくぼみにある「風池(ふうち)」、こめかみの少し上にある「太陽(たいよう)」などは、頭痛と吐き気の緩和に効果があるとされています。
指の腹で3〜5秒押して離す動きを数回繰り返すと、血流が促されやすくなると言われています。
また、首や肩を軽く回すストレッチを取り入れることで、緊張型頭痛によるこりの軽減にもつながります。
我慢せず、まずは「休息」が最優先
頭痛と吐き気があるときは、「根性で乗り切る」よりも「しっかり休む」ことが何より大切です。
痛みを我慢して無理に動くと、症状が長引く場合もあるため、まずは体を横にして落ち着かせましょう。
それでも改善しない場合や、繰り返すようなら早めの検査を検討することがすすめられています。
#頭痛と吐き気 #即効対処法 #セルフケア #冷却温熱法 #深呼吸リラックス
薬や市販品を使う際の注意点と使い方

頭痛と吐き気が同時に起きると、「とにかく薬で早く抑えたい」と思う方も多いでしょう。
しかし、薬の種類や使うタイミングを間違えると、効果が得られにくいどころか、症状が悪化することもあると言われています。
ここでは、頭痛薬や吐き気止めを使うときの注意点や、正しい使い方を解説します。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
市販の鎮痛薬を使うときの基本
頭痛時に使われる代表的な市販薬には、アセトアミノフェン系、イブプロフェン系、ロキソプロフェン系などがあります。
どの薬も炎症や血管の拡張を抑えることで痛みを和らげる作用があると言われていますが、体質や頭痛のタイプによって効果が異なります。
片頭痛のようにズキズキする痛みにはイブプロフェンやロキソプロフェン系が使われることが多く、
筋肉のこわばりが原因の緊張型頭痛では、アセトアミノフェン系が体に優しく使いやすいとされています。
ただし、胃が弱い方や空腹時に服用すると、胃痛や不快感が出ることがあるため注意が必要です。
引用元:https://medicalook.jp/sleep-lack-headache/
吐き気が強いときの対処
吐き気が強くて薬を飲めない場合、無理に飲み込むのは避けましょう。
無理をすると吐き戻してしまい、薬の成分が吸収されないこともあります。
このようなときは、体を横向きにして安静にし、少し落ち着いてから水分を摂ってみてください。
どうしても薬が必要な場合は、医療機関で坐薬や注射など別の投与方法を相談するのが良いとされています。
引用元:https://www.kango-roo.com/learning/1209/
薬を使うタイミングと回数
頭痛薬は、「痛みが出始めたタイミングで使う」のがポイントだと言われています。
強い痛みが出てからでは薬の効果が出るまでに時間がかかり、効きにくくなることがあります。
ただし、1日の服用回数や間隔を守ることも重要です。
多くの市販薬は4〜6時間あけて服用するように設計されており、1日3回以内が基本とされています。
頻繁に服用しすぎると「薬物乱用頭痛」を引き起こすこともあるため、週に10回を超えるようなら一度専門家に相談しましょう。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
吐き気止め・制吐剤の活用について
市販の吐き気止め薬には、胃腸の動きを整えて吐き気を軽減するタイプがあります。
ただし、頭痛由来の吐き気にはあまり効果がないこともあり、原因に合った薬を選ぶことが大切です。
医療機関では、片頭痛や緊張型頭痛に対して鎮痛薬と制吐剤を組み合わせることもあるとされています。
吐き気がひどい場合や頻繁に繰り返す場合は、自己判断せず一度触診を受けて原因を確認すると安心です。
薬に頼りすぎない工夫も大切
頭痛薬は一時的に症状を抑えるには有効ですが、根本原因の改善にはつながらないことが多いと言われています。
薬を飲まなくてもすむように、日頃から睡眠・姿勢・ストレスケアを整えることが大切です。
また、「いつもの薬が効かなくなってきた」と感じる場合は、薬の種類を変えるよりも、まずは医師や薬剤師に相談することがすすめられています。
#頭痛と吐き気 #頭痛薬の使い方 #吐き気止め #市販薬の注意点 #薬物乱用頭痛
医療受診すべきタイミングと診療の流れ

頭痛と吐き気が続くと、「もう少し様子を見よう」と思ってしまう人も多いかもしれません。
しかし、原因によっては放置することで症状が悪化したり、思わぬ疾患が隠れている場合もあると言われています。
ここでは、受診を検討すべきサインと、医療機関での一般的な流れについて紹介します。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
受診を考えるべき症状
一時的な頭痛や軽い吐き気であれば、休息やセルフケアで改善することもあります。
しかし、次のような症状がある場合は早めの来院がすすめられています。
- 痛みが数日以上続く、または頻繁に起こる
- 吐き気や嘔吐を繰り返す
- これまでにないほど強い痛みが突然現れた
- ろれつが回らない、手足がしびれる、意識がもうろうとする
- 発熱、首のこわばり、視覚異常を伴う
これらは、くも膜下出血・髄膜炎・脳腫瘍などの重大疾患の初期サインの可能性もあるため、自己判断せず受診が望ましいとされています。
引用元:https://medicalook.jp/sleep-lack-headache/
どの診療科に行けばいいか
頭痛と吐き気が主症状の場合、まずは脳神経外科または頭痛外来が適しています。
症状の原因を見極めるために、頭部の血管や神経の状態を確認できる検査を行うことが多いです。
また、肩こりや自律神経の乱れなど体の緊張が関係していると考えられる場合は、整形外科や整骨院で筋肉や姿勢の状態をチェックするケースもあります。
一方、ホルモンバランスやストレスによる影響が疑われる場合は、内科や婦人科での相談がすすめられています。
受診時に行われる検査
医療機関では、まず問診で「いつから」「どんな痛み」「吐き気の頻度」「既往歴」などを確認します。
そのうえで、必要に応じて以下のような検査が行われます。
- 画像検査(CT・MRI):脳の出血や腫瘍を確認
- 神経学的検査:しびれ・筋力低下・感覚異常の有無を調べる
- 血液検査:炎症やホルモンの異常を確認
- 眼底検査:脳圧の上昇などを確認するために実施されることも
これらの結果をもとに、片頭痛や緊張型頭痛といった一次性の頭痛か、脳や神経の疾患による二次性頭痛かを判断すると言われています。
引用元:https://www.kango-roo.com/learning/1209/
治療・施術の流れ
検査結果に応じて、痛みの種類や原因に合わせたアプローチが行われます。
片頭痛であれば、血管の拡張を抑える薬(トリプタン系)や制吐剤の併用、緊張型頭痛では筋肉をほぐすストレッチや温熱療法などが取り入れられることがあります。
また、ストレスが関係している場合は、睡眠指導やリラクゼーション指導などの生活面でのサポートも行われることが多いです。
整骨院などでは、首・肩まわりの筋緊張を緩める施術が頭痛軽減につながるケースもあると言われています。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
早期対応で「重症化」を防ぐ
「吐き気があるけど、いつもの頭痛だから大丈夫」と軽く見てしまうことが一番危険です。
体がいつもと違うサインを出しているときこそ、早めの行動が大切です。
軽症のうちに正しい原因を知ることで、治療期間が短く済み、再発予防にもつながりやすいと言われています。
我慢せずに相談することで、日常生活の安心感が大きく変わります。
#頭痛と吐き気 #受診目安 #脳神経外科 #検査の流れ #早期対応
再発を防ぐための生活習慣と予防策

頭痛と吐き気の原因がわかっても、同じような症状を何度も繰り返す人は少なくありません。
薬や施術だけに頼らず、日常生活の中で「再発しにくい体の状態をつくること」が大切だと言われています。
ここでは、頭痛と吐き気を予防するための生活習慣やセルフケアのポイントを紹介します。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
睡眠リズムを整える
寝不足や睡眠の質の低下は、頭痛や吐き気の大きな原因のひとつとされています。
就寝・起床の時間を一定にすることで、自律神経が整い、脳や筋肉の疲労回復がスムーズになりやすいです。
寝る直前のスマホ・テレビ・パソコンの使用を控え、部屋を暗くして深い眠りを促すことも重要です。
また、休日に寝だめをするのは一見よさそうに思えますが、体内時計を乱す原因になるため、普段と大きくずれないようにするのが理想とされています。
引用元:https://medicalook.jp/sleep-lack-headache/
姿勢と筋肉バランスを見直す
デスクワークやスマホ操作によって前かがみ姿勢が続くと、首や肩の筋肉が緊張し、血流が悪化して頭痛を引き起こしやすくなります。
長時間同じ姿勢をとるときは、1時間に1回程度、軽くストレッチや肩回しを行うと良いでしょう。
また、座るときは背筋を伸ばし、頭が体の中心にくるよう意識することで首への負担を減らせます。
最近では、椅子の高さやモニター位置など、作業環境を整えることが緊張型頭痛の予防につながるとも言われています。
引用元:https://www.kango-roo.com/learning/1209/
食事と水分の取り方に気をつける
偏った食生活やカフェインのとりすぎ、アルコールの摂取は頭痛や吐き気を誘発することがあります。
特にカフェインは一時的に血管を収縮させる効果がありますが、過剰摂取や急な断ち方がリバウンド頭痛を引き起こす可能性があるとされています。
また、水分不足も血液の循環を悪くし、頭痛を助長します。
こまめに常温の水を飲み、1日あたり1.5〜2リットルを目安にすると良いでしょう。
バランスの取れた食事を心がけることが、頭痛体質の改善につながるとも言われています。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5310/
ストレスコントロールとリラクゼーション
精神的なストレスは、自律神経を乱し頭痛や吐き気を悪化させる大きな要因です。
1日の終わりに深呼吸やストレッチを取り入れたり、軽い運動を習慣にすることで副交感神経が働きやすくなります。
音楽を聴いたり、アロマを使うなど“自分に合ったリラックス法”を見つけるのも効果的だと言われています。
特に、仕事の合間に短時間でも目を閉じて深呼吸することで、脳の緊張が和らぎやすくなることが知られています。
気圧・気候変化への対応
気圧の変化が頭痛や吐き気を悪化させることがあります。
天候の変化が激しい時期には、耳のマッサージや首まわりの温めを行うことで、内耳の血流が改善しやすくなると言われています。
また、気象アプリなどで気圧の変動を把握しておくことで、体調の変化を事前に予測できるようになります。
自分の体調リズムを記録する「頭痛日記」をつけることも、再発防止に役立つ方法のひとつです。
「小さな改善の積み重ね」が再発予防につながる
頭痛や吐き気を完全にゼロにするのは難しくても、生活習慣を整えることで発作の頻度や強さを軽減できると言われています。
薬に頼る前に、まずは“日常の質”を見直すことが、長期的な改善への近道になるでしょう。
#頭痛予防 #生活習慣改善 #姿勢ケア #ストレス対策 #気圧頭痛対策