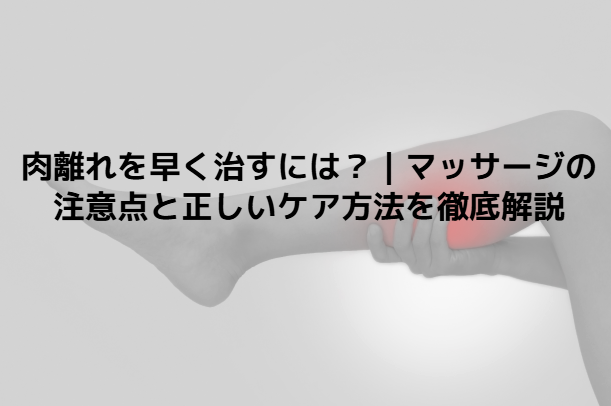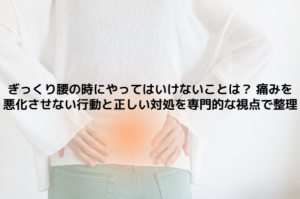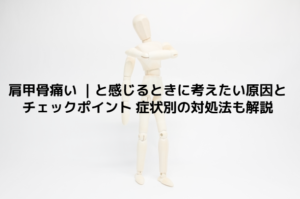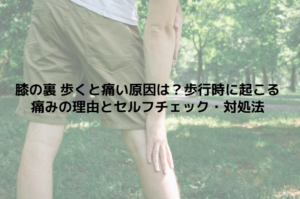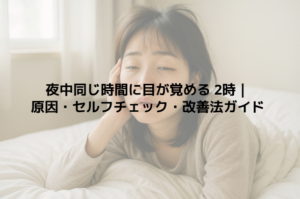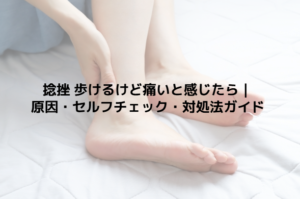肉離れとは?基本的な仕組みと回復までの流れ

筋肉が「引き伸ばされて切れる」ような状態
「肉離れ」とは、筋肉が強く引き伸ばされた際に筋繊維の一部が損傷してしまう状態のことを指すと言われています。スポーツ中の急なダッシュやジャンプ、あるいは急に体をひねったときなどに起こることが多く、特に太ももの裏(ハムストリング)やふくらはぎでよく見られます。
受傷した瞬間に「ブチッ」とした感覚がある人もいれば、違和感程度で済む人もいます。ただ、放っておくと内出血や腫れが強く出たり、歩くのもつらくなったりするケースもあるため、初期対応が非常に大切です。
肉離れは、筋肉が完全に切れてしまう「重度」から、わずかに損傷した「軽度」まで3段階に分けられると言われています。軽度の場合は2〜3週間ほどで改善傾向が見られますが、重度になると数ヶ月かかることもあります。いずれの場合も、焦って動かすよりもまずは冷却や安静を優先することが基本です。
引用元:https://www.krm0730.net/blog/2535/
回復の流れと「早く治す」ための考え方
肉離れの回復は、一般的に「炎症期」「回復期」「リハビリ期」の3段階に分けられるとされています。
最初の炎症期(約3日〜1週間)は、筋肉の損傷部分に炎症反応が起き、腫れや痛みが強く出る時期です。この間はマッサージやストレッチを避け、安静と冷却を徹底することが重要といわれています。
次の回復期(1〜3週間ほど)では、炎症が落ち着き、損傷した筋肉が少しずつ修復を始めます。この時期になると、軽いストレッチや関節を動かす運動を取り入れてもよいケースがありますが、無理は禁物です。
最後のリハビリ期では、筋肉の再生とともに柔軟性・筋力を戻す段階に入ります。ここで再発を防ぐためのストレッチや筋トレが効果的といわれています。
「早く治すためにマッサージをする」という考え方は、一見正しそうですが、炎症が残っている時期に強い刺激を与えると悪化するおそれもあります。状態に合わせて、正しいタイミングで行うことが大切です。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/pushups-effect/
引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/145/
#肉離れ #筋肉損傷 #早期回復 #マッサージのタイミング #リハビリ
肉離れを早く治すために大切な初期対応(RICE処置)

「早く治したい」と焦るほど、冷静な対処が必要
肉離れを起こした直後は、「少し休めば大丈夫」と思ってしまいがちですが、最初の対応で回復までの期間が大きく変わると言われています。筋肉が損傷した直後は、内部で出血や炎症が起きており、その状態で動かしたりマッサージを行ったりすると、かえって症状を悪化させることがあるのです。
この時期に大切なのが、いわゆる**RICE処置(ライス処置)**と呼ばれる応急対応です。これは、Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の4つの頭文字を取った方法で、スポーツ現場などでも広く行われています。
まずは「動かさないこと」が基本。痛みが出た部分に負荷をかけないように姿勢を整え、患部を心臓より少し高い位置に置きます。そのうえで、タオルなどで包んだ氷や保冷剤を使って冷やすと、内出血や腫れを抑えられると言われています。冷却は1回15〜20分を目安にし、感覚が鈍くなったら間を空けながら繰り返すのがよいとされています。
圧迫は、包帯やテーピングなどを軽く巻く程度で十分です。強く締めすぎると血流が悪くなるおそれがあるため、皮膚の色や感覚を確認しながら行いましょう。
引用元:https://www.krm0730.net/blog/2535/
初期対応の目的は「ダメージを広げないこと」
RICE処置は、あくまで応急的なものであり、筋肉の修復を早めるためというより、損傷の拡大を防ぐために行うものです。早く治したいと思っても、炎症が治まるまでは刺激を与えないことが大切とされています。
また、痛みが強い場合や腫れが広範囲に出ている場合は、自己判断で動かすのではなく、整骨院や専門家に来院して触診やエコー検査で損傷の程度を確認することが望ましいです。無理をしてしまうと、肉離れが慢性化したり、再発のリスクが高まる可能性もあるといわれています。
一見地味に感じるRICE処置ですが、この段階でしっかり炎症を抑えておくことで、その後の回復スピードやリハビリの効果が高まりやすくなるとされています。焦らず丁寧に対処することが、結果的に“早く治す近道”につながるのです。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/pushups-effect/
引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/145/
#肉離れ #RICE処置 #応急対応 #早期改善 #冷却と安静
マッサージを始めてよいタイミングと注意点

「早くマッサージすれば治る」は誤解かもしれません
肉離れをした後、「マッサージをすれば早く治る」と考える人は少なくありません。ですが、これはタイミングを間違えると逆効果になる可能性があると言われています。損傷した筋肉は、受傷直後に炎症を起こしており、その段階で刺激を与えると、出血が広がったり痛みが増したりするおそれがあるのです。
一般的に、マッサージを行ってよいのは**炎症が落ち着いた回復期(受傷から3日〜1週間後)**と言われています。この時期に入ると、損傷した筋肉の修復が始まり、軽い刺激が血流を促して回復をサポートする効果が期待できるとされています。ただし、痛みが残っている場合は無理をせず、まずは専門家に相談するのが安心です。
引用元:https://www.krm0730.net/blog/2535/
自分でマッサージを行う際のポイント
もしセルフマッサージを行う場合は、「押す」よりも「さする」ようにして、筋肉の表面を優しく温める感覚で行うのが基本です。力を入れすぎると筋繊維を再び傷つける可能性があるため注意が必要です。
また、筋肉を直接もむよりも、温めることで血流を促すほうが安全といわれています。入浴後のリラックスした状態で、軽くストレッチを組み合わせるのもよい方法です。
一方で、痛みや腫れが残っているうちはマッサージを控えましょう。症状が落ち着かないまま刺激を加えると、再出血や炎症の長期化につながることがあるといわれています。
専門的な施術では、筋肉の硬直を和らげる「軽擦法(けいさつほう)」や「温熱療法」などが用いられることもあります。これらは筋肉の修復を助けるサポート的な役割を持つとされており、自己流ではなくプロの判断を取り入れることが重要です。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/pushups-effect/
引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/145/
#肉離れ #マッサージ #タイミング #セルフケア #炎症期
肉離れ後のストレッチはいつから?安全に始めるコツ

無理なストレッチは回復を遅らせることも
肉離れをしたあと、「筋肉を柔らかくしたほうがいいのでは?」と早い段階でストレッチを始めようとする人も多いですが、炎症が残っている時期に伸ばすのは危険だといわれています。受傷直後は、筋繊維がまだ修復途中で非常にデリケートな状態です。その段階で無理に伸ばすと、せっかく治りかけていた部分が再び裂けてしまう可能性があります。
ストレッチを行ってよいのは、痛みや腫れが落ち着いてからです。目安としては、受傷後1〜2週間ほど経ち、歩行時に違和感がない程度に改善してきた頃と言われています。この時期になると、軽い可動域運動やストレッチを少しずつ取り入れることができるようになります。ただし、「伸ばして痛い」と感じる動きはまだ早い段階なので控えましょう。
引用元:https://www.krm0730.net/blog/2535/
効果的なストレッチのやり方と注意点
肉離れの回復期に行うストレッチは、「伸ばす」というよりも筋肉を目覚めさせるようにゆっくり動かすイメージが理想です。反動をつけず、呼吸を止めずに、10〜20秒かけてじんわりと筋肉を伸ばすようにします。
また、ストレッチ前に軽い温熱で体を温めておくと、血流が良くなり筋肉の柔軟性が上がるため、より安全に行えるといわれています。
特に太ももやふくらはぎなどの大きな筋肉は再発しやすいため、ストレッチの強度を上げる際は焦らず少しずつ進めることが大切です。日によって張りや違和感の出方も違うので、その日の体の状態を感じながら行うことが何より重要です。
さらに、ストレッチの段階に入っても、急なダッシュやジャンプなど強い負荷は避けるべきです。完全に痛みが取れ、専門家の確認を経てから本格的な運動再開をするのが安全といわれています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/pushups-effect/
引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/145/
#肉離れ #ストレッチ #リハビリ #筋肉回復 #柔軟性アップ
肉離れの再発を防ぐために意識したいポイント

「治った」と油断すると再発しやすい理由
肉離れは、一度改善したように見えても再発しやすいケガのひとつと言われています。その理由は、筋肉が完全に修復するまでには時間がかかるのに、痛みが軽くなるとすぐに運動を再開してしまう人が多いからです。表面上は動けるように見えても、筋繊維の内部ではまだ修復が進行中のこともあります。その状態で急な動きや強い負荷をかけると、再び筋肉が裂けてしまう可能性があるのです。
また、筋肉のアンバランスも再発の原因とされています。たとえば太ももの前側と後ろ側の筋力差、あるいは左右の足のバランスの崩れなどがあると、同じ部位に負担が集中しやすくなると言われています。そのため、痛みがなくなってからも筋力バランスを整えるトレーニングを継続することが大切です。
引用元:https://www.krm0730.net/blog/2535/
再発予防のための体づくりと習慣づけ
肉離れの再発を防ぐためには、筋肉そのものを強くするだけでなく、柔軟性と血流の良さを保つ生活習慣も重要とされています。運動前のウォーミングアップでしっかり筋肉を温めること、運動後のクールダウンで軽くストレッチを行うことなど、基本的なことを丁寧に続けるだけでも再発リスクを減らせるといわれています。
また、入浴や軽いマッサージなどで日常的に血流を促すことも有効です。筋肉が冷えたり硬くなったりすると、わずかな動きでも筋繊維が引き伸ばされやすくなるため、体を温かく保つことがケガの予防につながります。
特にスポーツをしている人は、「痛みが引いた=完治」ではないことを意識することが大切です。リハビリの段階で専門家に触診してもらいながら、可動域や筋力の左右差をチェックし、段階的にトレーニングを再開するようにしましょう。
焦らず、自分の体のサインを聞きながら回復を進めていくことが、最も確実な“早く治す方法”だと言われています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/pushups-effect/
引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/145/
#肉離れ #再発予防 #ウォーミングアップ #リハビリ #筋バランス