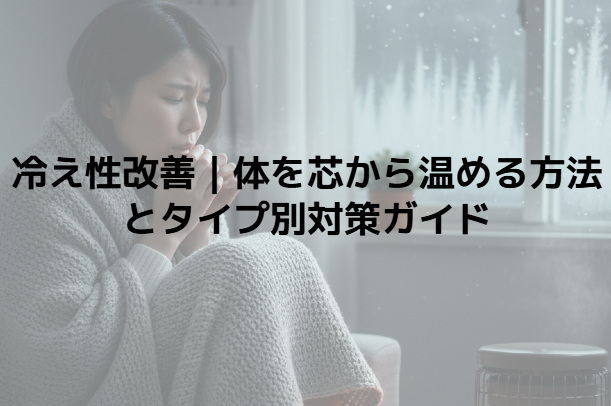冷え性とは? 種類と体への影響

冷え性の基本と仕組み
「手足が冷たくて寝つけない」「夏でも指先が冷える」――そんな悩みを持つ人は少なくありません。
冷え性とは、体の末端まで血液がうまく行き届かず、体の一部が慢性的に冷えている状態を指すと言われています。
特に女性に多く見られますが、最近では男性や若年層にも増えているとされています。
人間の体は、血液を通して熱を全身に届けることで体温を一定に保っています。
しかし、血行が悪くなると手足の先まで十分な熱が運ばれず、温度差が生じるのです。
この状態が続くと、冷えだけでなく、疲労感や肩こり、頭痛、胃腸の不調、さらには免疫力の低下にもつながると考えられています。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
冷え性の種類と特徴
冷え性にはいくつかのタイプがあり、人によって感じ方や原因が異なります。
代表的なものとして、以下の4つが挙げられます。
- 四肢末端型(ししまったんがた)
手足の先が特に冷えるタイプ。血管の収縮や血流の悪さが影響しているとされています。デスクワークや運動不足の人に多い傾向があります。 - 下半身型
腰から下、特に太ももやふくらはぎが冷えやすいタイプ。長時間の座り仕事や骨盤の歪み、筋肉量の不足が関係していることがあると言われています。 - 内臓型
手足は冷えていないのに、お腹の中が冷えるタイプ。ストレスや自律神経の乱れ、食生活の乱れが原因となりやすく、便秘や倦怠感を伴うこともあります。 - 全身型
体全体が冷えるタイプで、基礎代謝の低下や甲状腺ホルモンの影響が関係しているとされています。加齢や慢性的な疲労も要因の一つです。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
冷えが体に及ぼす影響
冷えは単なる「不快感」だけでなく、体のさまざまな不調を引き起こす要因になると言われています。
血流が悪くなることで、筋肉や臓器に酸素や栄養が届きにくくなり、肩こり・腰痛・倦怠感などが現れやすくなります。
また、自律神経のバランスが乱れると、ホルモンの働きにも影響し、月経不順や肌荒れ、免疫力の低下などが見られることもあります。
さらに、冷えが続くと基礎代謝が下がり、脂肪が燃えにくくなるため、体重が増えやすくなる傾向もあります。
「体が冷えると太りやすい」と言われるのは、この代謝低下が関係しているのです。
引用元:”クラシエ製薬 健康コラム” (https://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/magazine/14.html)
自分の冷え性タイプを知ることが改善の第一歩
冷え性を改善するためには、まず自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることが大切です。
同じ「冷え性」でも、原因が血流、ホルモン、自律神経など人によって異なるため、対策方法も変わってきます。
たとえば、運動不足が原因なら筋力アップを意識した運動を、ストレス型ならリラックス習慣を取り入れるなど、生活に合わせた工夫が求められます。
自分の体の変化を丁寧に観察し、タイプに応じたケアを行うことで、冷えにくい体質へと少しずつ近づくことができると言われています。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
#冷え性改善
#冷え性の種類
#血行不良
#基礎代謝
#自律神経バランス
冷え性の主な原因とリスク要因

血行不良と筋肉量の低下
冷え性の根本的な原因として最も多いのが、血行不良だと言われています。
血液は体のすみずみまで酸素や栄養を運び、同時に熱も届けています。
ところが、長時間のデスクワークや運動不足が続くと、ふくらはぎや太ももの筋肉が衰え、血液を押し戻す力(筋ポンプ作用)が弱まってしまいます。
その結果、末端部分まで血流が届かず、手足が冷えやすくなるのです。
特に、女性は男性よりも筋肉量が少ないため、体の熱をつくり出す力が低く、冷えやすい傾向があると言われています。
また、姿勢の悪さや猫背も血流の滞りを招くため、正しい姿勢を保つことが予防につながります。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
自律神経の乱れ
血流のコントロールを担っているのが、自律神経です。
このバランスが乱れると、体温調節がうまくいかなくなり、手足の末端まで血液が流れにくくなります。
自律神経はストレスや睡眠不足、不規則な生活リズムの影響を受けやすく、特に現代人に多い冷えの原因の一つとされています。
たとえば、仕事のプレッシャーや人間関係のストレスで交感神経が優位な状態が続くと、血管が収縮して血流が悪化します。
反対に、リラックス時に働く副交感神経がうまく機能しないと、夜になっても体が温まりにくく、寝つきの悪さにもつながることがあります。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
ホルモンバランスの変化
特に女性では、月経周期や妊娠、更年期によるホルモンバランスの変化が冷え性に影響すると言われています。
女性ホルモンの分泌が減ると、血管の拡張や代謝のコントロールがうまくいかなくなり、体温が下がりやすくなります。
また、体の水分や塩分のバランスが崩れることでも血流が滞りやすくなるため、冷えを感じやすくなるのです。
ホルモンバランスの乱れは、自律神経とも密接に関係しています。
そのため、無理なダイエットや睡眠不足、過度なストレスは、冷えを悪化させる要因になることがあります。
引用元:”日本産科婦人科学会” (https://www.jsog.or.jp/)
食生活の乱れと栄養不足
偏った食生活も冷えを引き起こす大きな要因のひとつです。
甘い物や冷たい飲み物を摂りすぎると、体を内側から冷やしてしまうことがあります。
また、朝食を抜くとエネルギーが十分に供給されず、代謝が低下して体温が上がりにくくなることもあります。
一方で、たんぱく質・鉄分・ビタミンB群などは血液や熱の生成に欠かせない栄養素です。
これらが不足すると、体が冷えやすくなると言われています。
温かいスープや根菜類を取り入れ、バランスの良い食事を心がけることが冷え性改善の第一歩です。
引用元:”日本栄養士会” (https://www.dietitian.or.jp/)
冷えを招く服装・生活環境
薄着やタイトな衣類も冷えの一因となります。
体を締め付ける服装は血流を妨げるため、特に腰まわりや足首を冷やさない工夫が大切です。
冷房の効いたオフィスや冬場の外出時など、気温差の激しい環境では体温調節が追いつかず、冷えを感じやすくなります。
また、冷えた床に素足でいる、冷たい飲み物を頻繁に摂るなど、日常の小さな習慣も積み重なることで慢性的な冷えにつながると言われています。
季節を問わず「下半身を冷やさない」意識を持つことが、日常的な予防につながります。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
#冷え性改善
#血行不良
#自律神経の乱れ
#ホルモンバランス
#生活習慣
まずできるセルフチェック:あなたの冷え性タイプは?

自分の体を知ることが冷え性改善の第一歩
冷え性を改善するには、まず「自分がどんなタイプの冷えなのか」を知ることが大切だと言われています。
同じ“冷え”でも、原因や感じ方は人それぞれ。
手足だけが冷える人もいれば、体の芯が冷えている人、顔は火照るのに下半身だけ冷たいという人もいます。
この違いを見極めることで、対策の方向性がはっきりします。
「冷えをどうにかしたい」と思っても、闇雲に温めたりサプリを摂るだけでは、かえってバランスを崩すこともあるため注意が必要です。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
四肢末端型:手足が冷たいタイプ
最も一般的なのが、手足の先が冷える「四肢末端型」です。
寒い時期はもちろん、夏でも冷房の影響で指先が冷たくなる人もいます。
血管が収縮して末端まで血液が届きにくくなっているのが特徴で、運動不足や貧血、低血圧の人に多いとされています。
対策としては、足首や手首を温めること、軽い運動で血流を促すことが効果的とされています。
また、カフェインの摂りすぎや極端な食事制限も血流を悪化させるため注意が必要です。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
下半身型:腰や太ももが冷えるタイプ
「上半身は温かいのに足だけ冷たい」「冬になると脚のだるさが取れない」という人は、下半身型の冷えに当てはまる可能性があります。
骨盤の歪みや筋肉のコリによって下半身の血流が滞り、熱が行き届きにくくなっている状態です。
デスクワークで座りっぱなしの人や、運動不足の人に多い傾向があると言われています。
対策としては、骨盤まわりのストレッチや、下半身を意識したウォーキングが効果的です。
また、冷えを防ぐためにレッグウォーマーや湯たんぽを使うのもおすすめです。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
内臓型:体の内側が冷えるタイプ
手足はそれほど冷たくないのに、お腹のあたりが冷える人は「内臓型冷え性」と呼ばれるタイプに分類されます。
ストレスや自律神経の乱れ、食生活の乱れが影響し、内臓の血流が低下していると考えられています。
このタイプは、胃腸の不調や便秘、倦怠感を伴うことが多く、外から温めても改善しづらい傾向があります。
対策としては、食事で温かいものを摂る、冷たい飲み物を避ける、腹巻きや湯たんぽで内側から温めることが効果的だと言われています。
引用元:”クラシエ製薬 健康コラム” (https://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/magazine/14.html)
全身型:慢性的に体が冷えるタイプ
全身の代謝が低下し、体全体の温度が低い人は「全身型冷え性」に該当します。
甲状腺ホルモンの分泌低下や、極端なダイエット、睡眠不足などが関係しているとされています。
体温が常に低いと免疫力も落ちやすく、風邪をひきやすくなる傾向も見られます。
対策としては、まず生活リズムを整え、適度な運動と十分な睡眠を確保することが大切です。
また、たんぱく質をしっかり摂ることで筋肉量が増え、熱をつくる力が高まりやすいと言われています。
引用元:”日本甲状腺学会” (https://www.japanthyroid.jp/)
タイプ別チェックリスト
自分の冷え性タイプを見極めるために、次のような質問をしてみましょう。
・手足の先が冷たくなることが多い
・下半身が重く、だるい感じがする
・お腹が冷えると体調を崩しやすい
・体温が常に低く、肩こりや疲れを感じやすい
3つ以上当てはまる項目があれば、そのタイプの可能性が高いと言われています。
まずは自分の傾向を知り、そこから生活を見直していくことが冷え性改善の第一歩になります。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
#冷え性改善
#冷え性タイプ
#四肢末端型
#内臓型冷え
#全身型冷え
冷え性改善のための生活習慣と対策

体を温める食事を意識する
冷え性の改善には、日々の食生活を見直すことが欠かせません。
人間の体は、食べた物をエネルギーに変えて熱を生み出しています。
そのため、栄養バランスの偏りや、冷たい飲食物の摂りすぎは体温の低下につながると言われています。
特に冷え性の人は、根菜類(にんじん、ごぼう、れんこんなど)や生姜、ねぎ類など、体を内側から温める食材を意識して取り入れると良いとされています。
一方、冷たいジュースやアイスコーヒー、白砂糖の多いスイーツなどは、血流を悪化させる原因となることがあります。
また、朝食を抜くとエネルギー供給が滞り、代謝が下がりやすくなるため、温かい味噌汁やスープを摂る習慣をつけるのもおすすめです。
引用元:”クラシエ製薬 健康コラム” (https://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/magazine/14.html)
筋肉を動かして「熱をつくる体」へ
冷え性の人は、筋肉量の少なさが原因で体温が上がりにくい傾向があります。
筋肉は体の中で熱を生み出す「ヒーター」のような役割を果たしているため、運動によって基礎代謝を上げることが重要です。
特に効果的なのが、下半身を中心に使う運動です。
ウォーキングやスクワット、ヨガなど、無理のない範囲で継続できるものを選びましょう。
ふくらはぎの筋肉は血流を心臓に戻すポンプの役割を持つため、ここを動かすだけでも全身の巡りが良くなると言われています。
日中に軽いストレッチを取り入れたり、通勤中に階段を使うなど、生活の中で自然に動かす工夫をしてみてください。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
入浴と温活で「芯から温める」
体の外側だけでなく、内側から温めることも冷え性改善には欠かせません。
シャワーだけで済ませず、できるだけ湯船に浸かることがすすめられています。
38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かると、体の芯まで温まり、血流がスムーズになりやすいと言われています。
また、湯船に生姜やエプソムソルトを入れると発汗が促され、より深いリラックス効果が得られます。
入浴後は靴下を履いたり、足首を温めることで熱を逃さないようにすることも大切です。
もし時間がない場合は、足湯を取り入れるだけでも下半身の血流改善に役立ちます。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
睡眠とストレス管理で自律神経を整える
自律神経は体温調節と密接に関係しています。
そのため、睡眠不足や精神的なストレスが続くと、冷えが悪化しやすくなると言われています。
夜更かしを避け、寝る前はスマホやパソコンの光を控えるなど、リラックスできる環境を整えましょう。
また、深呼吸や軽いストレッチ、ハーブティーなどを取り入れると、副交感神経が優位になり、血流が整いやすくなります。
ストレスをためこまない生活リズムを作ることが、冷え性改善に欠かせないポイントです。
引用元:”日本自律神経学会” (https://www.jsna.org/)
服装・日常の工夫で冷えを防ぐ
服装の選び方や日常のちょっとした工夫も大切です。
薄着を避け、重ね着で空気の層を作ることで保温性が高まります。
特に、首・手首・足首の「三つの首」を冷やさないよう意識すると、全身の血流が良くなりやすいと言われています。
また、冷たい床に直接足をつけないようスリッパを履く、デスク下にひざ掛けを使うなど、小さな対策も効果的です。
冬場だけでなく、夏の冷房対策としてもこうした工夫を取り入れると、一年を通して冷えにくい体を保ちやすくなります。
引用元:”メディエイドオンライン” (https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1386/)
#冷え性改善
#温活習慣
#筋トレと代謝
#食生活の見直し
#自律神経ケア
タイプ別のアプローチと専門的ケアを検討する目安

自分に合った「冷え性改善法」を見つける
冷え性は、人によって原因も症状も異なるため、「これをすれば必ず改善する」という方法は存在しないと言われています。
大切なのは、自分の体質やライフスタイルに合った方法を見つけ、継続することです。
たとえば、四肢末端型の人は「血流を促す運動」や「温める衣類」、内臓型の人は「食生活の見直し」や「ストレスケア」を重視するなど、タイプ別に対策の重点を変えるのが効果的とされています。
また、季節や環境によって冷えの出方が変わることもあります。
冬だけでなく、夏の冷房や寝冷えなどにも注意しながら、自分の体の反応をこまめに観察していくことが大切です。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
四肢末端型には「循環を整える」アプローチ
手足の冷えが強いタイプは、血流をスムーズにする工夫がポイントです。
軽い有酸素運動やストレッチを習慣化することで、ふくらはぎや太ももの筋肉が活発になり、血液を全身に巡らせやすくなります。
また、マッサージや温熱パッドなどで局所的に温めるのも良い方法です。
一方で、カフェインの摂取やタイトな服装は血管を収縮させるため、冷えを悪化させることがあります。
特に仕事中は、手首や足首を冷やさないよう注意しましょう。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
内臓型には「体の内側から温める」ケア
お腹の冷えを感じやすい内臓型は、食事と生活リズムの見直しが鍵になります。
冷たい飲み物や甘いスイーツを控え、温かいスープや煮込み料理を積極的に摂るようにしましょう。
また、腹巻きやカイロを使ってお腹まわりを温めることで、内臓の働きがサポートされると言われています。
さらに、ストレスによって自律神経が乱れると、内臓の血流が低下しやすくなるため、リラックス時間を確保することも大切です。
湯船に浸かる、深呼吸をする、好きな香りのアロマを取り入れるなど、心と体の両面から温める工夫を取り入れてみてください。
引用元:”クラシエ製薬 健康コラム” (https://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/magazine/14.html)
下半身型には「骨盤ケア」と「筋トレ」
下半身の冷えに悩む人は、骨盤の歪みや姿勢の悪さが影響していることが多いとされています。
長時間座りっぱなしでいると、骨盤周囲の筋肉がこわばり、血流が滞る原因になります。
立ち上がってストレッチをしたり、太ももやお尻の筋肉を動かすことで、下半身全体の巡りが改善しやすくなります。
特におすすめなのが「骨盤まわりを意識したヨガ」や「スクワット」です。
無理のない範囲で継続すると、筋肉が熱を生み出しやすくなり、冷えにくい体へ変わっていくとされています。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%9F%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%A7%E5%AF%BE)
改善が見られない場合は専門家へ相談を
生活改善を続けても冷えが強く残る場合、内科的・ホルモン的な要因が関係している可能性があります。
甲状腺機能低下症、貧血、自律神経失調症などが隠れていることもあるため、早めに専門家へ相談することがすすめられています。
整骨院や鍼灸院では、血流改善を目的とした施術や姿勢調整なども行われており、体のバランスを整えるサポートを受けることもできます。
冷えを「体質だから」と放置せず、専門的なケアを取り入れることで、根本的な改善が期待できると言われています。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/4852/)
継続が冷え性改善のカギ
冷え性改善において最も重要なのは、「継続すること」です。
食事・運動・睡眠・ストレスケアのどれも、短期間で効果を実感できるものではありません。
小さな工夫を日々の習慣に落とし込み、体の変化を感じながら少しずつ続けていくことが、冷えにくい体を作る一番の近道だと言われています。
自分に合った方法を見つけ、焦らず、丁寧に体と向き合うことが、健康的な温活の第一歩です。
引用元:”メディエイドオンライン” (https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1386/)
#冷え性改善
#タイプ別対策
#温活習慣
#血流改善
#専門的ケア