足のだるさを感じる人の特徴と原因

こんな人が足のだるさを感じやすい
「最近、夕方になると足が重い」「長時間立っているとだるくなる」――そう感じる人は意外と多いものです。
特に、立ち仕事やデスクワークが多い人は、足の血流が滞りやすく、だるさを感じやすいと言われています。動かずに同じ姿勢を続けることで、ふくらはぎの筋肉(いわゆる“第二の心臓”)がうまく働かず、血液やリンパ液が下半身にたまりやすくなるためです。
また、冷え性の人やむくみやすい体質の人も、足のだるさを感じやすい傾向があります。冷えによって血管が収縮し、循環が悪くなることで、筋肉が硬くなりやすいと言われています。
さらに、運動不足や水分・塩分のバランスの乱れ、靴のサイズやヒールの高さが合っていないといった日常的な要因も関係しているケースが多いようです。
「夕方になると靴がきつくなる」「足首やふくらはぎを押すと跡が残る」という人は、血流やリンパの流れが滞っているサインのひとつと考えられています。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
足のだるさの主な原因とは?
足のだるさの原因は、一言でいうと「循環の滞り」です。
心臓から送り出された血液は足先まで届きますが、重力の影響で心臓へ戻りにくく、ふくらはぎの筋肉がポンプのような役割を果たして押し戻しています。
しかし、この筋肉の働きが弱くなると、血液やリンパがうまく戻らず、足に老廃物がたまりやすくなると言われています。
また、長時間の立ちっぱなしや座りっぱなしが続くと、血液が足に滞り、だるさやむくみを感じやすくなります。
デスクワーク中に足を組むクセがある人や、立ち仕事で体重を片足にかけるクセがある人も要注意です。こうした姿勢の偏りが、筋肉や血管に余計な負担をかけていることがあります。
加えて、加齢やホルモンバランスの変化によっても血流が低下しやすくなるとされています。女性の場合は、月経周期や更年期の影響で足のだるさを感じやすくなることがあるそうです。
引用元:”日本整形外科学会” (https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/foot_pain.html)
放置すると起こりやすいトラブル
軽い足のだるさは一時的なこともありますが、慢性的に続く場合は注意が必要だと言われています。
血行不良が進行すると、筋肉の疲労が抜けにくくなり、むくみや冷えが悪化することがあります。さらに、静脈の弁がうまく機能しなくなると、「下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)」などの疾患につながるケースもあるそうです。
ただし、早めに原因を見つけて対策を行えば、改善が期待できるケースが多いとされています。
「たかがだるさ」と放置せず、自分の生活習慣や姿勢を見直すことが、足の軽さを取り戻す第一歩です。
引用元:”日本血管外科学会” (https://www.jsvs.org/public/varix.html)
#足のだるさを取る方法
#血行不良
#デスクワークむくみ
#冷え性対策
#第二の心臓
即効性が期待できるセルフケア法(ストレッチ・マッサージなど)

まずは「動かすこと」で血流を促す
足のだるさを感じたときに最も手軽で効果的なのが、軽いストレッチや足首の運動だと言われています。
デスクワーク中や立ち仕事の合間に、つま先を上下に動かしたり、足首をゆっくり回すだけでも血流が促され、だるさを和らげる助けになります。
「仕事中でもできる簡単な動き」としては、かかとの上げ下げ運動(カーフレイズ)もおすすめです。5〜10回ほど繰り返すと、ふくらはぎの筋肉ポンプが働きやすくなります。
また、ストレッチを行う時間帯も重要です。朝は足首を軽く動かして巡りを整え、夜はふくらはぎを伸ばして一日の疲労をリセットするように意識すると良いとされています。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
足のだるさに効く簡単マッサージ
足のだるさを取るには、足裏からふくらはぎに向かってやさしくマッサージするのが基本です。
足首を片手で支えながら、もう一方の手で円を描くように下から上へさすります。こうすることで、静脈やリンパの流れを助け、老廃物の排出を促す効果が期待できると言われています。
マッサージの際は、オイルやクリームを使うと摩擦を防げるため、皮膚への負担が少なくなります。
また、ふくらはぎの中央を軽く押すように刺激すると、筋肉がゆるみやすくなる傾向があります。
お風呂上がりなど体が温まっているときに行うと、よりリラックスしやすいでしょう。
引用元:”日本整形外科学会” (https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/foot_pain.html)
ツボ押しでだるさを軽減
足のだるさに効果的とされるツボには、「湧泉(ゆうせん)」と「三陰交(さんいんこう)」があります。
「湧泉」は足裏の土踏まずの少し上、中央よりやや指寄りにあり、疲労回復を促すツボと言われています。
「三陰交」は内くるぶしの上、指4本分ほどの位置にあり、冷えやむくみに関係するツボとして知られています。
ツボ押しのコツは、強く押しすぎないこと。
ゆっくり深呼吸しながら、3秒押して3秒離すリズムで数回繰り返すと、緊張がほぐれやすくなるとされています。
夜のリラックスタイムに取り入れると、入眠のサポートにもつながることがあります。
引用元:”Rehasakuマガジン” (https://rehasaku.net/magazine/ankle/weaknessinlegs-improvement/)
お風呂と温冷交代浴で巡りを整える
お風呂でのケアも、足のだるさを取るための重要な方法とされています。
ぬるめ(38〜40℃程度)の湯に10〜15分浸かると、血管が広がり、血流がスムーズになりやすいと言われています。
また、温かいお湯と冷水を交互にかける「温冷交代浴」は、自律神経を整え、むくみ軽減にも役立つとされています。
冷え性の人は、湯船の中で足首を回したり、つま先を動かすだけでも十分です。
体の芯から温めることを意識すると、足の重だるさが和らぐ傾向が見られます。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E4%B8%80%E5%88%BB%E3%82%82%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0)
自宅でできる簡単リセット法
1日の終わりに、足を心臓より高い位置に上げて5〜10分キープするのも効果的と言われています。
クッションや壁を使って足を上げるだけで、重力の助けを借りて血液やリンパが戻りやすくなります。
この「足挙上法」は、足のむくみやだるさを感じたときにすぐ試せる簡単ケアとして人気です。
テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも続けられるので、毎日の習慣にしやすい点も魅力です。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
#足のだるさを取る方法
#ストレッチ
#足マッサージ
#ツボ押し
#足挙上法
血流改善・むくみケアの方法

血流を整えることでだるさを軽減
足のだるさは、血流が滞ることで起こることが多いとされています。
心臓から送り出された血液が足先まで届いたあと、重力に逆らって戻るときに、ふくらはぎの筋肉が「ポンプ」のような役割を果たしています。
しかし、この働きが弱まると、血液やリンパ液がうまく循環せず、疲労物質や水分がたまりやすくなります。
そのため、血流を促すケアを取り入れることが重要です。
日常的に歩く習慣をつける、つま先立ち運動を行う、エスカレーターではなく階段を使うなど、無理のない範囲で下半身を動かすことが推奨されています。
軽い有酸素運動(ウォーキングやストレッチ)を続けることで、筋肉の柔軟性が保たれ、血行が整いやすくなると言われています。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E4%B8%80%E5%88%BB%E3%82%82%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0)
着圧ソックス・弾性ストッキングの活用
日常でできる血流改善の工夫として、着圧ソックスや弾性ストッキングの使用も効果的だと言われています。
一定の圧力で足首からふくらはぎにかけて締めることで、血液の滞りを防ぎ、むくみを軽減する手助けをしてくれます。
特に、長時間の立ち仕事やデスクワークをする人、飛行機や車での移動が多い人には有効とされています。
ただし、締め付けが強すぎるものや、寝るときに使用するタイプを誤って使うと逆効果になることもあるため、自分に合った製品を選ぶことが大切です。
医療用タイプを使用する場合は、販売店や専門家のアドバイスを受けると安心です。
引用元:”日本静脈学会” (https://www.js-phlebology.jp/public/)
足を高くして休む「足挙上法」
血液をスムーズに心臓へ戻すためには、足を心臓より高い位置に上げるのも有効とされています。
夜寝る前や入浴後に、クッションやソファの肘置きを使って足を少し高くするだけでもOKです。
この姿勢を5〜10分ほど続けることで、リンパの流れが促され、脚のむくみやだるさが軽くなることがあると言われています。
また、デスクワーク中でも、足元に小さな台やクッションを置いて、軽く傾斜をつけると血流が改善しやすくなる場合があります。
「少し足を上げる」だけでも日々の疲労感が違ってくるので、習慣に取り入れやすい方法です。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
水分補給と塩分バランスを整える
足のむくみやだるさを和らげるには、水分と塩分のバランスも意識する必要があります。
「むくむから水分を控える」という人もいますが、実際には脱水によって血液がドロドロになり、かえって循環が悪くなることがあるとされています。
水分は1日あたり1.5〜2リットルを目安に、こまめに摂ることが理想的です。
また、塩分の摂りすぎは体に水分をため込みやすくするため、味の濃い食事を控え、カリウムを含む野菜や果物(バナナ、ほうれん草など)を取り入れると良いと言われています。
引用元:”日本栄養士会” (https://www.dietitian.or.jp/)
定期的に足を温める習慣を
冷えが続くと血流が悪化し、だるさが慢性化しやすくなります。
そのため、足湯や温湿布などで定期的に足を温めるのも有効だと言われています。
特に冬場や冷房の強い職場では、足首を冷やさない工夫が必要です。
温める際は、38〜40℃程度のぬるま湯に10分ほど足を浸すのが目安。
血行が促されると、むくみだけでなく、足先の冷えや筋肉のこわばりも和らぎやすくなります。
就寝前の足湯は、リラックス効果があり、睡眠の質を高めることにもつながるとされています。
引用元:”Rehasakuマガジン” (https://rehasaku.net/magazine/ankle/weaknessinlegs-improvement/)
#足のだるさを取る方法
#血流改善
#むくみケア
#着圧ソックス
#足を高くする習慣
日常生活で気をつけたいポイント

姿勢と歩き方のクセを見直す
足のだるさは、単に「疲労」だけでなく、姿勢の乱れや歩き方のクセが関係していることが多いと言われています。
たとえば、猫背や骨盤の傾きによって重心が偏ると、片側の脚ばかりに負担がかかりやすくなります。
また、足裏のアーチ構造(縦・横アーチ)が崩れていると、着地時の衝撃をうまく吸収できず、ふくらはぎや太ももが常に緊張した状態になります。
こうした姿勢や歩行バランスの乱れを整えるには、正しい立ち方を意識するのが第一歩です。
かかと・足の小指・親指の付け根の3点で体を支える「トライポッド姿勢」を心がけると、自然とバランスが取りやすくなるとされています。
また、ウォーキングの際は“かかとからつま先”へ体重を移動させることを意識すると、下半身全体の筋肉が効率よく使えるようになります。
引用元:”ホットペッパービューティー整体特集” (https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000527453/blog/bidA098331481.html)
靴選びとインソールの見直し
「なんとなく履きやすい靴」でも、長時間歩いたり立ち続けたりすると、合わない靴が足のだるさを引き起こすことがあります。
特に、ヒールが高い靴や、底が硬い靴を日常的に履いていると、足首やふくらはぎの筋肉が常に緊張して血流が悪くなりやすいと言われています。
おすすめは、かかとがしっかり固定され、つま先が少し反り上がった靴です。
靴底が柔らかすぎるものより、程よい反発力のあるタイプを選ぶと、歩行時の衝撃を吸収しやすくなります。
また、既製品の靴が合わない人は、足の形に合わせたカスタムインソールを使用すると、重心が安定し、だるさの軽減につながることがあります。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
デスクワーク中の工夫
長時間座ったままの姿勢は、血流が下半身で滞り、足のむくみやだるさを悪化させることがあります。
そのため、デスクワーク中は1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすことが推奨されています。
椅子に座ったままでも、かかとの上げ下げ運動や足首回しを行うだけで、ふくらはぎの筋肉が刺激され、血流が促されます。
また、足元に小さな踏み台を置いて角度をつけることで、血液が心臓へ戻りやすくなると言われています。
最近では、オフィス用の「フットレスト」や「着圧ソックス」なども市販されているため、取り入れやすい環境を整えるのも効果的です。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E4%B8%80%E5%88%BB%E3%82%82%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0)
食生活と生活リズムの調整
足のだるさを防ぐには、外側のケアだけでなく内側からのサポートも欠かせません。
バランスの良い食事を心がけ、鉄分・ビタミンE・カリウムを含む食材を積極的に摂ることで、血流と代謝のバランスを整えやすくなると言われています。
また、睡眠不足やストレスも自律神経の乱れを引き起こし、血管の収縮を強めてしまうことがあるため、十分な休息も大切です。
特に、塩分の摂りすぎは体に水分をため込みやすくし、むくみやだるさを悪化させることがあります。
加工食品や外食が多い人は、意識的に野菜や果物を増やして調整するとよいでしょう。
引用元:”日本栄養士会” (https://www.dietitian.or.jp/)
日々の「小さな積み重ね」が大切
足のだるさを根本的に改善するには、「気づいたときに動かす」「足を温める」「姿勢を整える」といった小さな習慣の積み重ねが大切だと言われています。
どれも特別なことではありませんが、日常の中で少しずつ続けることで、循環が整い、疲れにくい体づくりにつながります。
無理をして一度に変える必要はありません。
1日5分でも、足のストレッチや温浴を続けることが、将来的なだるさの予防につながるとされています。
引用元:”Rehasakuマガジン” (https://rehasaku.net/magazine/ankle/weaknessinlegs-improvement/)
#足のだるさを取る方法
#姿勢改善
#靴選び
#デスクワークケア
#生活習慣改善
こんなときは要注意・専門機関を検討すべきサイン

「いつもと違う」だるさを感じたら注意
多くの足のだるさは一時的な疲労や血行不良によるものですが、いつもと違う感覚や片足だけ強いだるさがある場合は注意が必要と言われています。
たとえば、片側の足だけが急にむくむ、皮膚の色が変わる、触ると熱を持っているように感じるといった場合は、単なる疲労ではなく血管や神経のトラブルが関係していることがあります。
特に、下肢静脈瘤や”深部静脈血栓症(DVT)”などは、足の重さやだるさが初期症状として現れることがあるため、早めの検査がすすめられています。
「冷やしたら少し楽になる」「マッサージをしても改善しない」など、普段のケアで変化が見られない場合も、専門家に相談するタイミングと考えられています。
引用元:”日本静脈学会” (https://www.js-phlebology.jp/public/)
だるさ以外のサインを見逃さない
足のだるさと一緒に、しびれ・痛み・皮膚の変色・冷えなどの症状がある場合は、神経や循環系の異常が隠れている可能性があります。
例えば、糖尿病や末梢動脈疾患(PAD)などでは、血流の低下によって足が冷えたり、傷が治りにくくなることがあると言われています。
また、筋肉や関節の異常が原因で、慢性的な疲労や重だるさを感じるケースもあるようです。
自分で判断しづらいときは、整形外科や血管外科、または整体院での触診・画像検査を受けてみると良いでしょう。
特に長期間続く場合や、夜間にズキズキと痛むような場合は、早期の来院が安心です。
引用元:”日本整形外科学会” (https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/foot_pain.html)
専門的な検査でわかること
専門機関では、まず問診と触診を通して、痛みやだるさの部位・持続時間・生活習慣などを確認します。
必要に応じて、血流検査(エコー)やレントゲン、MRIなどで筋肉・血管・神経の状態を確認することもあります。
こうした検査を行うことで、単なる疲労性のだるさなのか、血流や神経系の異常によるものなのかを見分けることができるとされています。
また、原因が特定できれば、ストレッチ・温熱療法・インソール調整・物理療法など、症状に合わせた施術プランを立てることが可能になります。
引用元:”くまのみ整骨院” (https://kumanomi-seikotu.com/blog/6896/)
早期対策が改善への近道
「少し気になるけど忙しくて放置してしまう」という人も多いですが、足のだるさは早めにケアを始めるほど改善しやすいと言われています。
特に、生活習慣や姿勢の見直しとあわせて、専門的なアドバイスを受けることで再発防止にもつながります。
放置すると慢性化し、筋肉の硬直や冷えが強くなるケースもあるため、自己ケアだけで変化が見られない場合は、早めの相談が安心です。
「少し気になる」「同じ箇所が繰り返し重い」などの段階で、早めに行動することが将来的な不調予防にもつながるとされています。
引用元:”IMC総合医療センター” (https://imc.or.jp/archives/mamechishiki/%E4%B8%80%E5%88%BB%E3%82%82%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0)
専門家に相談する際のポイント
来院時は、痛みやだるさが出るタイミング・時間帯・生活環境などをメモしておくと、原因の特定がスムーズになります。
また、靴の写真や、足のむくみが出たときの様子をスマホで撮影して見せるのも有効です。
医療機関や整体院では、生活習慣の改善アドバイスや、セルフケアの方法を具体的に教えてもらえることもあります。
大切なのは、「我慢せず、自分の体の変化に気づいたら早めに相談する」こと。
これが、足のだるさを長引かせない最もシンプルで確実な対策だと言われています。
#足のだるさを取る方法
#下肢静脈瘤
#深部静脈血栓症
#血流検査
#早期相談
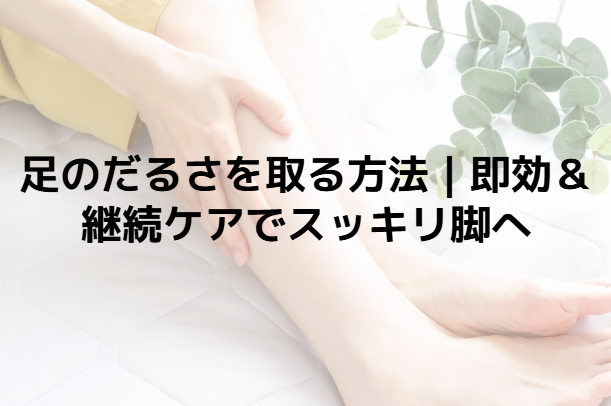
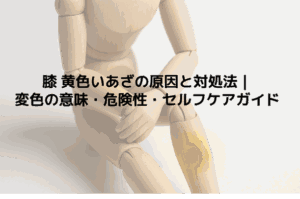
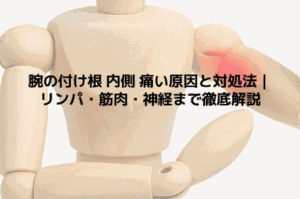
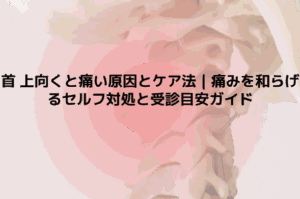
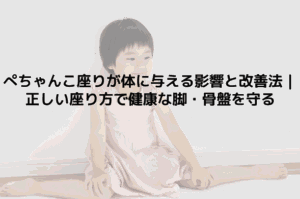
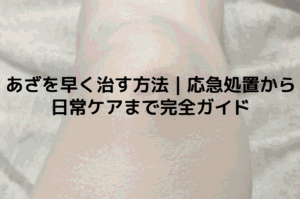
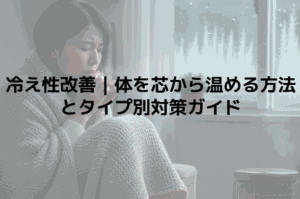

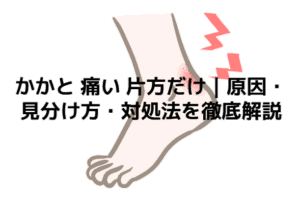
コメント