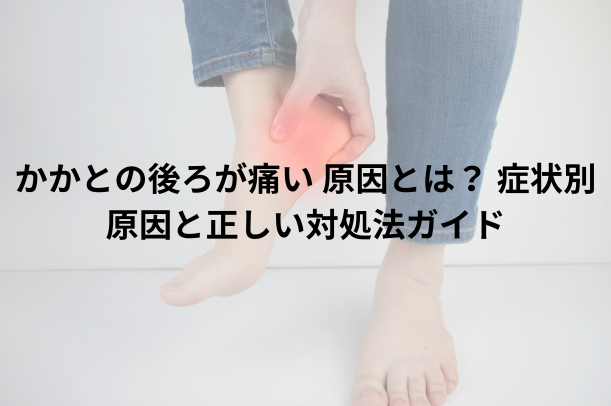痛い場所・タイミングで読む!かかとの後ろの痛みの見分け方

痛む部位(アキレス腱付着部、かかと上縁、踵骨後端など)
「かかとの後ろが痛い」と感じても、実は“どのあたり”かで原因が変わることが多いんです。例えば、アキレス腱がかかとの骨にくっつく部分(付着部)に痛みを感じる方が多く、これが アキレス腱付着部症 の典型例と言われています。MSDマニュアル+2日本足の外科学会+2
また、やや上縁(踵骨の後部上縁)にズキッとくる場合もあり、靴の後ろが当たって摩擦が起こることが原因になったり、骨の突出(ハグルンド変形など)による影響だったりすることがあります。さらに、踵骨の後端そのもの(骨の端っこ)に痛みを感じるケースでは、疲労骨折のような骨の微損傷も念頭に置くべきパターンです。
だから、「ただ“後ろ”じゃなくて、ちょっと押してみて“どこが一番響くか”を感じてみて」は、最初の手がかりになります。
痛みが出るタイミング(歩き始め、運動中、立ち仕事後など)
次に、いつ痛むかも大きなヒントになりますよね。例えば、歩き始め にズキッとくる場合って、アキレス腱周囲炎の“こわばり”が残っているケースが少なくなく、動き始めで痛みを感じる人は多いです。豊洲整形外科リハビリクリニック+2済生会+2
逆に、運動中・運動後 に痛みがだんだん強くなるタイプもあります。これはアキレス腱に繰り返し負荷がかかって炎症が拡がっている可能性があるパターンです。ほんだ整骨院+1
あるいは、夕方や一日の終わり、立ち仕事をした後に痛みがドンとくる人もいます。これは使いすぎや筋肉疲労、足へのストレス蓄積が要因となる流れです。
このように、痛むタイミングを意識すると、たとえば「朝だけ痛い → こわばり系」「後半に痛みが増す → 負荷累積型」など、仮説を立てやすくなります。
症状パターン別チェックリスト・図解
では、ここで簡単なチェックリスト形式で「あなたの痛みパターン」がどのタイプに近いか整理してみましょう:
| チェック項目 | YESが多ければ 想定されるタイプ |
|---|---|
| 朝一歩目に痛む | アキレス腱付着部炎・周囲炎 |
| 歩き始めだけ鋭く響く | こわばり・炎症初期 |
| 運動を続けているうちに痛みが増す | 負荷蓄積型(腱過使用) |
| 一日の終わりに痛みがひどくなる | 疲労/使いすぎ型 |
| 靴のかかと部が当たると痛む | 摩擦・革靴後端刺激型 |
| かかとを押すとピンポイントで痛い | 付着部や骨端部の局所性 |
#かかと痛み #アキレス腱付着部炎 #痛むタイミング #チェックリスト #後ろ痛み辨別
かかとの後ろが痛い 原因となる主な疾患・病態

アキレス腱付着部炎(腱・骨の付着部での炎症)
かかとの後ろで最も多いとされるのが、アキレス腱がかかとの骨にくっつく部分で炎症が起きる「アキレス腱付着部炎」です。歩き始めや階段の上り下りで痛みやすく、腫れや熱感を伴うこともあると言われています(引用元:rehasaku.net)。
アキレス腱炎/アキレス腱周囲炎
アキレス腱そのもの、あるいはその周囲組織に炎症が広がるのがこのタイプです。ランニングやジャンプ動作で悪化しやすく、朝のこわばりが特徴とされています(引用元:yasu-clinic.com)。繰り返しの負荷で腱が硬くなると、改善に時間がかかることもあるそうです。
踵骨疲労骨折
「骨にヒビが入るほど強い運動はしていないのに…」という方でも、長期間の立ち仕事やランニングで踵骨に微細な損傷が積み重なり、疲労骨折につながるケースがあるとされています。押すとピンポイントで痛む、歩行でズキンと響くといった症状が目安になることがあります(引用元:msdmanuals.com)。
ハグルンド病(踵骨隆起)や骨変形
かかと後方に骨の出っ張りができ、靴に当たって痛みを引き起こすのが「ハグルンド病」と呼ばれる状態です。硬い革靴や運動靴で擦れやすく、赤みや腫れを伴うこともあると言われています。骨の形そのものが影響しているので、靴選びやインソールの工夫が対策につながることが多いとされています。
その他の疾患(シーバー病、神経圧迫、関節炎など)
成長期の子どもに見られる「シーバー病」は、踵骨の成長軟骨に負担がかかって痛みが出るものです。また、大人では足根管症候群など神経圧迫による痛み、あるいは痛風や関節リウマチなどの炎症性疾患がかかとの後ろに症状を出す場合もあります(引用元:ubie.app)。
#かかと後ろの痛み #アキレス腱付着部炎 #踵骨疲労骨折 #ハグルンド病 #シーバー病
リスク因子・誘因と発症に至るメカニズム

過負荷・オーバーユース(ランニング、ジャンプ、立ち仕事)
かかとの後ろの痛みは、日常の繰り返し動作が積み重なって起こることが多いとされています。ランニングやジャンプを続けることでアキレス腱や骨に微細なストレスがかかり、炎症につながるケースがあります。立ち仕事で長時間荷重をかけ続けることも同じような負担要因になると言われています(引用元:rehasaku.net)。
不適切な靴・ソールの影響
「最近、靴を変えてから痛みを感じるようになった」という声もよく聞かれます。硬すぎるかかとカウンターや薄いソールは、摩擦や衝撃を直接かかとに伝えてしまうため、炎症を引き起こす誘因となることがあります(引用元:yasu-clinic.com)。逆にクッション性のある靴やインソールを活用することで、痛みの軽減につながるケースもあると言われています。
ふくらはぎ・アキレス腱・筋肉の柔軟性低下
加齢や運動不足でふくらはぎの柔軟性が落ちると、アキレス腱やかかとに過剰なテンションがかかります。その結果、腱や付着部に炎症が起きやすくなると考えられています。ストレッチや軽い運動で柔軟性を維持することが、負担を減らす方法として紹介されています(引用元:toyosu-seikeigeka.com)。
体重増加・肥満・加齢
体重が増えると、当然ながら足への負荷も大きくなります。特にかかとは体重を支える部分なので、肥満や急激な体重増加はリスク因子のひとつです。また、年齢を重ねるにつれて腱や骨の回復力が落ちることも重なり、痛みの発症につながりやすいとされています。
足のアーチ異常・歩行バランス・足部構造の影響
偏平足やハイアーチなど足の形の違いも、かかとの後ろに負担を与える要因になると言われています。足のアーチが崩れると衝撃が分散されず、アキレス腱や踵骨へのストレスが増すからです。さらに、歩き方や姿勢の癖があると、片側に負荷が集中し痛みにつながるケースもあります(引用元:ubie.app)。
#かかと痛みリスク #オーバーユース #靴の影響 #柔軟性低下 #足の構造
自宅でできる対処法・予防法:痛みを和らげ、再発を防ぐ

安静・荷重制限・使用軽減
まず大事なのは「使いすぎないこと」と言われています。強い痛みがあるときは無理に動かさず、立ち仕事を控えるなど、かかとへの負荷を減らす工夫が必要です。完全な安静というより、痛みを感じにくい範囲で動きを調整するほうが改善につながるケースもあるそうです(引用元:rehasaku.net)。
アイシング・温熱・物理療法
炎症が強い時期は、アイシングで熱を抑えることがすすめられています。一方で慢性的に痛む場合は、温めて血流を促すと回復を助けると言われています。入浴や足湯で温めたり、温湿布を使うのも一案です。こうした物理的なケアは、自宅でも取り入れやすいのがメリットです(引用元:yasu-clinic.com)。
ストレッチ・筋膜リリース・筋肉強化
ふくらはぎや足底筋膜が硬いとアキレス腱への負担が増えるので、ストレッチや筋膜リリースが役立つとされています。タオルを使ってふくらはぎを伸ばす運動や、テニスボールを足裏で転がす方法は簡単に行えるケアです。さらに、カーフレイズ(つま先立ち運動)で筋力をつけると再発予防につながると紹介されています(引用元:toyosu-seikeigeka.com)。
インソール・クッション性の高い靴選び・修正具の活用
靴の影響は想像以上に大きいです。クッション性の高い靴や、かかと部分を安定させるインソールを使うと衝撃を和らげやすいと言われています。特に硬い靴で摩擦を感じる場合は、ヒールカップや踵パッドなどの補助具を取り入れると痛み軽減につながるケースがあります。
歩行改善・フォーム矯正
「歩き方が悪いのかな?」と感じたことはありませんか。実際に、つま先の向きや重心のかけ方によってはアキレス腱に負担が集中することがあると言われています。鏡で姿勢を確認したり、専門家のアドバイスを受けることでフォーム改善が期待できます。
体重管理・全身アプローチ
体重が増えると足への負担はどうしても大きくなります。バランスの良い食事や適度な運動による体重管理は、かかとだけでなく全身の健康にもつながる要素です。また、股関節や体幹を強化することが、下肢の負担を減らすという報告もあります。
#かかとケア #アキレス腱ストレッチ #靴とインソール #アイシング温熱 #体重管理
いつ受診すべき?整形外科での診断と治療の流れ

受診目安:痛みが1~2週間改善しない、腫れ・熱感、歩行困難など
「少し休めば良くなるだろう」と放置してしまう方もいますが、かかとの後ろの痛みが1~2週間続いて改善しない場合は来院を考える目安とされています。特に、腫れや熱感がある、歩くのがつらい、朝起きて一歩目が強く痛むなどの症状があるときは注意が必要と言われています(引用元:rehasaku.net)。
受診先・診療科(整形外科、足専門外来など)
かかとの痛みは整形外科での相談が基本です。スポーツによる痛みであればスポーツ整形、慢性の症状がある場合は足専門外来やリハビリ科が選択肢になります。地域によっては足の専門クリニックがあり、歩行や靴選びまでアドバイスを受けられることもあるそうです(引用元:yasu-clinic.com)。
診断に用いられる検査(問診・視診・触診、X線・MRI・エコー・神経伝導検査など)
医療機関では、まず問診で「いつから痛いか」「どの動作で強まるか」を確認し、視診や触診で炎症の場所を調べます。さらに必要に応じてX線で骨の異常を確認したり、MRIで腱や周囲組織の状態を詳しく見たりすることもあります。エコー検査は腱の状態を観察しやすく、神経圧迫が疑われるときには神経伝導検査が使われる場合もあると言われています。
治療選択肢:保存療法(リハビリ、薬、注射、装具)/手術適応例
基本的には保存療法と呼ばれる方法が中心です。炎症を抑える薬や注射、装具による安定化、リハビリでのストレッチや筋力トレーニングなどが行われます。これらで改善が見込めない場合や、骨の変形・腱断裂など重度の異常がある場合に限り、手術が検討されるケースもあると言われています(引用元:ubie.app)。
治療後フォロー・再発予防
施術後も再発を防ぐために、靴やインソールの見直し、ストレッチの継続、生活習慣の改善が大切だとされています。医師や理学療法士のアドバイスを受けながら、自宅でできるケアを並行して続けることで、長期的に安定した状態を目指すことができると考えられています。
#かかと受診目安 #整形外科検査 #アキレス腱痛み #保存療法と手術 #再発予防