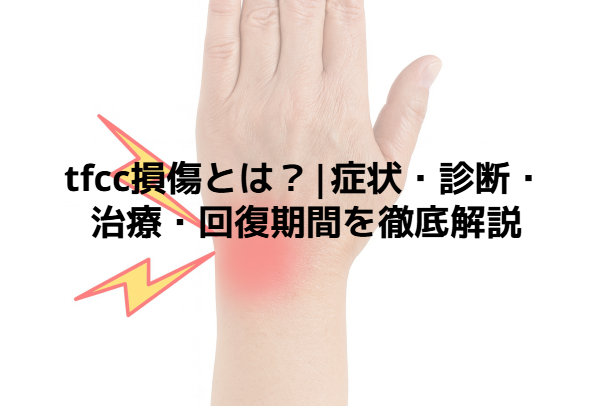tfcc損傷とは

「手首の小指側がズキッと痛む」「ドアノブを回すと違和感がある」――そんな経験はありませんか?
その痛み、もしかすると**TFCC損傷(ティーエフシーシー損傷)**と呼ばれる状態かもしれません。
TFCCとは「三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex)」の略で、手首の小指側に位置する軟骨や靭帯の集まりのことを指します。
この部分は、手首の骨同士をつなぎ、関節の安定を保ちながら衝撃を吸収するクッションのような役割をしていると言われています。
引用元:https://www.west-umeda-clinic.com/tfcc
転倒して手をついたり、スポーツで手首を強くひねったりすると、このTFCCが傷つくことがあります。
特に野球やテニス、ゴルフなど、手首を何度も使う競技では、少しずつ負担が重なって痛みが出るケースもあるようです。
また、加齢による軟骨のすり減りや、手首の骨の長さの違い(尺骨長変異)も関係しているといわれています。
引用元:https://nambahandcenter.com/tfcc
痛みの出方には個人差がありますが、「物を持つ」「手をつく」「ひねる」といった動作で小指側に強い痛みを感じるのが特徴です。
初期のうちは違和感だけでも、放置すると慢性的な痛みに進行することもあります。
そのため、早めに整形外科での検査を受け、原因を見極めることが改善への第一歩とされています。
引用元:https://sapporo-chuoseikei.com/column/tfcc-wrist-pain-treatment
TFCCの役割
TFCCは、手首の骨(橈骨と尺骨)の間に位置し、関節の安定を支える大切な構造といわれています。
簡単に言えば、骨同士を支えるクッション兼サスペンションのような存在です。
物を持つ・ひねる・押すといった日常のあらゆる動きで、手首への負担を分散させる働きをしています。
この部分が損傷すると、関節の動きがスムーズでなくなり、「回すと痛い」「小指側が重だるい」といった違和感が生じやすくなります。
イメージとしては、ドアの蝶番に油が切れてきしむような状態に近いです。
放っておくと動かすたびに摩擦が起き、炎症が続くこともあるため、早めの対処が大切といわれています。
#tfcc損傷 #手首の痛み #三角線維軟骨複合体 #スポーツ障害 #整形外科知識
tfcc損傷の症状と特徴

TFCC損傷では、手首の小指側に出る痛みがもっとも多くみられると言われています。
特に、「ドアノブを回す」「ペットボトルのふたを開ける」「床に手をつく」といった動作でズキッとした痛みを感じるケースが多いようです。
日常生活の中で手首をひねる場面は意外と多く、気づかないうちに症状が進行することも少なくありません。
また、痛みの強さや出方は人によって異なります。
「少し力を入れたときだけ痛む」人もいれば、「安静時でもズーンと重だるい感覚が残る」人もいます。
症状が軽い場合は違和感程度で済むこともありますが、放っておくと関節の不安定感やクリック音(コリッという音)が出ることもあるようです。
引用元:https://nambahandcenter.com/tfcc
初期症状と悪化のサイン
初期の段階では、「疲れたときだけ痛む」「手をひねるとピリッとする」など、軽い違和感で気づく方が多いです。
この時期に無理を続けると、炎症が広がり、腫れや熱感を伴うようになるケースもあるといわれています。
さらに進行すると、物を持つ動作そのものが難しくなり、日常生活に支障を感じることもあります。
悪化してくると、手首の小指側を押すと痛みが強く出たり、前腕の回内・回外(手のひらを上や下に向ける動作)で違和感が増す傾向があります。
また、手首の奥で「パキッ」や「コリッ」と音がする人もおり、これは関節内の組織が擦れることによる摩擦音とされています。
引用元:https://sapporo-chuoseikei.com/column/tfcc-wrist-pain-treatment
症状を感じたら、早めに整形外科で検査を受けることがすすめられています。
早期に原因を把握し、適切な対応をとることで慢性化を防ぎやすいといわれています。
無理にストレッチやマッサージを行うと悪化する場合もあるため、専門家の指導を受けながら改善を目指すことが大切です。
引用元:https://www.west-umeda-clinic.com/tfcc
#tfcc損傷 #手首の痛み #初期症状 #クリック音 #整形外科知識
tfcc損傷の検査と診断方法

手首の痛みが続く場合、TFCC損傷かどうかを判断するには、整形外科での検査が欠かせないといわれています。
見た目だけでは判断が難しいため、まずは痛みの出る場所や動作を丁寧に確認してもらうことが大切です。
引用元:https://www.west-umeda-clinic.com/tfcc
検査の流れとしては、最初に問診が行われ、痛みが出るタイミングや、どんな動作で悪化するかを詳しく聞かれます。
そのうえで、**手首を軽く押したり、ひねったりする「触診」**が行われることが多いです。
例えば、手首の小指側を押して痛みが強く出る場合や、ドアノブを回すような動作でズキッとする場合は、TFCC損傷が疑われると言われています。
画像検査の種類と目的
より正確に状態を確認するために、画像検査が行われることもあります。
レントゲン検査では、骨のズレや骨折の有無を確認します。
ただし、軟骨や靭帯といった柔らかい組織は写りづらいため、CTやMRIを使うこともあるようです。
MRI検査では、TFCCの断裂や炎症の有無、周囲の関節への影響などを詳しく調べることができるといわれています。
引用元:https://nambahandcenter.com/tfcc
さらに、明確な診断が難しい場合には、関節鏡検査という方法が選ばれることもあります。
関節鏡は、手首の内部を直接観察できる小型カメラのような器具で、損傷の範囲や位置をより正確に把握できるのが特徴です。
この検査は専門施設で行われることが多く、手術が必要かどうかの判断にも役立つといわれています。
引用元:https://sapporo-chuoseikei.com/column/tfcc-wrist-pain-treatment
検査結果によっては、固定や安静といった保存的な対応が中心になることもあります。
痛みが強い時期に無理をすると炎症が悪化する場合もあるため、**「我慢せずに早めの来院」**がすすめられています。
早期に原因を特定して、日常生活に合った対応を行うことが、改善への近道といわれています。
#tfcc損傷 #手首の検査 #MRI #関節鏡 #整形外科知識
tfcc損傷の施術と改善方法

TFCC損傷の対応は、症状の程度や生活環境によって変わるといわれています。
すべてのケースで手術が必要というわけではなく、**まずは保存的な方法(手術を行わない対応)**から始めるのが一般的です。
引用元:https://www.west-umeda-clinic.com/tfcc
初期段階では、痛みや炎症を抑えるために安静を保ち、手首を固定する装具(サポーターやギプス)を使用することがあります。
この時期は、できるだけ手首を動かさず、負担を軽減することが改善への第一歩とされています。
また、冷却や湿布、痛み止めの使用などで炎症を落ち着かせる方法も取り入れられています。
一方で、固定期間が長くなると筋力低下や関節のこわばりが起こる場合もあります。
そのため、痛みが落ち着いてきた段階で、**リハビリテーション(運動療法)**が行われることがあります。
理学療法士の指導のもとで、手首を支える筋肉を少しずつ動かす練習を行い、関節の安定を取り戻していくといわれています。
引用元:https://sapporo-chuoseikei.com/column/tfcc-wrist-pain-treatment
手術が検討されるケース
保存的な対応を続けても痛みが取れない場合や、TFCCの断裂が大きい場合には、手術が検討されることもあるといわれています。
手術の方法には、主に「関節鏡を使った修復」と「部分的な切除」があります。
関節鏡手術は、皮膚を大きく切らずに内部を確認しながら損傷部を縫い合わせるため、体への負担が少ないのが特徴とされています。
引用元:https://nambahandcenter.com/tfcc
また、尺骨の長さが橈骨より長く、繰り返し衝突することで痛みが出ている場合には、「尺骨短縮術」という骨の長さを調整する施術が行われることもあります。
いずれの方法も、医師が画像検査や関節の状態を確認したうえで判断するのが一般的とされています。
手術後は再発を防ぐため、一定期間の固定とリハビリが必要になります。
焦って動かそうとせず、専門家の指導に従って段階的に回復を目指すことが大切です。
このように、TFCC損傷の改善には「安静」「装具」「施術」「リハビリ」の4つを組み合わせて進めるのが基本といわれています。
#tfcc損傷 #手首の施術 #保存療法 #関節鏡手術 #リハビリ
tfcc損傷の回復プロセスと予後

TFCC損傷は、適切な対応を行えば改善が期待できるといわれています。
ただし、回復までの期間は損傷の程度や施術内容によって大きく変わります。
引用元:https://www.west-umeda-clinic.com/tfcc
一般的に、軽度の場合は数週間から数か月で痛みが落ち着くことが多いようです。
手首を固定しながら日常生活での負担を減らすことで、軟骨や靭帯の修復が進みやすくなるといわれています。
一方で、断裂が大きいケースや手術を行った場合は、完全に安定するまで3〜6か月ほどかかることもあるようです。
重要なのは、痛みが和らいできても急に負荷をかけないことです。
回復期に無理をすると、再び炎症を起こしてしまうことがあります。
焦らず、段階を踏んで日常動作を取り戻していくことが大切です。
日常生活での注意点と再発予防
日常生活では、手首にかかる負担を減らす工夫がポイントといわれています。
例えば、重い荷物を片手で持たず、できるだけ両手で分散させること。
また、ドアノブを回す・ペットボトルを開けるなどの動作で痛みが出る場合は、手首をひねらず肘や肩を使うように意識すると良いとされています。
引用元:https://sapporo-chuoseikei.com/column/tfcc-wrist-pain-treatment
スポーツを再開する際は、医師や理学療法士の指導のもとで行うことが重要です。
リハビリで得た筋力や可動域を維持しながら、手首の動きを少しずつ慣らしていくと再発を防ぎやすいといわれています。
特に、手首を強くひねる競技(野球・テニス・ゴルフなど)は、フォームやグリップの使い方を見直すことが改善につながるとされています。
引用元:https://nambahandcenter.com/tfcc
さらに、姿勢や体全体のバランスを整えることも、再発予防の一環として重要です。
首や肩、肘の動きがスムーズになると、手首への負担が軽減される傾向があるといわれています。
体全体を連動させて動かすことを意識するだけでも、日常生活の中で痛みを感じにくくなる場合があります。
#tfcc損傷 #手首の回復 #再発予防 #日常生活の注意点 #整形外科知識