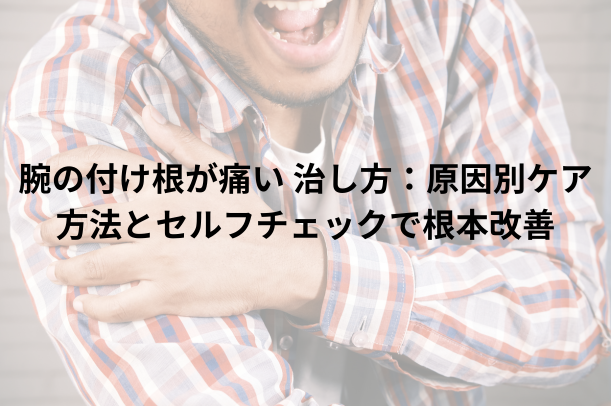腕の付け根が痛むと考えられる原因一覧と特徴

腕の付け根(肩・腋下周辺)が痛むとき、原因はひとつとは限らず、いくつかの要因が重なっていることもあります。ここでは代表的な原因と、それぞれがどのように痛みを引き起こすか、どんな動きで痛みが出やすいかを見ていきましょう。
肩関節周囲炎(いわゆる五十肩・凍結肩)
- 発生機序:肩関節を包む関節包や滑膜、周囲の腱・靭帯が慢性的に炎症を起こしたり癒着(くっつくこと)したりすることで、関節の動きが制限され、痛みを伴うようになると言われています。 国立癌研究センター+2理学ボディ+2
- 典型症状・痛むタイミング:
・腕をあらゆる方向に動かすと痛みが出やすい(上下・外転・内旋などあらゆる動きで) 慶崇会+2国立癌研究センター+2
・夜間痛(寝ているときにズキズキ痛む)や、じっとしていても痛む時間帯がある
・徐々に可動域が狭くなり、「腕が上がらない」「後ろに回しづらい」などの制限が出る
このような全方向的な痛み+動かしづらさが強い場合には、五十肩(肩関節周囲炎/凍結肩)を疑うパターンです。
腱板損傷(腱板断裂・腱板炎)
- 発生機序:肩のインナーマッスル群(腱板:棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)が長年の摩耗、使いすぎ、加齢変性、あるいは転倒など外力で損傷・断裂することがあります。断裂が部分的か完全かで程度が異なります。 国立癌研究センター+1
- 典型症状・痛むタイミング:
・腕を上げようとすると途中の角度(例:45~90度あたり)で痛みが強くなる
・腕を上げきる前後で引っかかる感じ、ズキッとする痛みが出ることも
・腕を動かさないと痛みは比較的落ち着くが、特定の動き(回旋・横から挙げる動作など)で痛む
・痛む方向が限定されやすく、「外転/捻り」で痛むことが多い
そのため、「腕を上げる途中が痛い」や「特定の方向で痛みが出る」ような症状のときは、腱板損傷を疑いやすくなります。
上腕二頭筋長頭腱炎
- 発生機序:上腕二頭筋の腱(長頭腱)が関節の近くを通る結節間溝(腱が滑る部分)で摩擦や過負荷を受けて炎症を起こすことがあります。 国立癌研究センター+1
- 典型症状・痛むタイミング:
・手のひらを上に向けて腕を前方に上げると痛みが出る(肩前方挙上動作で誘発されやすい) 慶崇会+1
・前腕をひねる(回外・回内)動作で肩前方に違和感や痛みが出ることも
・腱の走行上に圧痛(押すと痛い部位)があることが多い
このため、「腕を前に出す・回す動作で痛む」「特定の前方動作で響く感じがある」ケースでは上腕二頭筋長頭腱炎を視野に入れます。
関節炎・滑液包炎
- 発生機序:肩関節自体の関節炎(変形性関節症、リウマチ性関節炎など)や、肩の滑液包(関節包近辺の潤滑・クッション役の袋状組織)の炎症(滑液包炎)が起こることがあります。
- 典型症状・痛むタイミング:
・関節を動かすと痛みや硬さを感じる
・時に腫れ・熱感を伴うことがある
・安静時にも痛むことがある
・可動域制限や関節のこわばり感が強くなる
こういった「関節そのもの」「滑液包近傍」が炎症を起こしているパターンでは、動いた時だけでなくじっとしていても痛むことが多くなります。
神経性原因(頸椎性・胸郭出口症候群など)
- 発生機序:首(頸椎)の変形・椎間板ヘルニア・頚椎症などで神経根が圧迫される、あるいは鎖骨・肋骨・筋膜の間で神経や血管が圧迫される胸郭出口症候群などが原因になることがあります。
- 典型症状・痛むタイミング:
・肩や腕を動かしても痛みがあまり変わらないことがある
・首を動かすと肩や腕に響く痛み・しびれが出る
・しびれ、チクチク感、感覚異常を伴うことがある
・腕を使わない状態でもズーンと重だるさを感じることがある
このような場合、「肩を動かしても変わらない痛み」や「首・肩を動かすと響く感覚」「しびれ・異常感覚」を伴うときには、神経性の原因を慎重に考えるべきです。
筋肉・筋膜性の過負荷・緊張
- 発生機序:腕・肩・背中周辺の筋肉や筋膜に過度な負荷・使い過ぎ・疲労がかかり、筋繊維や筋膜の微細な傷・緊張が起こることがあります。ストレス・姿勢の悪さ・継続的な重い荷物の持ち運びなども誘因です。
- 典型症状・痛むタイミング:
・腕を使っている時(持ち上げ・押す・引く)などに痛むことが多い
・じっとしていると痛みは比較的軽くなることがある
・筋肉を押したときにコリ・張り感・圧痛を伴う
・動き出し(最初の一動作)で痛みを感じることがある
こうした筋・筋膜性の痛みは、使いすぎや姿勢不良が背景になることが多く、運動・ストレッチ・休息で改善しやすいことがあります。
内科的・全身性要因(稀なケース)
- 発生機序:腕・脇・胸郭付近の痛みが、循環器系・呼吸器系・胸膜・心臓・腫瘍・リンパ節腫脹など、全身性疾患・内科的な異常の影響で起こる可能性も否定できません。
- 典型症状・痛むタイミング:
・胸部症状(息苦しさ・胸部圧迫感・動悸など)を伴うことがある
・痛みが持続・進行性で、腕や肩の動きそのものと関連が薄いこともある
・腋下リンパ節の腫れ・しこりを触れることがある
こういう場合は、腕の動きのみで説明できない違和感・全身症状が伴うことが多く、慎重な評価が必要です。
このように、「いつ痛むか?」「どの動きで痛むか?」という視点で自分の症状を当てはめてみることで、どの原因が近いかを仮に絞り込むことができます。ただし、最終的には 専門家による検査 が不可欠であると言われています。
#腕の付け根の痛み
#肩関節周囲炎
#腱板損傷
#上腕二頭筋腱炎
#神経性痛み
痛みの段階別セルフケアの考え方

まず、腕の付け根・肩周辺の痛みには「急に炎症が強い時期(急性期/炎症期)」「炎症が落ち着き始める中立期」「回復・改善に向かう時期(改善期)」という流れがあると考えられています。
この “赤信号 → 中立 → 改善期” を目安に「いつ何をすべきか」を切り替えていくのが、セルフケアでは重要なポイントです。
炎症期(赤信号期:痛み・熱感が強い時期)の対応
この時期は、体が “反応” を起こしている状態なので、無理をせず抑制優先とするアプローチが一般的と言われています。
- 安静(動かさない):痛みが強いときは、関節を大きく動かさず、できるだけ過剰な負荷をかけないようにします。刺激を入れると炎症が悪化する可能性があると言われています。
- 冷却(アイシング・冷湿布など):患部が熱を帯びている、腫れ感があるといったときは、冷やして炎症を抑える意図で対応することがよいとされています。だいたい発症から 2〜3 日を冷却の目安とする論もあります。 ohda-hp.ohda.shimane.jp+2日本医専+2
- 動かさない範囲の軽い関節保持:完全に固めるのではなく、「痛みの出ない範囲」で少し動かす余地を残すこともあります(ただし無理は禁物)。
この時期では、温めたり強めの運動をすると炎症反応を刺激してしまう恐れがあるため、温熱アプローチは控えるのが普通だと言われています。 AR-Ex Medical Group+3ohda-hp.ohda.shimane.jp+3茨木市 まつお鍼灸整骨院 | 頭痛・骨盤矯正でお悩みなら!+3
中立期〜改善期(痛みが落ち着いてきた時期)の対応
炎症が収まりつつある段階では、「血流促進」「可動性回復」を意識したケアにシフトすると言われています。
- 温熱(温める):痛みが和らぎ、熱感・腫れが引いてきたら、温めて血流を改善し、組織の回復を促す方法がよく取り入れられます。例えば、温湿布やホットタオル、ぬるめのお風呂など。 fujiyaku-direct.com+4AR-Ex Medical Group+4hirai-seikei.com+4
- 軽い運動・ストレッチ:関節を徐々に動かすストレッチや可動域訓練、インナーマッスル強化運動などを、痛みの出ない範囲で取り入れていくことが推奨されます(無理なく、段階的に)。
- 段階的な負荷の導入:重いものを持つ、反動をつけるなどの高負荷動作は慎重に。少しずつ動かす量・範囲を広げていきます。
この切り替え時期を見誤ると、炎症を再燃させてしまうリスクもありますので、「熱感がなくなり、痛みもやや軽くなった」など変化を目安に判断することが多いようです。 足立区 梅島駅から徒歩4分のすずらん鍼灸院|医師が推薦する鍼灸院+3日本医専+3医療法人社団 東整会 東京神田整形外科クリニック+3
温める vs 冷やす の使い分けポイント
痛み対策でよく迷う「温めるか冷やすか」の使い分けですが、次のような基準がよく紹介されています。
| 状況 | 優勢な対応 | 解説 |
|---|---|---|
| 痛み・熱感・腫れが強いとき | 冷やす(冷湿布・アイシングなど) | 炎症抑制、腫れの拡大を抑える意図があるとされます。 久我山病院+3ohda-hp.ohda.shimane.jp+3茨木市 まつお鍼灸整骨院 | 頭痛・骨盤矯正でお悩みなら!+3 |
| 痛みが弱まり、熱感・腫れが落ち着いたとき | 温める(温湿布・温熱療法) | 血流を高めて組織回復を助ける目的で行われます。 fujiyaku-direct.com+4AR-Ex Medical Group+4hirai-seikei.com+4 |
| 判断しづらいとき | 触って熱ければ冷やす、冷たく感じたら温める目安とする | 患部を軽く触って “熱感” の有無を確認して切り替えることも一部で紹介されています。 ohda-hp.ohda.shimane.jp+2久我山病院+2 |
ただし、冷やしすぎ・長時間冷却・過度の温熱も組織に負担になる可能性が指摘されており、状態を見ながら適切な時間設定(例えば冷やすなら 10〜20 分程度など)を意識することが勧められています。
市販薬・湿布・鎮痛剤の使い方・注意点
セルフケアとして使われやすい市販薬・湿布・鎮痛剤の使い方と注意点もおさえておきましょう。
- 湿布・貼り薬:消炎鎮痛成分(NSAIDs 系:ロキソプロフェン、ジクロフェナクなど)入りのものが多く、痛みや炎症を和らげる効果が期待されるとされています。 セルフケア整体+3くすりの窓口+3第一三共ヘルスケア+3
ただし、製品に記載された用法・用量を守ることが基本で、長期間同じ部位に貼りっぱなしにすることは避けるよう注意が促されています。 第一三共ヘルスケア+2エスエス製薬+2
また、湿布による皮膚刺激・かぶれ、光線過敏症、併用薬との相互作用にも配慮が必要です。特に日光照射時には注意が必要な成分もあります。 Minacolor+2エスエス製薬+2 - 経口の鎮痛剤(飲み薬):痛みが強くて日常生活に支障がある場合に使われることがあります。NSAIDs 系などが代表的で、炎症を抑えつつ痛みを和らげる働きがあります。 セルフケア整体+2くすりの窓口+2
ただし、胃腸への負担、腎機能への影響、他の薬との相互作用、副作用(吐き気・胃痛など)を考慮して、なるべく最少用量・短期間使用が推奨されるとされています。 エスエス製薬+2セルフケア整体+2 - 使用するタイミング・期間の目安:湿布ならば通常 3~4 日程度使って変化がなければ検討を見直す、悪化する場合は早めに医療機関に相談する、といったガイドもあります。 第一三共ヘルスケア+1
日常動作で避けるべきこと・注意点
セルフケアの段階で特に注意しておきたい「避けたほうがいい動作・習慣」について、次の点を意識するとよいでしょう。
- 強く腕を振る・急な動き:急激な動作や反動をつけた動きを行うと、炎症部位に刺激を与えてしまうことがあります。
- 重い物を持つ:重さのある荷物を持つことで肩や腕に大きな負荷がかかるため、可能な限り軽くする工夫を。
- 腕を高く上げ続ける動作:腕を高く上げた状態を長時間維持する姿勢は、肩関節へのストレスを増やす可能性があります。
- 無理に可動域を広げようとする:痛みがまだ残る状態で無理にストレッチを push するようなことは逆効果になることもあると言われます。
- 長時間同じ姿勢・不良姿勢:例えばデスクワーク中に腕を前に突き出す姿勢、スマホ操作で肩が前に倒れる姿勢などは負荷を増やすので注意が必要です。
#腕の付け根の痛み
#肩痛セルフケア
#冷却と温熱の使い分け
#市販薬注意点
#段階別対処法
実践ストレッチと運動プログラムの考え方

腕の付け根・肩の痛みを改善していくには、「可動性をつけるストレッチ」「筋力強化・安定化」「毎日続けやすい習慣化」が鍵になります。ただし、無理をして痛みを誘発してしまうと後戻りするので、“痛みの出ない範囲”を守りつつ進めていくことが大切だと言われています。
痛みが出にくいストレッチ例(肩外旋・広背筋・テーブルサンディングなど)
以下は、比較的安全に取り組みやすいストレッチ例です。無理なく、ゆっくりと行うことを念頭に置いてください。
- 肩関節外旋ストレッチ
肘を体側につけ、肘を90度に曲げたまま前腕を外側にゆるやかに回すストレッチ。抵抗がかからない軽い範囲で行うようにします。
また、セラバンドや軽いバンドを使って、抵抗を加えず「誘導するように」回旋運動を行う方法も紹介されています。引用元:Drugs.com「Shoulder external rotation」 Drugs.com - 広背筋ストレッチ
片手を上に上げ、反対側の腰を支点にして、体を横に倒すようにして背側(脇下~広背筋あたり)を伸ばす動き。長時間同じ姿勢で固まりがちな背中・脇の筋肉に有効とされます。
また、Rehasaku 等では肩甲骨まわりストレッチを紹介しており、肩・背中の連動を意識するストレッチが効果的という見解があります。引用元:Rehasaku「肩甲骨はがし」 リハサク - テーブルサンディング(テーブルトップ面を使ったスライド運動)
テーブルや机に手をつき、手を滑らせながら前後・左右に動かすストレッチ。肩の可動域をゆるやかに拡げていくアプローチとして紹介されることが多いです。
※この種の滑らかな動きを使うストレッチは、過度な力を入れず “支えながら誘導” する感覚で行うと比較的安全とされます。
これらストレッチは、痛みが出ないレベルでゆっくり数十秒保持 or 反復 を原則とし、無理して伸ばし過ぎないように注意します。
筋力強化/安定化運動(インナーマッスル・体幹連動)
ストレッチだけでは不十分で、肩を支える筋肉(特にローテーターカフ・肩甲下筋・菱形筋・僧帽筋中・下部など)の強化と、体幹との連動性を高める運動も重要です。
- アイソメトリック回旋(等尺性内旋・外旋)
壁やドア枠を使って、手のひらまたは手の甲を軽く押し当てて力を入れる(回旋方向に押す/戻す)が紹介されています。肩関節インピンジメント予防にも使われるアプローチです。引用元:HSS「Isometric Shoulder Internal & External Rotation」 Hospital for Special Surgery - サイドライイング外旋運動
横向きに寝て、痛みのない側を下に。上側の腕を肘90度で固定して、前腕を天井方向に回す運動。抵抗は軽いダンベルや軽い重さから始め、ゆるやかに戻すようにする方法が多く紹介されています。引用元:HSS サイドライイング外旋運動 Hospital for Special Surgery+1 - バンドを使った回旋トレーニング
セラバンドを柱やドアノブに固定し、肘を体側につけたまま前腕を外側(あるいは内側)に回す。抵抗を制御しながら動かすことでローテーターカフを強化できます。引用元:Stone Clinic「Theraband external & internal rotation」 Th Stone Clinic - 体幹連動型の引く動作(ロウイング系)
バンドや軽いケーブルを使ったローイング動作。肩甲骨の制御を伴った引き動作は、肩と背中の筋肉を連動させて安定性を高める効果が期待されます。Healthline などではこれを回復期の補助運動として紹介しています。引用元:Healthline「Rotator cuff exercises」 Healthline
これら運動は、最初は軽い抵抗または無負荷、ゆるやかな動きで始め、痛みが強くならない範囲で徐々に強度を上げていくことが一般的に推奨されると言われています。
毎日継続できる簡易体操ルーチンの例
以下は、毎日無理なく続けやすい体操ルーチン案です(目安:5〜10分程度):
- 肩関節ゆるゆる回旋(前後・上下)をゆっくり 1 分
- テーブルサンディング滑らせ運動 10 回 × 2 セット
- 肩外旋ストレッチ(肘90度保持) 30 秒 × 左右
- サイドライイング外旋(軽抵抗または無抵抗) 8〜10 回 × 左右
- 軽いロウイング系バンド引き運動 10 回 × 2 セット
このように複数種目を少しずつ混ぜて、痛みを誘発しない範囲で毎日続けられるようなルーチン構成が有効と考えられています。
ストレッチ・運動を行う際の注意点・痛みの出ない範囲設定
運動を“やりすぎ”たり“無理に伸ばしにいく”と逆効果になることもあるため、以下の点に気をつけるといいでしょう:
- “響く痛み” はストップライン:軽い違和感程度は許容範囲とされることもありますが、「ズキッと響く/鋭い痛み」が出たらその動作は中止する。
- 翌日痛みが強くなるなら強度抑える:運動後、翌日痛みが明らかに増すようなら負荷を落とすべきというガイドが複数出ています。引用元:E3Rehab「Shoulder range of motion progression」 e3rehab.com
- ゆっくり動かす・反動をつけない:勢いをつけると筋や腱に衝撃がかかるため、ゆっくり丁寧な動作を意識
- 可動域は “痛みが出ない直前まで” を目安に:完全に痛みのない範囲を動かす、ストレッチも伸ばし過ぎず
- 肩甲骨の安定を意識:肩だけを動かすのではなく、肩甲骨(肩の後ろの骨)をしっかり支えて使う感覚を養う
- 毎日必ずやらなくてはならないわけではない:疲労を感じるときは休む。継続性を重視
- 症状が強いとき・長引くときは専門家に確認を:自己流で進めると悪化リスクもあるため、改善が見られなければ検査を受けることも大事とされます。
ハッシュタグのまとめ(5つ)
#腕の付け根の痛み
#肩ストレッチ
#ローテーターカフ強化
#毎日体操ルーチン
#痛みを出さない運動
日常習慣でできる予防・改善アプローチ

痛みが軽くなったあとは、日常生活の積み重ねが再発防止やさらなる改善につながります。「無理せず続けられる工夫」を中心にして、以下のような習慣を取り入れておくとよいでしょう。
姿勢改善(デスクワーク・スマホ使用時の首・肩位置)
- 頭と背骨を一直線に保つ意識
スマホやパソコンを使うとき、うつむき姿勢になりやすいですが、これが首・肩に負荷をかけると言われています。あごを引き、頭頂を天井方向に軽く引き上げるような意識で姿勢を整えるとよいと考えられています。引用元:あいち診療所「肩の痛みと姿勢の関係」 あいち診療会 - 椅子・机の高さ調整
肘が自然に90度前後になるような高さにし、ディスプレイは目線近くに置くのが理想的とされています。引用元:エーザイの肩こり姿勢解説「背筋を伸ばし、首を前傾させないように」 エーザイ株式会社のセルフケア製品情報 - こまめな姿勢リセット
1時間ごとに立ち上がる、軽く肩を後ろに引く、背伸びをする、など“こわばりを防ぐ動き”を挟むように促す記事も見られます。引用元:アンカークリニック「作業姿勢を整える、肩を固まらせないようにする」 anchor-clinic.jp
肩・腕にかかる負荷を減らす工夫(荷物・動作の見直し)
- 荷物は体幹近くで持つ/両手で分散
バッグや荷物を片肩だけにかけると、肩が引っ張られる負荷が増す可能性があります。リュックを使う、左右交互に持ち替える、持ち物を軽くする工夫が紹介されています。引用元:エーザイ姿勢解説「バッグは肩から下げるタイプを避け、リュックを使う」 エーザイ株式会社のセルフケア製品情報 - 動作の工夫(肘を曲げて引く、体を回して物を取る)
腕を伸ばしたまま引く、無理に肩を使って物を持ち上げるような動作を控えるとよいとする見解があります。引用元:SakraWorld Hospital「過度の使用・反復動作を避ける」 sakraworldhospital.com - 重い物は脚・体幹を使って
腕だけで持ち上げず、腰・膝を使うよう意識することで肩への負荷を抑えるという教えも見かけます。引用元:同上 sakraworldhospital.com
生活習慣(運動頻度・睡眠・ストレス管理)
- 適度な運動を習慣化
ウォーキング・水泳・ヨガなど、肩関節に過負荷をかけない運動は、血行促進や筋肉バランス維持につながるとされています。引用元:Seikei-Mori「肩の痛みを予防する生活習慣」 seikei-mori.com - 良質な睡眠確保
睡眠不足や浅眠は体の回復力を落とすため、痛みの改善や再発防止には十分な睡眠が大切だという見方があります。引用元:Seikei-Mori 同上 seikei-mori.com - ストレス管理
慢性的なストレスが筋肉の緊張を引き起こすことが報告されており、リラックス法(深呼吸・ストレッチ・軽い運動など)を取り入れておくメリットが指摘されます。引用元:同上 seikei-mori.com
血行促進法(入浴・温熱利用・マッサージ)
- ぬるめのお風呂にゆったり浸かる
体を温めることで血行が改善し、筋肉の緊張を緩和できるという報告があります。引用元:Seikei-Mori「温罨法で血行促進」 seikei-mori.com - 温湿布・ホットパック活用
長時間冷えて硬くなった筋肉には、温めることで柔軟性を保つアプローチも用いられています。ただし、炎症が強いときは冷やす方を優先する必要性も指摘されます。引用元:Seikei-Mori 同上 seikei-mori.com - 優しいマッサージ/筋膜リリース
強くもみすぎると筋繊維を傷つける恐れがあるため、軽い圧でほぐすようにするべきという注意書きもあります。引用元:サワイ健康推進課「肩こりにおすすめ肩甲骨ストレッチ・マッサージに対する注意」 サワイ健康推進課
再発防止の視点(定期的ケア)
- 週 1〜数回のメンテナンス体操
痛みが落ち着いた後も、ストレッチ・軽い運動を定期的に続けておくことで、再び関節・筋肉が硬くなるのを防ぐという見解があります。引用元:リルラ「四十肩・五十肩予防の体操習慣」 LiLuLa | - 自分の “こわばり信号” を把握する
肩や腕周辺がいつも重く感じる、引っぱられる感じ、可動性が狭くなる前触れを意識して、早めにストレッチを入れる習慣をつけるという対策があります。引用元:アンカークリニック「肩を固まらせないようにする」 anchor-clinic.jp+1 - 定期チェック・見直し
姿勢、仕事環境、日常動作に変化があれば見直す。特にデスク環境や荷物持ち動作などは、気づかず習慣化しやすいので、定期的に「これで大丈夫かな?」とチェックすることが望ましいという視点もあります。引用元:同上 anchor-clinic.jp
#姿勢改善習慣
#肩の負荷を減らす工夫
#生活リズムと肩の健康
#血行促進セルフケア
#再発防止メンテナンス
改善しない・悪化したときの対処と受診の判断基準

痛みが続いたり強くなったりしたときには、自己流ケアだけで進めるのはリスクがあります。ここでは「要注意症状チェックリスト」「受診先ガイド」「医療対応の選択肢」「改善期間・リハビリの流れ」「専門家相談時の準備」の観点から、読者が次のステップを判断しやすいようにまとめます。
この症状なら要注意:チェックリスト
次のような症状がある場合は、まず「専門家による評価」を検討すべきサインと言われています:
- 腕や手の しびれ・感覚異常(チクチク・痺れ)
- 夜間痛(寝ているときにもズキズキ痛む)
- 腕がまったく 上がらない・腕を動かせない
- 痛む部位に 熱感・腫れ・赤み が見られる
- 痛みが 急激に始まった、あるいは 急に悪化した
- 痛みが 3週間~1か月以上改善しない(改善傾向を感じない)
- 痛みだけでなく、 発熱・倦怠感・他部位の症状併発 がある
複数該当する場合、特に重度・炎症性・神経性の可能性を念頭に、早めに来院を考える方が安全です。肩の痛みで “眠れないほど強い痛み” がある時点で受診目安とする見解もあります。 引用元:ユビー「肩の痛みがある場合の、受診の目安」 症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie
また、痛みが 1 週間以上続く、あるいは動かしにくさが増すようなら整形外科の受診を検討すべきというガイドもあります。 引用元:Doctors File「四十肩・五十肩の受診目安」 ドクターズ・ファイル
受診すべき診療科(どこに行くか)
痛みの原因を明らかにするには適切な診療科を選ぶことが肝心です。一般的な受診ルートは以下の通りとされています:
- 整形外科:骨・関節・腱・靭帯・神経・筋肉などを含む「運動器領域」の専門。肩・腕の痛みでまず最初に相談されることが多い科です。 引用元:Knee-Cell「肩の痛いときは何科?」 札幌ひざのセルクリニック|変形性膝関節症・手術しない膝治療
- リハビリテーション科 /理学療法科:整形外科で初期評価を受けた後、リハビリ専門家の運動療法・物理療法・機能回復プランを行う部門
- ペインクリニック:慢性的・難治性痛・神経痛が疑われるケースで鎮痛注射などを扱う施設。 引用元:Seikei-Moriブログ「肩こりは何科?」 seikei-mori.com
- 内科 /救急外来:痛みが肩・腕だけでは説明しきれない(胸痛・呼吸困難・心臓関連症状などがある)場合は、まず内科や救急外来での全身評価が優先されることがあります。 引用元:クリニークハル「肩が痛いときに何科?」 クリニークハル大阪梅田 | 大阪梅田の整形外科ならクリニークハル大阪梅田
医療による治療法:選択肢と特徴
来院後の診察・検査によって、保存的アプローチから外科的対応までが選択肢になります。
| 治療法 | 主な内容 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 理学療法(運動療法・可動域訓練) | 専門家指導で肩の可動域回復・筋力強化を段階的に進める | 多くのケースで第一選択となる。3ヶ月程度続けても改善が乏しい場合には次ステップを検討することがあります。 引用元:梶田ら「拘縮肩の積極的治療法」 杏嶺会 |
| 注射療法(ステロイド・局所ブロック注射など) | 関節内注射、滑液包周辺注射、神経ブロック注射など | 炎症が強いときの鎮静作用を期待。繰り返し注射には軟組織への影響リスクもあるとされます |
| 手術療法 | 関節鏡視下手術(腱板修復・授動術など)、人工肩関節手術など | 腱板断裂など構造的損傷が重度な場合に選択されることがあります。術後リハビリ期間が長くなることが多い。 引用元:Muto 整形外科「肩腱板損傷 回復期間」 muto-seikei.com また、腱板手術の術後入院・回復経過の記載も霞ヶ浦医療センターより。 引用元:霞ヶ浦医療センター「腱板断裂」 kasumigaura.hosp.go.jp |
改善までの目安期間・リハビリの流れ
痛み・可動域制限の改善には時間を要することが多く、損傷の程度・個人差・治療開始時期などによって大きく変動します。
- 五十肩・肩関節周囲炎:軽症例では数週間〜数か月程度で痛みが軽減することもある一方、重症例では 1 年半〜 3 年かかるケースも報告されています。 引用元:Okuno-Y Clinic「五十肩の経過」 オクノクリニック
- 腱板損傷(非手術例):軽度なら数ヶ月で日常動作レベルに改善、中等度で 6~12 か月、重度で 1 年以上かかることもあります。 引用元:Muto 整形外科「肩腱板損傷 回復」 muto-seikei.com
- 手術後:関節鏡下手術後、日常生活レベルの機能回復は 3 ヶ月前後という報告もあります。 引用元:Tsunashima 整形外科「五十肩 手術後のリハビリ」 tokyo-jointclinic.jp ただし、スポーツ復帰や高負荷動作復帰まではさらに数ヶ月を要することも。 引用元:霞ヶ浦医療センター「腱板断裂術後」 kasumigaura.hosp.go.jp
- リハビリ流れ(例):
1. 初期:他動・受動的可動域訓練(理学療法士が補助)
2. 中期:自動運動・軽い抵抗運動導入
3. 後期:機能改善・筋力強化・日常生活動作練習
4. 維持期:定期的ストレッチ・負荷トレーニング
ただし、3 ヶ月以上リハビリを継続しても改善が乏しい場合は、注射や手術など “積極的治療” を検討する段階になることがあるとも言われています。 引用元:梶田ら「拘縮肩の積極的治療法」 杏嶺会
専門家に相談するときの準備:伝えるべき情報と記録
受診・相談をスムーズにし、的確な評価を受けるためには、以下をあらかじめ整理しておくとよいでしょう:
- 症状開始時期と経過:いつから痛みが出たか、どのように変化してきたか
- 痛みの性質・増悪因子:ズキズキするか・鋭いか・しびれを伴うか・どういう動作で悪化するか
- 可動域・制限具合:どの方向に腕を動かせないか、どこで引っかかる感じがするか
- 痛みのある動作・日常生活で困る動き:家事・服の着替え・洗顔などで支障があるか
- 写真・動画や動作記録:痛みを感じている肢位・動作をスマホ動画で残しておくと、医師が判断しやすくなることがあります
- 既往歴・内科的背景:糖尿病・高血圧・骨粗鬆症・心疾患など持病があれば伝える
- これまで試したセルフケア・薬(湿布・鎮痛薬など)使用歴
これらを整理しておくことで、医師・理学療法士とのコミュニケーションがスムーズになり、より適切な検査・治療につながる可能性が高まると言われています。
#肩の痛み要注意サイン
#整形外科受診目安
#肩痛と医療の選択肢
#リハビリ回復期間
#専門相談の準備ポイント