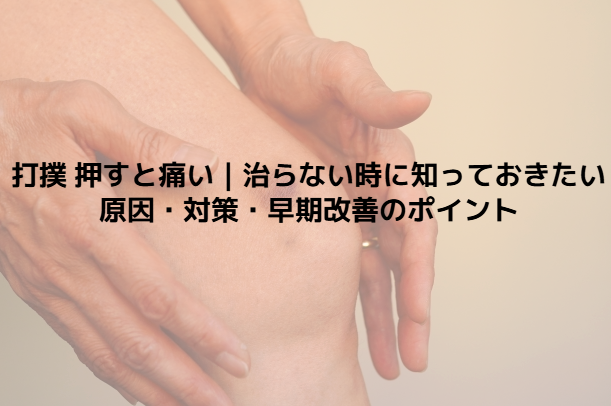なぜ「打撲 押すと痛い 治らない」のか?原因と見落とされがちな損傷パターン

軽い打撲だと思って放置すると長引くことも
「打撲 押すと痛い 治らない」って、どうして起こるの?と思われるかもしれません。実は、誰もが「ただぶつけただけ」と思っていても、打撲によって患部の筋肉・血管・骨膜などが損傷しており、しばらくしてから“押すと痛い”という状態が残ることがあると言われています(引用元:パルモ大井町整骨院「打撲」症状や原因について https://www.palmo-os.com/symptom/bruise )。
つまり、見た目には「あざも腫れも大したことない」と思えても、その内部では血液の出血・腫れ・炎症という連鎖が始まっており、それが適切に落ち着かなければ痛みが長引きやすくなるのです。
骨膜打撲・微小骨折・血腫形成など、見落とされやすい損傷とは?
特に“治らない”ケースで見落とされがちなのが、骨膜を覆う組織が傷ついた「骨膜打撲」や、ぶつけた衝撃で微細な亀裂が入る「微小骨折」、あるいは筋肉内や骨の近くで血液がたまり硬くなる「血腫」ができてしまっている状態です。骨膜打撲では「時間を追うごとに痛みが強くなり、治りづらい傾向がある」と言われています(引用元:パルモ大井町整骨院 https://www.palmo-os.com/symptom/bruise )。さらに、血腫が硬化して「押すと痛むしこり」となることも、専門の現場で報告されています(引用元:こばやし接骨整骨院グループ「骨化性筋炎」参照 https://kobayashi-oc.jp/2023/01/08/kokkaseikinen/ )。
こうした損傷があると、ただ“安静にしていればいつか改善する”という期待だけでは進まず、痛みが“押すと痛い”という形で残ることがあります。
「軽い打撲だから大丈夫」と思った時こそ要注意
ぶつけた直後は腫れもあまり出ず「動けるから大丈夫」と思いがちですが、この油断が長引きの原因になりやすいと言われています。例えば、ある整骨院では「打撲の痛みや腫れは通常2〜3週間で改善するものだが、4週間以上治らない場合は骨折や捻挫の可能性が高い」と説明されています(引用元:クリニック事故24「打撲の痛みはいつまで続けば病院に行くべき?判断基準や治し方」 https://clinic.jiko24.jp/jiko-info/treatment/bruise-pain-until-when/ )。
つまり、「押すと痛い・治らない」状態が続くということ自体が、軽視できないサインということです。
以上より、「打撲 押すと痛い 治らない」と感じたときには、自分で「ただぶつけただけ」と判断せず、押すと痛むしこり・腫れの残り・動かすと痛むといったサインを見逃さないことが、早めの改善につながるポイントと言われています。
#打撲押すと痛い
#打撲長引く原因
#骨膜打撲
#血腫硬化
#打撲応急処置
押すと痛い・治らない打撲にありがちな見落としポイント

「軽い打撲だから大丈夫」と思っているときこそ注意
「打撲 押すと痛い 治らない」と感じるとき、まず考えておきたいのが『ただの打ち身だから』と軽く考えて放置してしまう点です。実際には、打った直後に「動けるから大丈夫」と思っても、内部では筋肉・血管・骨膜などがダメージを受け、痛みが長引くケースがあると言われています(引用元:メディカルック「なぜ?打撲して、押すと痛いのが治らない…病院行くべき?」 https://medicalook.jp/bruise-tenderness-does-not-heal/ )。
その結果、押すと痛む“しこり”や内出血の色が残ったまま、数週間経っても変化しないという状態に至ることがあります。
骨膜打撲・微小骨折・血腫形成…見落とされやすい損傷とは?
「押すと痛いまま治らない」背景には、骨膜を覆っている膜が損傷する『骨膜打撲』や、骨内部に微細な傷が入る『骨挫傷(こつざしょう)』、また筋肉内や骨の近くに出血がたまる『血腫』など、見落とされやすい損傷が隠れているといわれています(引用元:倉石整形外科クリニック「もしかして骨折?「いいえそれは骨挫傷です」」 https://kuraishi-seikei.com/column/2242/ )。
例えば骨挫傷では、X線では異常が見えず、「押すと強く痛む」「少しぶつけただけでも痛みが出る」「時間が経っても痛みが残る」といった特徴があり、通常の打撲と見分けづらいとされています。
放置すると慢性化・機能制限につながるリスク
また、痛みが続いているにもかかわらず「時間が経てば治る」と安易に判断してしまうと、修復されていない組織が硬くなったり、しこりが残ったりして、関節の可動域が狭くなるなど“打撲後の後遺症”的な状態になることがあります(引用元:こーしん接骨院「打撲の早期回復を目指すなら」 https://www.koushin-cs.com/symptom/bruise )。
こうしたケースでは、「押すと痛い」という状態そのものが、体からの“処置を要するサイン”という見方もできるため、症状が長引く場合は専門家の触診・検査を検討することがすすめられています(引用元:みんなの家庭の医学「転倒後3週間経過しても打撲の痛みが治まらない」 https://kateinoigaku.jp/qa/8610/ )。
このように、「打撲 押すと痛い 治らない」場合、よくある軽い打ち身の範囲を超えている可能性があるため、放置せずに“押すと痛む・しこりが残る・長引く”というサインを見逃さないことが、早期改善につながると言われています。
#打撲押すと痛い
#打撲長引く原因
#骨膜打撲
#骨挫傷
#血腫硬化
自宅でできる“まずはここから”セルフケア方法

打撲直後は「RICE処置」で炎症を広げない
「打撲 押すと痛い 治らない」と感じたとき、最初の対応で回復スピードが大きく変わると言われています。ぶつけた直後は、まずRICE処置(Rest:安静、Ice:冷却、Compression:圧迫、Elevation:挙上)が基本です。
無理に動かさず、冷たいタオルや保冷剤をタオル越しに10〜15分あてて患部を冷やすと、内出血や炎症の広がりを抑えられるとされています(引用元:日本整形外科学会「打撲の応急処置」 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/bruise.html )。
冷やす時間は「冷やして・休んで・再度冷やす」を数回繰り返すイメージで。長時間の冷却は逆に血行を悪くすることもあるため、様子を見ながら調整するのがポイントです。
48時間以降は「温め・軽い動き」で血流を促す
冷却期間を過ぎても押すと痛い状態が続くときは、内出血による血液の滞りや、筋肉のこわばりが関係していることが多いと言われています。そのため、48時間ほど経過して腫れが引いてきたら、今度は温めて血流を促すケアに切り替えましょう。
蒸しタオルを患部に当てたり、入浴時にゆっくり温めることで、体内の老廃物が流れやすくなり、回復を助けると言われています(引用元:熊野見整骨院公式ブログ https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/ )。
また、軽く関節を動かすストレッチを取り入れると、筋肉の緊張がやわらぎ、血液やリンパの循環が整いやすくなるとされています。
押すと痛い部分を無理に揉まない
多くの人が「マッサージしたら早く治るのでは?」と思いがちですが、炎症が残っている時期に強く押すと、逆に痛みが悪化することがあります。
特に、腫れや熱感が残っているうちは刺激を加えず、自然な回復を待つことが大切です。痛みが落ち着いてきてから、やさしくさするようなマッサージを行うと、血流改善やしこりの軽減につながることもあるといわれています(引用元:オレンジ接骨院「打撲のセルフケア」 https://orange-bone.com/bruise-care/ )。
セルフケアは“早く動かす”ことよりも、“今の状態を悪化させない”ことを目的に行うことがポイントです。
#打撲セルフケア
#RICE処置
#冷却と温熱
#打撲後マッサージ
#炎症ケア
「治らない」と感じたら何が原因?次のステップ&専門家への相談タイミング

1〜2週間経っても押すと痛いのは「要チェック」
通常、軽度の打撲であれば1〜2週間ほどで痛みや腫れが落ち着いてくるといわれています。それにもかかわらず「押すと痛い」「しこりが残っている」「腫れが引かない」といった状態が続く場合、表面上の打撲だけではなく、骨膜や筋肉の深部が損傷している可能性もあります(引用元:メディカルック「打撲して押すと痛いのが治らない…病院行くべき?」 https://medicalook.jp/bruise-tenderness-does-not-heal/ )。
また、打撲した部分を押すとズキッと痛んだり、寝返りや歩行など日常動作で痛みが走るような場合も、見えない損傷が広がっているサインとされています。
骨・軟部組織・血腫の可能性を見落とさない
痛みが長引く原因として、骨膜打撲や微小骨折(骨挫傷)、筋肉内の血腫(血の塊)などが挙げられます。特に血腫は、時間が経つと硬くなって“しこり”のような感触になり、押すと痛みが再発することがあります。これらの損傷は見た目では判断しづらく、湿布や安静だけでは改善しにくいケースもあると言われています(引用元:こばやし接骨整骨院グループ「骨化性筋炎」 https://kobayashi-oc.jp/2023/01/08/kokkaseikinen/ )。
もし患部にしこりや熱感が残っている場合は、炎症が内部で持続している可能性があるため、早めに専門家の触診を受けることがすすめられています。
整形外科・整骨院どちらに行くべき?
「押すと痛い」「治らない」状態が続く場合、まずは整形外科でレントゲンやMRIなどの検査を行うことで、骨折や骨挫傷の有無を確認することができます。一方、整骨院では、筋肉や関節の動き、血流の滞りなど、よりソフトな部分の評価・施術を受けられるのが特徴です。
痛みの原因が骨の損傷か、筋肉や軟部組織のトラブルかによって対応が変わるため、まず整形外科で検査を受け、その後必要に応じて整骨院で回復サポートを受けるという流れが推奨されることもあります(引用元:熊野見整骨院公式ブログ https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/ )。
「我慢せず早めの確認」が早期改善への近道
「打撲は放っておけばそのうち治る」と思われがちですが、押すと痛い・動かすとズキズキする・腫れが2週間以上続くなどの場合は、自己判断よりも専門的な確認が重要です。早めに原因を特定し、必要なケアを始めることで、長期化や後遺症を防げる可能性が高いと言われています。
#打撲治らない
#押すと痛い原因
#骨挫傷
#整形外科と整骨院
#早期相談
再発・慢性化させないための予防・メンテナンス習慣

打撲を繰り返す人に共通する習慣とは?
「打撲 押すと痛い 治らない」経験が何度もある人は、実は日常の動き方や体の使い方に共通点があると言われています。たとえば、姿勢のクセや筋力のアンバランスで転倒・衝突しやすい体勢ができていたり、スポーツ中に筋肉が硬いまま動くことで衝撃を吸収できず、打撲を起こしやすくなったりするケースがあります(引用元:熊野見整骨院公式ブログ https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/ )。
また、睡眠不足や栄養バランスの乱れによって筋肉の回復が遅れ、軽い衝撃でも内出血しやすい体質に傾くこともあるため、日常的な体のメンテナンスが大切です。
筋力・柔軟性を保つことが最大の予防策
打撲を防ぐうえで重要なのは、筋力と柔軟性を保つことだとされています。特に太ももやお尻の筋肉(大腿四頭筋・大臀筋)は、転倒や衝突の衝撃を吸収する「クッション」のような働きをします。ストレッチや軽い筋トレを日常的に行うことで、筋肉がしなやかに動き、外力を受けた際のダメージを軽減できると言われています(引用元:オレンジ接骨院「打撲のセルフケア」 https://orange-bone.com/bruise-care/ )。
また、運動前後のウォーミングアップ・クールダウンを怠ると、筋肉が硬いままの状態で動いてしまい、再び打撲や肉離れを起こしやすくなるため注意が必要です。
日常生活でできる「ぶつけにくい体づくり」
打撲の再発を防ぐには、単に気をつけるだけでなく、「ぶつけにくい体の使い方」を身につけることもポイントです。
例えば、階段を上るときは手すりを使う、夜の移動では明るい足元を確保するなど、環境面の工夫で打撲のリスクを減らすことができます。また、足裏のバランスを整えるインソールの使用や、正しい姿勢での歩行を意識することで、転倒防止にもつながるといわれています(引用元:クリニック事故24「打撲の痛みはいつまで続けば病院に行くべき?」 https://clinic.jiko24.jp/jiko-info/treatment/bruise-pain-until-when/ )。
回復後も“使いながらケア”を意識する
打撲の痛みが治まっても、完全に元の状態に戻るまでには時間がかかることがあります。痛みが引いた後も軽めのストレッチや温浴を継続して、血流を促す習慣を続けることが再発予防になります。
特に、気温が低い季節や冷房が効いた環境では筋肉が硬くなりやすいため、「冷やさない・動かす・ほぐす」の3つを意識することが重要です。
再発を防ぐためには“治ったあとこそケアを続ける”ことが、長期的に健康な体を保つ秘訣と言われています。
#打撲予防
#再発防止
#柔軟性アップ
#筋力トレーニング
#メンテナンス習慣