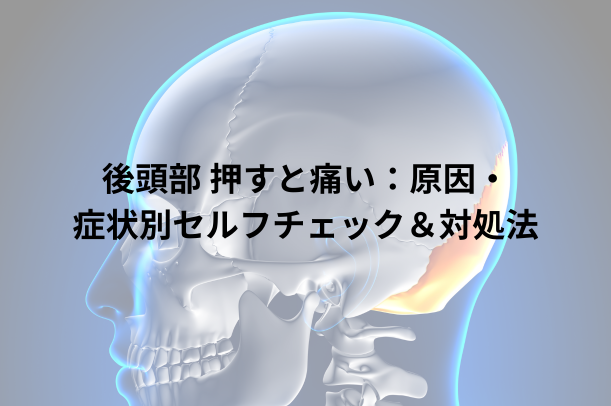後頭部を押すと痛いという症状:まず確認すべきポイント

痛み方や場所で原因の見当がつくことも
「後頭部を押すと痛い」と感じたとき、最初にチェックしたいのは“どこを押すと痛いのか”という部分です。痛みが後頭部の中央なのか、左右どちらか寄りなのか、首との境目あたりなのかによって、原因が少しずつ違うと言われています。たとえば、首の筋肉のこりが関係している場合は、首の付け根を押したときに鈍い痛みが出やすいようです。一方、頭皮の炎症や神経の圧迫があると、ピリッと鋭い痛みを感じることもあります(引用元:Rehasaku)。
痛みの性質・タイミングをチェック
痛みの出方にも特徴があります。チクチク、ズキズキ、重たいような鈍痛など、感じ方を言葉にしてみると、自分の状態が整理しやすくなります。たとえば「朝起きた時だけ痛い」「長時間スマホを見たあとに痛む」など、タイミングや誘因がはっきりしている場合は、姿勢や筋緊張との関連が指摘されています。また、髪をとかすときや洗髪時に痛むなら、頭皮や神経への刺激が関わっていることもあるようです(引用元:Medical DOC、浦安柳整骨院)。
併発する症状にも注目を
もし、しびれや吐き気、発熱、視覚異常などを伴う場合は、単なる筋肉の張りではなく、神経や血流のトラブルが背景にあるケースもあると言われています。痛みの強さよりも「どんな症状と一緒に出ているか」を見ることで、危険サインを早めに察知できる可能性があります。
自分の痛みタイプを見分ける導線づくり
「押すと痛い」感覚は、筋肉・神経・頭皮など複数の要素が絡みやすいため、一つずつ整理するのがポイントです。どの動作で痛むのか、どのくらい続くのかをメモしておくと、今後の改善のヒントになります。この段階で原因を完璧に特定することは難しいですが、特徴を把握することで「どのようなケアをすれば良いか」が見えやすくなるでしょう。
#後頭部痛 #首こり #神経痛 #セルフチェック #姿勢改善
考えられる主な原因
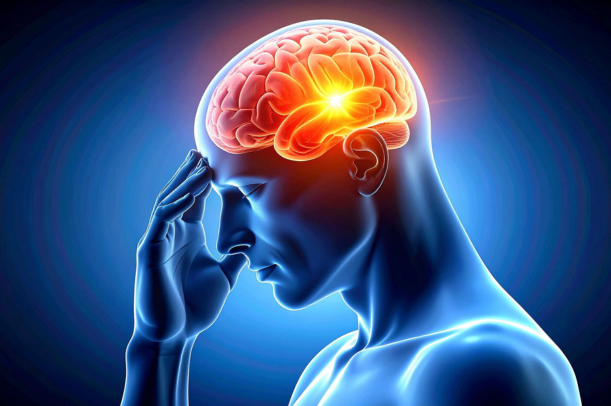
1. 筋肉・コリ・筋膜性の原因
首や肩のこりによって、後頭部を押すと痛みを感じるケースが多いと言われています。特に、僧帽筋や肩甲挙筋といった筋肉が硬くなると、筋膜を通じて痛みが広がることがあります。長時間のデスクワークやスマホ姿勢などで血流が悪くなると、筋肉が緊張しやすくなるのです。押すと鈍い痛みが出る場合は、筋膜の張りが影響していることが多いとも言われています(引用元:有限会社かおり&やすらぎ、リハサク)。
2. 後頭神経痛(大後頭神経・小後頭神経の圧迫)
「ピリッ」「ズキッ」と電気が走るような痛みが特徴とされるのが後頭神経痛です。神経が筋肉や周囲の組織に圧迫されると、後頭部を押したときに強い痛みが出ることがあるようです。首こりやストレス、枕の高さの不適合が関係するとも報告されています。皮膚表面がヒリヒリしたり、洗髪時に刺激を感じやすいのも特徴です(引用元:スカルプD ブランドサイト、いしざき脳神経内科)。
3. 頚椎や神経圧迫による関連痛
加齢や姿勢の崩れで頚椎が変形し、神経を圧迫して後頭部に痛みが出るケースもあると言われています。首を後ろに反らせたときに痛みが強くなる場合は、神経や椎間板の関与が疑われます。慢性的な痛みや手のしびれを伴うこともあるため、注意が必要です。
4. 皮膚・頭皮の炎症やできもの
頭皮の炎症、毛嚢炎、帯状疱疹、しこりなどが原因で「押すと痛い」症状が出る場合もあります。頭皮の乾燥やシャンプー刺激、紫外線などが悪化要因になることもあるようです。かゆみや赤みを伴う場合は、皮膚のトラブルを疑うと良いかもしれません(引用元:メディカルドック、スカルプD ブランドサイト)。
5. 血管性・重篤疾患の可能性
くも膜下出血や椎骨動脈解離など、血管系の病気が原因で後頭部に痛みを感じる場合もあります。突然の激しい痛みや吐き気、視覚異常を伴うときは、神経や脳への血流障害が関係していることがあると言われています。この場合は、自己判断せず専門機関への相談が推奨されています(引用元:横濱もえぎ野クリニック、yaesu-noushinkeigeka.jp)。
6. その他の刺激・生活要因
頭皮の乾燥、紫外線、強いマッサージ、過度な整髪料なども「押すと痛い」感覚を引き起こすことがあります。外的刺激を減らし、頭皮環境を整えることが回復の一助になると言われています(引用元:イシャチョク、スカルプD ブランドサイト)。
#後頭部痛 #神経痛 #首こり #頭皮ケア #生活習慣
症状別セルフチェック法・リスク判断フロー

自分の痛みタイプを整理してみよう
「後頭部を押すと痛い」と感じたとき、まず意識したいのは痛み方の特徴です。短時間で鋭く「ピリッ」とくるなら神経の過敏や圧迫が関係していると言われています。一方で、広い範囲が重だるく痛む場合は、首こりや筋膜の張りが原因であることが多いようです。自分の痛みが“ズキズキ型”か“ジワジワ型”かを整理するだけでも、原因の方向性がつかみやすくなります(引用元:リハサク、有限会社かおり&やすらぎ)。
押したときの反応・拡がり方を観察
実際に軽く押してみると、痛みがその場で感じるのか、周囲に広がるのかで特徴が変わります。たとえば、指で押したときに痛みが首筋やこめかみ方向へ拡がるなら、筋膜性の影響が考えられると言われています。反対に「一点だけがズキッと痛い」「触るだけでビリビリする」場合は神経性の要素が強いこともあります。強く押すと悪化するケースもあるため、やりすぎには注意が必要です。
併発症状をチェックしてみる
痛み以外のサインも重要です。たとえば、発熱・体重減少・しびれ・視覚異常などが同時にある場合は、体の内部で別の変化が起きていることもあると言われています。特に、吐き気やふらつきを伴うようなときは、脳や血流の異常が関係しているケースも否定できません(引用元:横濱もえぎ野クリニック、メディカルドック)。
医療機関に相談すべき“赤旗サイン”
以下のような症状がある場合は、できるだけ早く専門家への相談がすすめられています。
- 痛みが急に強くなった、または今までと違う感覚がある
- 手足のしびれや麻痺が出ている
- 頭痛とともに吐き気や意識のぼやけがある
- 視界がかすむ、物が二重に見える
- 安静にしても改善せず、日常生活に支障がある
これらは一時的なこりではなく、神経や血管の異常が関係していることもあるため、無理に我慢せず医療機関へ相談することが大切だと言われています。
#後頭部痛 #セルフチェック #神経痛 #首こり #赤旗症状
自宅でできる対処法・ケア(原因別)

筋肉やコリが原因の場合
首や肩のこりによる後頭部の痛みには、まず「温める」ことが有効だと言われています。温タオルや温湿布を使うと、筋肉がほぐれやすくなり、血流も改善しやすくなるようです。軽いストレッチや首回りの体操も、固まった筋肉をやわらげる助けになります。ただし、強く押したり無理に動かすと、逆に筋膜を痛めることもあるので注意が必要です。日常的に姿勢を整えることも大切で、特にスマホを長時間見下ろす姿勢は避けるよう心がけましょう(引用元:リハサク、有限会社かおり&やすらぎ)。
神経痛が関係している場合
後頭神経痛など神経の圧迫や過敏が背景にあるときは、まず安静をとることがすすめられています。枕の高さを調整し、首の角度に負担をかけないようにすると良いと言われています。軽い神経ストレッチやリラックスできる深呼吸も有効とされますが、刺激を与えすぎると悪化することもあるため、痛みが強いときは無理をしないようにしましょう(引用元:いしざき脳神経内科、スカルプDブランドサイト)。
頭皮・皮膚トラブルが原因のとき
頭皮の炎症やできものによって押すと痛い場合は、皮膚を清潔に保ち、保湿を意識すると良いと言われています。低刺激のシャンプーを選び、熱すぎるお湯で洗わないように注意が必要です。抗炎症ケアとして、皮膚科専用のスカルプケア用品を使用するのも一つの方法です。かゆみや赤みが続く場合は、自己判断せず医療機関への相談がすすめられています(引用元:メディカルドック、駅前AGAクリニック)。
生活習慣を見直すポイント
睡眠不足やストレス、長時間同じ姿勢を続けることも、痛みを悪化させる要因になるようです。1時間ごとに姿勢を変える、首を軽く回すなどのリフレッシュ習慣を取り入れるとよいでしょう。また、枕の高さや硬さを調整するだけでも、首への負担が減る場合があると言われています。
自己流ケアの落とし穴
つい「マッサージで強く押せばスッキリする」と思いがちですが、痛みを感じるほどの刺激は逆効果になることがあります。押すと痛いときほど“やさしいケア”を意識して行うことが大切です。
#後頭部痛 #首こり #神経痛 #ストレッチ #生活習慣改善
受診の目安と医療対応、診療科の選び方

すぐ来院を検討すべきサイン
後頭部の痛みが急に強くなったり、いつもと違う種類の痛みを感じる場合は注意が必要だと言われています。特に、手足のしびれや麻痺、視覚の異常、発熱や吐き気を伴うときは、脳や神経系のトラブルが関係していることもあるようです。これらはいわゆる“赤旗症状”と呼ばれるサインで、できるだけ早めの来院がすすめられています。急な痛みや違和感があるときは無理せず、体の声を聞くことが大切です(引用元:横濱もえぎ野クリニック、リハサク)。
相談すべき診療科の目安
痛みの原因によって、相談先が異なる場合があります。筋肉や骨の問題が考えられるなら整形外科、神経に関する痛みやしびれがある場合は神経内科、頭の中での血流異常などが疑われるときは脳神経外科が推奨されています。また、皮膚や頭皮の炎症が関係するようなら皮膚科での相談が適しています。複数の症状があるときは、まず総合的に判断できる整形外科や脳神経内科を訪ねるのも一つの方法です。
医療機関で行われる検査の流れ
来院後は、問診や触診を行い、必要に応じて画像検査を実施することが多いようです。たとえば、骨や関節の状態を確認するためのレントゲン、神経や血管の圧迫を調べるMRI、脳の異常を調べるCTなどが代表的です。神経の働きを確認するために、神経伝導検査を行うこともあります。これらの検査結果をもとに、痛みの原因や範囲を特定していく流れが一般的だと言われています(引用元:いしざき脳神経内科、メディカルドック)。
検査・施術と今後のケア
医師がとる対応としては、痛みをやわらげる薬の処方、神経ブロック注射、理学療法、リハビリなどが挙げられます。原因によっては、手術による神経や血管の圧迫解除を検討することもあるようです。ただし、ほとんどのケースでは保存的なケアで改善することが多いとも言われています。痛みが落ち着いた後も、姿勢改善やストレッチを習慣づけることで再発予防につながります。
日常での再発予防と注意点
再び痛みを感じないためには、長時間のうつむき姿勢を避け、適度に首を動かすことが大切です。枕の高さやデスク環境を見直すだけでも、後頭部への負担を減らせると言われています。
#後頭部痛 #脳神経外科 #首こり #神経痛 #赤旗症状