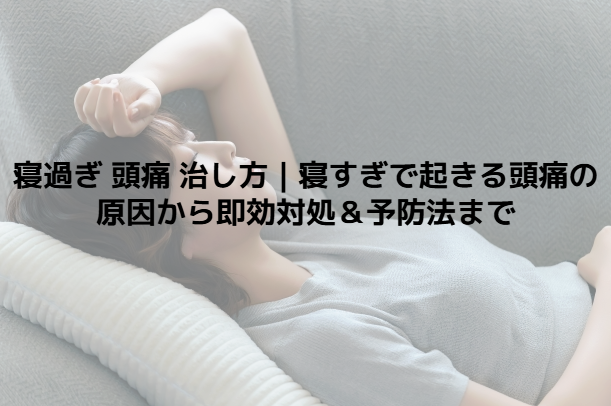寝過ぎで頭痛が起こる仕組み

「せっかくの休日だから」と長く寝たのに、起きたら頭がズキズキ……。そんな経験、ありますよね。実はこの“寝過ぎ頭痛”、医学的にも理由があると言われています。
血管の拡張による「片頭痛タイプ」
長時間眠ることで、脳の血管がゆるみ、血流がゆっくりになり過ぎてしまうことがあります。起きた瞬間に血管が急に広がったり縮んだりすると、その変化が周囲の神経を刺激して痛みを感じやすくなると考えられています。こうした反応は「寝過ぎによる片頭痛」と呼ばれ、休日明けなどに多いと言われています。
また、副交感神経が優位になり過ぎることで血管が拡張し、ズキズキする頭痛につながることもあるそうです。
引用元:https://nishikawa1566.com/column/sleep/20191018105911
引用元:https://oshimizu-clinic.com/2023/11/28/nesugi
引用元:https://shopjapan.co.jp/good-sleep-labo/article/030
筋肉のこわばりによる「緊張型頭痛タイプ」
一方で、長時間同じ姿勢で眠ると、首や肩の筋肉がこわばって血行が悪くなり、頭を締めつけるような痛みを感じる場合があります。これは「緊張型頭痛」と呼ばれるもので、寝具が合っていなかったり、枕の高さが合わなかったりしても起こることがあるそうです。
このタイプの人は、朝起きた瞬間よりも、少し時間が経ってから「重だるい」「頭が締めつけられる」と感じやすいと言われています。
引用元:https://interior.francebed.co.jp/nemurinavi/column/Headache_oversleeping
引用元:https://oshimizu-clinic.com/2023/11/28/nesugi
睡眠リズムの乱れが引き金になることも
もうひとつ見逃せないのが、体内時計の乱れです。普段よりも長く寝ると、脳が「まだ夜だ」と錯覚して自律神経のバランスを崩し、頭痛を感じやすくなることがあると言われています。
つまり、寝不足も寝過ぎも、どちらも頭痛の引き金になりやすいということです。適切な睡眠時間を保ち、寝る時間・起きる時間を一定にすることが大切だとされています。
引用元:https://nemurinomikata.com/%E5%AF%9D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%AF%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%81%AB%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F%E5%AF%9D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B%E3%81%A8%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%90%86
まとめ:寝過ぎ頭痛は“体のサイン”かもしれない
寝過ぎた翌日の頭痛は、「よく休めた証拠」ではなく、血流や筋肉の緊張、あるいは自律神経の乱れが原因になっている可能性があると言われています。
まずは自分の頭痛がどちらのタイプなのかを把握し、体が発しているサインを無視しないことが大切です。
#寝過ぎ頭痛 #片頭痛 #緊張型頭痛 #睡眠リズム #自律神経
寝過ぎ頭痛のタイプ別症状と見分け方

「寝すぎたあとに頭が痛い」と言っても、実は人によって原因も痛み方も少しずつ違います。大きく分けると、片頭痛タイプと緊張型頭痛タイプの2種類があると言われています。ここでは、それぞれの特徴と見分け方を紹介します。
ズキズキする「片頭痛タイプ」
片頭痛タイプは、主に血管の拡張が関係していると考えられています。長く眠って血流がゆるみ、起きたときに急に血管が広がることで、神経が刺激を受けて痛みを感じる仕組みです。
痛み方は「ズキズキ」「ドクドク」と脈打つように感じることが多く、頭の片側だけに起こる場合もあります。人によっては、光や音に敏感になったり、吐き気を感じたりすることもあるそうです。
会話で言えば、「頭がドクドクして目を開けるのもつらい」といった状態が近いかもしれません。
引用元:https://nishikawa1566.com/column/sleep/20191018105911
引用元:https://brain-sleep.com/blogs/magazine/sleep-headache
引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_head/sy0371
重だるい「緊張型頭痛タイプ」
一方、緊張型頭痛タイプは、首や肩の筋肉がこわばって血行が悪くなり、頭全体が締めつけられるように感じるケースが多いと言われています。長時間同じ姿勢で寝たり、枕が高すぎたりすると起こりやすいタイプです。
痛みは「ズキズキ」ではなく、「じわーっと重い」「後頭部がぎゅっとする」といった感覚。首や肩こりを伴う人も多く、起きてから時間が経つほど重だるくなることもあります。
「寝たのに疲れが取れない」「肩がガチガチで頭が痛い」と感じたら、このタイプの可能性が高いとされています。
引用元:https://interior.francebed.co.jp/nemurinavi/column/Headache_oversleeping
引用元:https://oshimizu-clinic.com/2023/11/28/nesugi
自分の頭痛タイプを見分けるポイント
どちらのタイプか見分けるには、痛み方や部位だけでなく、起きた時間帯や生活リズムにも注目してみてください。
・ズキズキして光や音に敏感 → 片頭痛タイプの可能性
・締めつけられるようで首肩のコリを感じる → 緊張型タイプの可能性
・寝る時間がバラバラ・長時間寝る休日に起こりやすい → どちらも起きやすい環境
どちらのタイプも、体が出している「ちょっと休みすぎかも」というサインかもしれません。痛みが頻繁に出る場合は、生活リズムや寝具の環境を一度見直してみることがすすめられています。
引用元:https://cliniciwata.com/2024/10/07/4816
#寝過ぎ頭痛 #片頭痛タイプ #緊張型頭痛 #頭痛の見分け方 #睡眠リズム
今すぐできる治し方・対処法

「寝すぎて頭が痛い…」そんなとき、どうすれば少しでもラクになれるのでしょうか。
頭痛のタイプによって対処の方向性が異なると言われています。ここでは、片頭痛タイプと緊張型頭痛タイプに分けて、すぐに試せる対処法を紹介します。
ズキズキ痛むときは「冷やして休む」
片頭痛タイプの場合は、血管が拡張して神経が刺激されている可能性があります。そのため、冷やすことで血管を落ち着かせると良いと言われています。
たとえば、保冷剤をタオルで包んで首の後ろ(盆の窪あたり)やこめかみに軽く当ててみてください。暗く静かな部屋で、光や音を避けながら深呼吸をするのも効果的とされています。
カフェインを少量摂る(コーヒーや緑茶など)と、血管の広がりを抑える作用が期待できることもあるようです。ただし、飲み過ぎは逆効果になる場合もあります。
引用元:https://medicalook.jp/over-sleeping-headache
引用元:https://nishikawa1566.com/column/sleep/20191018105911
引用元:https://oshimizu-clinic.com/2023/11/28/nesugi
重だるい痛みには「温めてほぐす」
一方で、緊張型頭痛タイプは、首や肩の筋肉がこわばって血行が悪くなっていることが多いと言われています。そんなときは、温めて血流を促すことがポイントです。
蒸しタオルを首の後ろに当てたり、ぬるめのお湯でゆっくり入浴したりするのもおすすめです。肩まわりを軽く回したり、深呼吸を繰り返すだけでも少し楽になることがあります。
また、デスクワークが続く人は、寝具や枕の高さも見直してみるといいでしょう。体に合っていない寝姿勢が続くと、翌朝の頭痛につながる場合があります。
引用元:https://interior.francebed.co.jp/nemurinavi/column/Headache_oversleeping
引用元:https://ouchi-de-08.jp/column/other/column250110
共通して気をつけたいポイント
どちらのタイプでも、まずは「無理をしない」ことが大切です。寝すぎ頭痛は、体が「もう十分休んだよ」と伝えているサインとも言われています。
もし、頭痛が何日も続く、吐き気やめまいを伴う、片側だけが強く痛むなどの症状がある場合は、自己判断せず専門家による触診や検査を受けたほうが安心です。
また、睡眠のリズムを整えたり、寝る前のスマホ使用を控えたりといった日常の工夫も、再発防止につながると考えられています。
引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_head/sy0371
#寝過ぎ頭痛 #頭痛対処法 #片頭痛ケア #緊張型頭痛 #セルフケア
再発を防ぐための予防・生活習慣の見直し

「寝過ぎて頭痛になるのはイヤだから、次は気をつけたい」――そう感じた方も多いかもしれません。
寝過ぎ頭痛は、一度おさまっても生活習慣が変わらなければ再発しやすいと言われています。ここでは、日常の中でできる予防ポイントを整理してみましょう。
睡眠時間の“ちょうどよさ”を意識する
まず意識したいのは、睡眠時間のバランスです。
一般的に成人の理想的な睡眠時間は7〜9時間程度とされていますが、それを大きく超えると、かえって体がだるくなったり頭痛を招くことがあると言われています。
「昨日寝不足だったから今日は12時間寝よう」といった“寝だめ”は、体内時計を乱してしまう原因になるそうです。
平日と休日で就寝・起床のリズムを大きく変えないようにすることが、頭痛予防の第一歩になります。
引用元:https://shimbashiclinic.jp/column/1725
引用元:https://nishikawa1566.com/column/sleep/20191018105911
昼寝や休憩のとり方を工夫する
昼寝はリフレッシュになりますが、長すぎると逆効果になることもあります。
15〜30分ほどを目安に、15時前までに済ませると夜の睡眠に影響しにくいと言われています。
ソファで軽く目を閉じる程度でも十分。短い昼寝をうまく取り入れることで、体のリズムが整いやすくなるようです。
引用元:https://nemurinomikata.com/%E5%AF%9D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%AF%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%81%AB%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F%E5%AF%9D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B%E3%81%A8%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%90%86
寝具と寝る環境を整える
寝具や枕の高さが合っていないと、首や肩の筋肉が緊張して血流が悪くなり、翌朝の頭痛につながることがあると言われています。
また、室温・湿度・照明の明るさも重要です。寝室を少し暗めにして、スマホの光を避けるだけでも、睡眠の質が変わることがあります。
カフェインやアルコールの摂取は寝付きや睡眠の深さに影響するため、寝る数時間前から控えるのが良いとされています。
引用元:https://bufferin.net/navi/head/type06
適度な運動とストレスケア
軽いストレッチやウォーキングなどで体を動かすと、血流がよくなり、自律神経のバランスも整いやすくなると言われています。
特に、寝る前の深呼吸やストレッチは、緊張型頭痛の予防にも効果的だと考えられています。
仕事や日常のストレスを溜め込みすぎないようにすることも、睡眠の質を守るためには大切です。
まとめ:生活リズムを整えることが最大の予防策
寝過ぎ頭痛を防ぐには、「しっかり寝る」よりも「ちょうどよく寝る」ことがポイントです。
決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。それだけでも、体のリズムが整い、頭痛が起こりにくくなると考えられています。
一日の中で、自分の体に耳を傾ける時間を少し作ることが、最もシンプルで効果的な予防法かもしれません。
#寝過ぎ頭痛 #頭痛予防 #生活習慣改善 #睡眠リズム #ストレスケア
こんなときは要注意・病院に相談すべきタイミング&まとめ

「寝過ぎただけだと思っていたのに、なかなか頭痛がおさまらない…」
そんなときは、単なる寝過ぎ頭痛ではない可能性もあると言われています。
ここでは、注意しておきたい症状と、医療機関に相談する目安を紹介します。
長引く・強い痛みは放置しないで
寝過ぎ頭痛は、多くの場合が一時的ですが、痛みが何日も続くようなら注意が必要です。
特に、「朝起きるたびに痛む」「吐き気やめまいを伴う」「視界がぼやける」「片側だけ強く痛む」といった場合は、頭の中の血流や神経に異常があるケースもあるとされています。
こうした症状が頻繁に起こるときは、自己判断せずに医療機関へ相談することがすすめられています。
引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_head/sy0371
引用元:https://oshimizu-clinic.com/2023/11/28/nesugi
相談するならどんなところ?
寝過ぎ頭痛が何度も起こる、または痛みが強い場合は、脳神経内科や頭痛外来での検査が推奨されています。
実際に、頭痛のタイプを見分けるためには、問診や触診を通して血管や筋肉の状態を確認することが大切だと言われています。
また、睡眠リズムや生活習慣が関係しているケースでは、整骨院や整体などで姿勢・筋肉バランスを整える施術を受けることで、再発を防ぐサポートにつながる場合もあります。
引用元:https://cliniciwata.com/2024/10/07/4816
引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_head/sy0371
日常で意識したいチェックポイント
再発を防ぐためには、普段の生活を少し見直すだけでも変化が出やすいとされています。
・寝る時間と起きる時間を一定に保つ
・寝具や枕の高さを体に合わせる
・ストレッチや深呼吸で筋肉をほぐす
・寝すぎた翌日は軽めの運動でリズムを戻す
・「疲れている=長く寝る」ではなく「質を高める」睡眠を意識する
これらを続けていくことで、頭痛の再発リスクを減らせると考えられています。
「寝過ぎ頭痛」は一見ささいに思えますが、体のリズムが乱れているサインでもあります。
無理に我慢せず、体が出している信号を見逃さないようにしたいですね。
まとめ
寝過ぎによる頭痛は、血管や筋肉、自律神経のバランスが崩れることで起こるとされています。
その日の体調や生活リズムに合わせて睡眠をコントロールすることが、最大の予防策です。
もし症状が長引く場合は、専門家に相談することをためらわないでください。
体を整えることで、翌朝の目覚めもきっと軽くなるはずです。
#寝過ぎ頭痛 #頭痛外来 #片頭痛注意 #生活リズム改善 #体のサイン