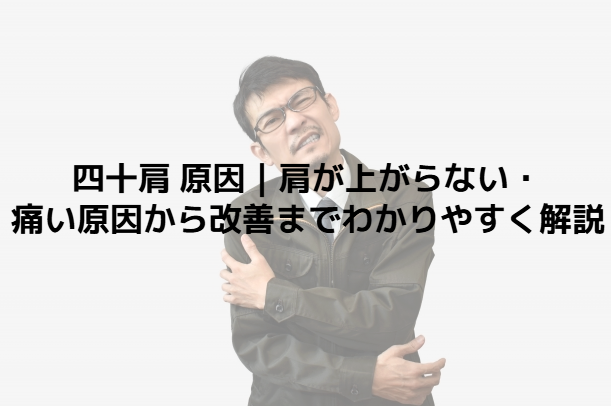四十肩とは?まず“原因”を知る前の基礎知識

「肩がいつの間にか上がらない」「腕を後ろに回せない…」そんな症状を感じたことがありませんか?それがいわゆる “ 四十肩 ” というものかもしれません。専門的には “ 肩関節周囲炎 ” と呼ばれることが多く、40代〜50代の方に比較的発症しやすい症状だと言われています。引用元: https://turn0search10
ここでは、四十肩の基礎的な知識を、会話形式で、わかりやすくお伝えします。
四十肩って“どんな状態”?
「それってただの肩こりじゃないの?」と感じる方も多いでしょう。四十肩は、肩関節を取りまく腱板(けんばん)、関節包、滑液包といった組織に炎症や変化が起こることで、肩の動きが制限されたり、痛みが出たりする状態と言われています。引用元: https://turn0search2
腕を上げる・後ろへ回す・寝返りを打つときなど、普段何気なく使っていた肩の動きが「なんか重い」「痛い」などと感じたら、それが最初のサインかもしれません。
なぜ“四十肩”というの?
名前の由来は、40〜50歳代に多く見られたことからと言われています。50代に多発したことから「五十肩」とも呼ばれてきましたが、近年では40代でも起こるため、四十肩という言い方も広まっています。引用元: https://turn0search16
ただ、年齢だけが原因ではなく、使い過ぎ・姿勢の悪さ・血流の低下など、複数の要因が“肩関節周囲炎”という状態を引き起こすと考えられています。引用元: https://turn0search0
放っておいて大丈夫?
「放っておけばそのうち治る」と思われることもありますが、必ずしもそうとは言えないと言われています。引用元: https://turn0search8
そのまま肩をあまり動かさずにいると、関節包などが硬くなってしまい、「肩が固まる」つまり動かせる範囲がさらに狭くなる拘縮(こうしゅく)状態に進行することもあるのです。こうなると、痛みだけでなく日常動作にも支障が出やすくなります。
何を知っておけばいい?
まずは「肩が思うように動かせない」「痛みが出る」「夜、肩がズキズキする」といった“症状のサイン”を知っておくことが大切です。
そして、次のステップとして「なぜこういう状態になるのか?」を理解しておくことで、自分でできる予防・ケアについて考えやすくなります。この記事では、そのための“原因の視点”にも触れていきますので、ぜひ次の項目もご覧ください。
#四十肩 #五十肩 #肩関節周囲炎 #肩の痛み #肩の可動域制限
四十肩の原因:肩に何が起きているのかを理解する

「なぜ四十肩になるの?」——そう思ったことはありませんか?
実は、明確な原因がひとつに特定されているわけではなく、いくつかの要因が重なって起こる“複合的な状態”だと言われています。ここでは、医学的な観点から考えられている主な原因を、日常生活の例を交えながら紹介します。
加齢による肩関節の変化
四十肩の最も一般的な要因は、加齢による筋肉・腱・関節包などの変性です。
40〜50代になると、肩の動きを支える「腱板」や「関節包」が少しずつ硬くなり、血流が悪くなる傾向があると言われています。引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/shoulder/
この硬さが続くと、肩を動かしたときに炎症が起きやすくなり、痛みや可動域の制限につながります。つまり「老化」そのものが原因というよりも、「回復しにくくなる体の変化」がベースにあるのです。
姿勢の悪さや肩の使い過ぎ
デスクワークやスマホ操作で猫背姿勢が続くと、肩の位置が前に出てしまい、肩甲骨の動きが悪くなります。
この状態では、肩関節周囲の筋肉に常に負担がかかり、炎症が起きやすくなると言われています。引用元:https://taisho-kenko.com/disease/615/
また、家事や育児、運動で同じ動きを繰り返すことも、肩へのストレスを増やす原因になります。特に「腕を上げる」「後ろに回す」動作が多い人ほど、炎症を起こしやすい傾向があるそうです。
血行不良と冷え
意外かもしれませんが、「冷え」や「血行不良」も四十肩の原因のひとつと考えられています。
血流が悪くなると、筋肉や腱の修復に必要な酸素・栄養が届きにくくなり、肩関節周囲の組織が硬くなってしまうからです。
冬場や冷房の効いた室内で長時間過ごす方は、肩を冷やさないよう意識するだけでも予防につながると言われています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-406/
生活習慣や基礎疾患も関係している?
糖尿病や甲状腺の病気を持つ人は、四十肩を発症しやすい傾向があるという報告もあります。
これらの疾患では、血管や組織の代謝が低下しやすく、炎症が起こりやすいと考えられています。
また、運動不足や睡眠の質の低下など、生活リズムの乱れも関節機能に影響を与える可能性があるそうです。
まとめ:四十肩の原因は「ひとつではない」
つまり、四十肩は「年齢のせい」だけでなく、姿勢や生活習慣、体の使い方、血流の状態など、いくつもの要因が重なって起こるものだと言われています。
「最近肩が動かしづらい」「ちょっと痛む」——そんなサインを感じたら、まずは日常生活の中でどんな姿勢を取っているか、どんな動きを繰り返しているかを見直すことが、改善への第一歩になるかもしれません。
#四十肩 #原因 #肩関節周囲炎 #姿勢不良 #血行不良
典型的な症状と進行の段階:こういう時は四十肩を疑おう

「最近、上の棚の物が取れない」「腕を後ろに回すとズキッと痛む」――そんな経験はありませんか?
それ、もしかすると“肩こり”ではなく“四十肩”の始まりかもしれません。四十肩には、特徴的な症状と、ある一定の進行パターンがあると言われています。ここでは、その代表的なサインと経過の流れを整理してみましょう。
肩が「上がらない」「回せない」違和感から始まる
最初の段階では、「ちょっと肩が重い」「動かすと痛い」といった軽い違和感から始まることが多いです。
特に、髪を結ぶ・服を脱ぐ・背中に手を回すといった動作のときに、痛みを感じやすいのが特徴です。引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/shoulder/
また、夜間にズキズキと痛む「夜間痛」も四十肩に多く見られる症状のひとつと言われています。寝返りを打ったときに痛みで目が覚めてしまう、というケースも少なくありません。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-406/
痛みの段階ごとの変化
四十肩は、「炎症期」「拘縮期(こうしゅくき)」「回復期」という3つの段階で進行することが多いとされています。引用元:https://taisho-kenko.com/disease/615/
- 炎症期(発症初期)
肩関節の中で炎症が起こり、動かすたびに痛みが強く出る時期です。
この時期は、無理に動かさず、安静と冷却が大切だと言われています。 - 拘縮期(肩が固まる時期)
痛みはやや落ち着きますが、関節包が硬くなり、腕の可動域が制限されていく時期です。
「腕が上がらない」「背中に手が届かない」など、日常生活で支障が出やすくなります。 - 回復期(動きが戻る時期)
時間の経過とともに、炎症が収まり、少しずつ動かせるようになる段階です。
ストレッチや軽い運動を取り入れることで、スムーズな改善が期待できると言われています。
日常生活で見られるサイン
「肩を上げると痛い」「腕を回すと引っかかる感じがする」「夜になると痛みが強くなる」――これらは四十肩の代表的なサインです。
また、「痛みが片側だけ」「左右差が大きい」「冷えると痛みが強まる」といった特徴も見られることがあります。
放置していると、関節が固まり“凍ったように動かせない”状態(フローズンショルダー)へ進行することもあるため、早めのケアがすすめられています。引用元:https://keisuikai.or.jp/patient/%E4%BA%94%E5%8D%81%E8%82%A9
まとめ:四十肩の進行は「痛み→固まる→動く」
四十肩は、痛みが出てからすぐに肩が上がらなくなるわけではなく、徐々に「痛み→拘縮→回復」と移り変わる経過をたどることが多いようです。
この段階を理解しておくことで、どの時期にどんな対策をすればいいのかを判断しやすくなります。
「ただの肩こりかも」と見過ごさず、違和感を感じた段階で早めに体をいたわることが、悪化を防ぐ第一歩です。
#四十肩 #肩が上がらない #夜間痛 #拘縮期 #肩の可動域
原因に応じた初期の対策と日常ケアのポイント

「四十肩になったら、どうすればいいの?」
そう感じたとき、焦って肩を動かしすぎたり、逆に何もしないまま放っておく人も多いかもしれません。
でも実は、四十肩には“時期に合った対策”があると言われています。ここでは、原因に応じた初期ケアと、日常生活で意識したいポイントを紹介します。
炎症期は「無理をしない・冷やす・支える」が基本
発症初期の炎症期では、肩関節の中で炎症が起きているため、無理に動かすと悪化することがあります。
まずは痛みを和らげることを優先し、安静を保ちましょう。
氷や冷却パックをタオルで包み、肩に10〜15分ほど当てて冷やすと、炎症の拡大を抑える効果があると言われています。引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/shoulder/
また、腕の重みで肩が引っ張られるのを防ぐため、スリングや三角巾などで腕を支えるのも有効です。
痛みが強いときは、無理をせず休むことが、結果的に早い改善につながります。
痛みが落ち着いてきたら「ゆるやかに動かす」
炎症が落ち着き始めたら、今度は「動かすこと」を少しずつ取り入れていきましょう。
いきなり大きく動かすのではなく、まずは肩を回す・腕を前後にゆっくり振るなど、小さな動きから始めるのがポイントです。
「痛気持ちいい」くらいの範囲で留め、無理に引っ張らないよう注意してください。引用元:https://taisho-kenko.com/disease/615/
この時期は、可動域を保つことが目的なので、動かすこと自体よりも“継続して行うこと”が大切だと言われています。
姿勢と生活動作の見直しも忘れずに
肩の動きを制限しているのは、肩そのものだけでなく「姿勢」も大きく関係しています。
長時間のデスクワークや猫背姿勢が続くと、肩甲骨が前に引っ張られ、肩関節に余分なストレスがかかります。
背筋を伸ばし、椅子に深く座る、スマホを見るときは顔を近づけすぎない――こうした小さな習慣が肩の負担を軽くしてくれます。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-406/
また、日常動作で「高い棚のものを取る」「重い荷物を持ち上げる」といった動きは、痛みが落ち着くまでは控えたほうが安心です。無理に使うと、せっかく治まりかけた炎症が再び悪化することもあると言われています。
睡眠中の姿勢にも注意
意外と見落とされがちなのが、寝るときの姿勢です。
痛い方の肩を下にして寝ると、体重が直接かかり、炎症を悪化させることがあります。
仰向けで寝る際は、痛い肩の下に薄めのタオルや枕を入れて少し支えると、肩の負担を軽減しやすくなります。
まとめ:焦らず「冷やす→休む→動かす→整える」
四十肩のケアは、“時期に合わせた行動”がとても大切です。
炎症期は「冷やす・休む」、拘縮期は「少しずつ動かす」、回復期は「姿勢を整える・肩を動かす」——この流れを意識しておくと、改善の道筋が見えやすくなります。
焦らず、自分のペースで肩と向き合うことが、回復への第一歩だと言われています。
#四十肩 #四十肩ケア #肩の痛み #姿勢改善 #冷却と安静
予防と再発防止:肩を強くする&固まらせないために

「やっと肩の痛みが落ち着いてきたのに、また痛くなった…」
そんな経験をする人は少なくありません。四十肩は、痛みが和らいでも関節や筋肉の柔軟性が十分に戻っていない場合、再発しやすい傾向があると言われています。
ここでは、日常でできる予防と再発防止のポイントを紹介します。
肩甲骨まわりを“動かす”習慣をつくる
四十肩の再発を防ぐには、肩関節だけでなく「肩甲骨を動かす」ことが大切です。
肩甲骨が硬くなると、腕の動きが制限されて再び炎症を起こしやすくなります。
おすすめなのは、タオルストレッチや肩回し運動です。
- 両手でタオルの端を持ち、頭の後ろへゆっくり引く
- 肩をすくめるように上げて、後ろへ回す
こうした動きは、関節の柔軟性を保ち、血流を促す効果があると言われています。引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/shoulder/
デスクワーク中も「小まめにリセット」
長時間パソコンに向かっていると、気づかないうちに肩が前に丸まり、肩甲骨が外側に広がります。
これを防ぐために、1時間に1回は肩を軽く動かしたり、背伸びをしたりするのがおすすめです。
また、デスクの高さや椅子の位置を調整し、肘が自然に曲がる姿勢を保つだけでも、肩の負担を減らせると言われています。引用元:https://taisho-kenko.com/disease/615/
冷え対策で筋肉の硬直を防ぐ
冷房の効いた部屋や寒い季節に肩を冷やすと、血流が悪化して筋肉が硬くなりやすくなります。
特に入浴を省略したり、シャワーだけで済ませる習慣がある人は注意が必要です。
湯船にゆっくり浸かって体を温めることで、肩まわりの筋肉が緩み、可動域を保ちやすくなると言われています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-406/
軽い運動を“継続”することが最大の予防
ストレッチや肩回しを一度に長くやるよりも、1日5分でも毎日続ける方が効果的だとされています。
「朝起きたら1分だけ肩を回す」「お風呂上がりにタオルを使って軽く伸ばす」など、生活の中に動きを取り入れていくのが理想的です。
運動不足が続くと筋肉の弾力が落ち、再び肩が固まりやすくなるため、継続的なケアが大切です。
まとめ:再発防止は“少しずつ、続けること”
四十肩の予防と再発防止には、特別なことをする必要はありません。
「冷やさない」「姿勢を整える」「肩を動かす」――この3つを意識するだけでも、肩の健康はぐっと保ちやすくなると言われています。
痛みがなくても、毎日ほんの少し肩を動かす習慣をつくる。それが、四十肩を遠ざけるいちばんの近道かもしれません。
#四十肩 #肩こり予防 #姿勢改善 #肩ストレッチ #再発防止