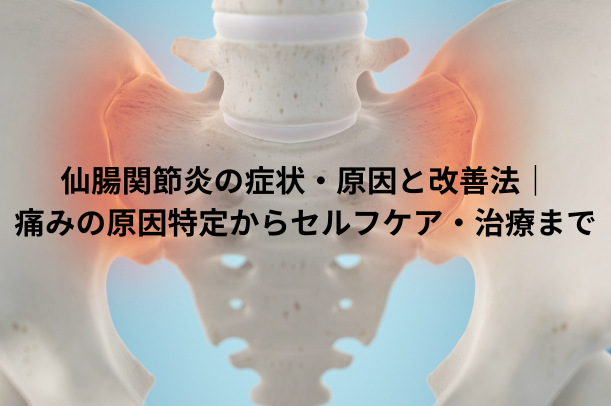1:仙腸関節炎とは何か・基本の知識

仙腸関節の構造と働き
「仙腸関節ってどこにあるの?」と患者さんからよく聞かれるのですが、骨盤の後ろ側で仙骨と腸骨をつなぐ関節を指すと言われています。左右に一つずつあり、強力な靱帯によって支えられているため、ほとんど動かない関節とも言われます。ただ完全に固定されているわけではなく、歩行や出産時などにわずかに動くことで衝撃を分散する働きを持つと考えられています(引用元: Medical Note)。
「炎症」「障害」と「ずれ」「機能異常」の違い
「仙腸関節炎」と呼ばれることもあれば「仙腸関節障害」と表現されることもあります。名前が違うと混乱しますが、基本的には同じ場所に起こる不具合を指していると言われています。炎症という言葉は関節内や周囲の組織が刺激を受けて痛みが出る場合を表し、障害や機能異常という表現は必ずしも炎症だけでなく関節の動きの不均衡や靱帯の緊張による不調も含むようです(引用元: かねしろ整形外科)。
発生メカニズム
どうして仙腸関節炎になるのか?この点もよく相談されます。大きくは、長時間の立ち仕事や中腰作業などで繰り返し負担がかかること、スポーツなどで腰や骨盤に強い衝撃が加わること、そして妊娠や出産によって靱帯が緩むことなどが要因と言われています。また交通事故や転倒といった外傷もきっかけになるケースがあると報告されています(引用元: 森本神経科クリニック)。
他の腰痛疾患との関係性
腰の痛みといえば椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症が有名ですが、仙腸関節炎も似たような症状を示すと言われています。そのため、画像検査でははっきりしないのに痛みが続くとき、仙腸関節の問題が隠れている場合もあるそうです。患者さん自身は「腰が痛い」と感じても、実は関節部が原因というケースが一定数あると言われています。この点が診断を難しくし、慢性的な腰痛の背景に仙腸関節炎が関わっている可能性が注目されています。
#仙腸関節炎
#腰痛の原因
#骨盤と仙骨
#妊娠出産と腰痛
#整形外科情報
2:典型的な症状と見分け方(症状の特徴・鑑別診断)

痛みの場所と出やすい場面
仙腸関節炎の特徴として、「腰というよりお尻のあたりがズーンと痛む」と話す方が多いと言われています。具体的には仙腸関節部や臀部、さらに鼠径部や太ももの後ろ、下肢にかけて違和感が広がるケースもあるそうです。
「座るとすぐ痛むんです」「寝返りのときにズキッとする」「歩き出す瞬間がつらい」など、生活のちょっとした動作で痛みが誘発されることが特徴として挙げられています(引用元:Medical Note)。
体の検査・徒手テスト
実際に医師や施術者が行う触診では、いくつかのテストを組み合わせると言われています。たとえば「One‐finger test」は、患者さんが痛みのある一点を指さすと仙腸関節部に集中するという特徴が見られるそうです。
また、骨盤を押し広げたり捻ったりして痛みを誘発する「Newton test」や、股関節を曲げて外に倒す「Patrick test」も参考になるとされています。さらに、PSIS(後上腸骨棘)の圧痛や靱帯部の押圧で痛みが出るかどうかを確認することで、仙腸関節由来の痛みを推定できると考えられています(引用元:かねしろ整形外科)。
画像検査の限界
「MRIやレントゲンを撮ったけど異常がないと言われました」と戸惑う方も少なくありません。仙腸関節炎は画像検査で明確に異常が映らないことが多いとされていて、見逃されやすい腰痛の一つだと紹介されています。そのため、症状や徒手テストを組み合わせて総合的に判断することが重要だと言われています(引用元:森本神経科クリニック)。
他疾患との鑑別
仙腸関節炎の厄介な点は、ほかの腰痛疾患と症状が重なるところにあります。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では坐骨神経痛のような下肢のしびれが出ることもありますし、股関節障害では鼠径部の痛みが強いケースがあるとされています。こうした疾患と区別するためには、丁寧な触診や複数の検査を組み合わせて慎重に確認する必要があると言われています。
#仙腸関節炎
#腰痛症状
#徒手テスト
#画像検査の限界
#腰痛鑑別
3:診断の流れと医療機関での検査・診断方法

問診で聞かれること
仙腸関節炎を疑って来院した場合、まずは問診が行われると言われています。
「いつから痛みが出たのか」「どの部位に痛みが集中しているのか」「座る・寝返り・歩行などで悪化するのか、あるいは和らぐ姿勢はあるのか」などが質問の中心になるそうです。患者さんが「ここが特に痛い」と指さした部位が仙腸関節に一致することも、重要な情報になると考えられています(引用元:Medical Note)。
徒手検査・動作テスト
問診のあとには、関節の状態を確認する徒手検査や動作テストが行われることが多いと言われます。代表的なものに「Patrick test」や「Newton test」があり、股関節や骨盤を動かした際の痛みの有無が確認されます。また、ワンフィンガーテストで患者さんが同じ一点を指差す場合、仙腸関節由来の痛みを示唆することがあるそうです。こうした検査は、画像に映らない原因を探る上で大切なヒントになると考えられています(引用元:かねしろ整形外科)。
仙腸関節ブロック注射の意義
画像や徒手検査だけでは判断が難しいとき、仙腸関節ブロック注射が使われることがあると言われています。これは局所麻酔を関節内に注入して痛みが軽減するかを確認する方法で、「本当に仙腸関節が原因かどうか」を見極める目的が大きいそうです。施術は整形外科やペインクリニックなどで行われることが多く、短時間で終わるケースが多いと紹介されています(引用元:森本神経科クリニック)。
専門医への紹介や追加検査
仙腸関節炎が疑われても、ほかの腰痛疾患と区別が必要な場合があります。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などとの鑑別が難しいときは、MRIやCTを追加することもあるそうです。また症状が強い場合や改善が見られない場合には、専門の整形外科や痛み外来に紹介される流れになると言われています。患者さんにとっては「自分の痛みの正体が何か」を知るために、複数の角度から確認していくことが大切だと考えられています。
#仙腸関節炎
#問診内容
#徒手検査
#ブロック注射
#専門医紹介
4:治療・改善法:保存療法からセルフケアまで

一般的な保存療法
仙腸関節炎と考えられる痛みがある場合、まずは保存療法から始めることが多いと言われています。一般的には痛み止め(NSAIDsなど)を用いた薬物療法、骨盤ベルトで関節を固定して安定させる方法、日常動作の指導などが取り入れられるそうです。「座るときに工夫すると楽になる」といった生活上のアドバイスも含まれることがあります(引用元:Medical Note)。
リハビリテーション・運動療法
「リハビリってどんなことをするんですか?」と患者さんから聞かれることもあります。リハビリでは体幹や股関節周囲の筋力強化、骨盤の可動域改善を目的とした運動療法が行われることがあると言われています。特にお尻や腰回りの筋肉を整えることで、仙腸関節への負担を減らせると考えられています。無理のない範囲で行うことで、日常生活が楽になるケースもあるそうです(引用元:かねしろ整形外科)。
セルフケアの工夫
自宅でできるセルフケアも取り入れるとよいとされています。例えばストレッチで股関節や腰回りをやさしく動かすこと、座り方や歩き方を見直すこと、荷物を片側だけで持たないように工夫することなどです。「こうした小さな習慣の積み重ねが、関節への負担軽減につながるのですね」と納得される方も多いようです(引用元:森本神経科クリニック)。
補助手段と理学療法
補助手段として温熱療法や冷却法、超音波などの物理療法が選択されることもあります。温めることで血流を促し、冷やすことで炎症を抑えるなど、状況に応じて使い分けることがあると言われています。理学療法士による施術も、患者さんの状態に合わせて行われるケースが紹介されています。
専門的治療・高難度治療
保存療法で改善が見られない場合には、ブロック注射や関節固定術といった専門的な方法が検討されることもあるそうです。こうした方法は整形外科や痛み外来などで行われることが多く、より強い症状に対応する手段として位置づけられています。すべての患者さんに必要というわけではなく、段階的に検討されるとされています。
#仙腸関節炎
#保存療法
#セルフケア
#リハビリ
#ブロック注射
5:予防と再発防止、長期にわたる痛みを防ぐための習慣

日常生活で気をつけること
仙腸関節炎を繰り返さないためには、普段の生活習慣を整えることが大切と言われています。姿勢が崩れると骨盤に負担がかかりやすいため、立つ・座る・歩くといった基本動作を意識することが重要だそうです。特に長時間同じ姿勢を避ける、体重管理を心がけるといった点も、関節へのストレス軽減につながると考えられています(引用元:Medical Note)。
運動・ストレッチルーティン
「何をしたら予防になりますか?」と質問を受けることも多いです。股関節や体幹を中心とした軽い運動が有効とされ、ストレッチで柔軟性を保つことが勧められています。具体的にはお尻の筋肉を伸ばすストレッチや、骨盤まわりを支える筋肉を鍛えるトレーニングが紹介されています。無理のない範囲で継続すると、再発を防ぐ助けになると言われています(引用元:かねしろ整形外科)。
痛みがぶり返した時の対応策
「良くなったと思ったらまた痛みが…」という声もあります。その場合はまず安静を意識し、負担をかけている動作を控えることが勧められています。痛みが強ければ冷却で炎症を抑えたり、温熱で血流を促したりといった方法を状況に応じて取り入れるとよいとされています。焦って無理をすると悪化につながるため、落ち着いた対応が大切だと言われています(引用元:森本神経科クリニック)。
医療機関に再び相談すべきタイミング
セルフケアを続けても痛みが長引く、しびれを伴う、歩行に支障が出るといった場合は、再度医療機関に相談することが望ましいとされています。仙腸関節炎だけでなく他の腰痛疾患が関わっている可能性もあるため、自己判断で放置せず専門家に触診や検査を依頼することが推奨されています。
#仙腸関節炎
#再発予防
#ストレッチ習慣
#生活改善
#相談の目安