シーバー病とは?成長期の子どもに多い「かかとの成長痛」

「運動のあと、子どもが『かかとが痛い』と言うようになった」──そんなときに考えられるのが、シーバー病(別名:セーバー病)です。
シーバー病とは、成長期の子ども、特にスポーツを頑張っている小学生から中学生に多く見られるかかとの成長痛の一種だと言われています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
シーバー病の特徴と発生しやすい年齢
シーバー病は、かかとの骨(踵骨)に炎症が起こることで痛みが出る状態を指します。
骨がまだ成長途中の時期は、筋肉や腱が引っ張る力に対して骨の一部が弱く、繰り返しのジャンプやダッシュでアキレス腱がかかとの骨を強く引っ張ることが原因の一つとされています。
特に、サッカーやバスケットボール、陸上競技などのように走る・跳ぶ動作の多いスポーツをする子どもに発症しやすい傾向があります。
男女ともに発症しますが、成長スピードの早い男子に多いと言われています。
どんな症状が出るのか?
シーバー病の主な症状は、かかとの痛みや違和感です。
最初は「走ると痛い」「ジャンプするとズキッとする」といった軽い痛みから始まり、進行すると歩くだけでも痛みを感じることもあります。
朝起きたときや練習のあとに痛みが強く出るケースも多く、「かかとを地面につけにくい」「つま先立ちで歩くようになる」と訴えるお子さんもいます。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sever_disease.html
痛みが一時的におさまっても、再び運動を始めるとぶり返すことがあるため、無理に練習を続けないことが大切だと言われています。
なぜ成長期に起こるのか?
成長期の子どもは、骨がまだ完成していないため、筋肉や腱とのバランスが崩れやすい時期です。
この時期は身長の伸びに筋肉が追いつかず、ふくらはぎの筋肉やアキレス腱が硬くなりやすいとされています。
その結果、運動のたびにかかとの骨に引っ張る力が加わり、微細な炎症を起こしてしまうという仕組みです。
また、成長期にありがちな「練習のしすぎ」「休息不足」「クッション性の低い靴」も発症のリスクを高める要因と考えられています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
親が気づくためのサイン
もし「片足だけをかばって歩く」「走るときにスピードが落ちる」「かかとを押さえると痛がる」といったサインが見られたら、シーバー病の可能性があります。
初期のうちに適切な対応を行うことで、改善までの期間を短縮できることがあると言われています。
#シーバー病 #かかとの痛み #成長期の子ども #スポーツ障害 #踵骨炎
シーバー病が起こる原因と悪化させる要因

シーバー病は、単なる「かかとの痛み」ではなく、成長期特有の体のバランスの崩れによって起こる炎症だと言われています。
特にスポーツをしている子どもでは、日々の練習や姿勢のクセが積み重なり、知らず知らずのうちにアキレス腱とかかとの骨の境目に負担が集中しているケースが多いようです。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
成長期の骨と筋肉のアンバランス
シーバー病が発症しやすいのは、10〜13歳前後の成長期です。
この時期は骨の成長が急激で、筋肉や腱の柔軟性が追いつかないことがあります。
その結果、アキレス腱が硬くなり、かかとの骨(踵骨)に強い牽引力がかかるようになるのです。
これが繰り返されることで、骨の付着部に炎症が生じ、痛みを感じるようになると言われています。
「体が硬い」「ストレッチを嫌がる」タイプの子どもほど、筋肉の緊張による影響を受けやすい傾向があります。
運動のしすぎと休息不足
シーバー病のもう一つの大きな原因は、**オーバーユース(使いすぎ)**です。
サッカーや陸上、バスケットボールなどのようにジャンプやダッシュを繰り返すスポーツでは、かかとへの衝撃が何百回も加わります。
この負担が積み重なると、成長線に微細な損傷が起こり、炎症や腫れが発生してしまうと言われています。
また、「痛いけど我慢して練習を続ける」ことも悪化の原因です。
痛みを抱えたまま動くと、片足をかばう歩き方になり、結果的に骨盤や膝、腰にも負担が広がるケースもあります。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sever_disease.html
靴の影響とフォームの崩れ
靴のクッション性が低かったり、サイズが合っていないと、着地時の衝撃がダイレクトにかかとへ伝わります。
さらに、**足の使い方(フォーム)**が乱れていると、かかとへの圧力が偏ってしまい、炎症を起こしやすくなります。
成長期の足は形が変わりやすいため、こまめに靴のフィット感をチェックすることが大切だと言われています。
姿勢や体のバランスの乱れ
普段の姿勢や歩き方もシーバー病のリスク要因のひとつです。
猫背や骨盤の傾き、偏平足、O脚などがあると、下肢全体のバランスが崩れ、特定の部位に負担が集中します。
日常的な姿勢の悪さが、運動中の着地動作にも影響を及ぼし、かかとに過剰なストレスを与えることがあるとされています。
#シーバー病 #成長期の痛み #オーバーユース #かかとの炎症 #スポーツ障害
放置するとどうなる?悪化・再発のリスク
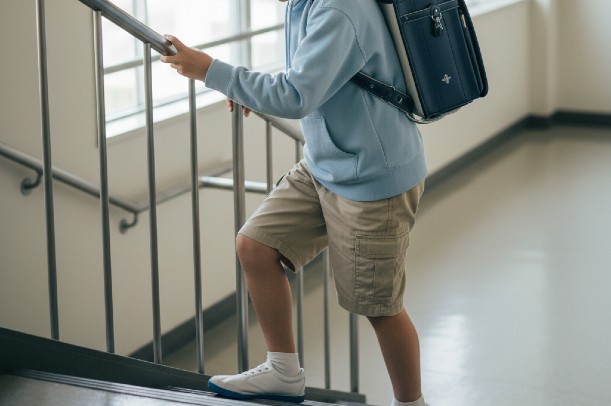
シーバー病は「一時的な成長痛だから、そのうち良くなる」と考えられがちですが、放置すると症状が長引いたり、再発しやすくなると言われています。
特にスポーツを続けている子どもは、痛みを我慢して動いてしまうことが多く、それが慢性的な炎症や歩行バランスの崩れにつながるケースもあります。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
痛みを放置すると慢性化する可能性
シーバー病の初期段階では「運動中だけ痛い」「少し休むと軽くなる」程度の症状が多いですが、炎症を放置すると骨の成長板(骨端核)に負担がかかり続けるため、慢性化するリスクが高まります。
この状態が続くと、痛みが運動後だけでなく、歩行や階段の上り下りでも出るようになることがあります。
さらに、かかとをかばって歩くクセがつくと、足首や膝、腰にまで負担が広がり、他の部位の不調を引き起こすこともあると言われています。
骨の変形リスクと成長への影響
シーバー病は、成長線(骨端線)に炎症が起こるのが特徴です。
この部分は骨が成長するための大切な軟骨組織であり、強い負担を繰り返すと成長板が損傷する可能性があります。
まれにですが、炎症が続くことで骨の形に影響を与えることもあり、痛みが長引いたり、かかとの形が変わることもあると報告されています。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sever_disease.html
そのため、「動けるから大丈夫」と放置するのではなく、痛みのある期間は安静を取ることが重要だと考えられています。
再発しやすい環境と生活習慣
シーバー病は、一度痛みが治まっても再発するケースが少なくありません。
特に、原因となる筋肉の硬さや姿勢のクセが改善されていない場合、運動を再開すると同じ場所に負担がかかりやすくなります。
また、靴の摩耗やサイズの合わないスパイクを使い続けることも、再発の一因になると言われています。
再発を防ぐためには、痛みがなくなったあとも、ふくらはぎやアキレス腱のストレッチを継続することが大切です。
無理をしない判断が重要
子どもは「大会があるから」「仲間と練習したいから」と無理をしてしまう傾向があります。
しかし、痛みを我慢して動くことは、回復の遅れや長期化につながるリスクがあります。
保護者や指導者が子どもの訴えを早めに察知し、「痛みが出たらすぐ休む」環境を整えることが何よりの予防策です。
#シーバー病 #成長期のかかと痛 #骨端炎 #再発予防 #スポーツ障害
回復を早めるケア方法と安静のポイント

シーバー病の回復を早めるためには、適切な安静と正しいケアが欠かせません。
「痛みを我慢して運動を続ける」ことが一番の悪化要因である一方で、ただ休むだけでは回復が遅れてしまう場合もあります。
痛みの程度や回復段階に合わせた対応を取ることが大切だと言われています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
安静にする期間とその過ごし方
シーバー病の痛みが強いときは、かかとに負担をかけないことが最優先です。
走る・跳ぶといった動作を避け、痛みが軽くなるまでは運動を中止するのが基本とされています。
ただし、完全に動かない生活を続けると筋力が落ちるため、痛みのない範囲でストレッチや軽い体操を行うとよいとされています。
また、痛みがある間は片足立ちや階段の上り下りを控え、必要に応じてかかとにクッション材を入れた靴を使用すると負担を軽減できます。
冷却(アイシング)で炎症を抑える
運動後や痛みが強いときは、氷や保冷剤でかかとを冷やすことが有効とされています。
目安は1回10〜15分程度。直接皮膚に当てると冷えすぎてしまうため、タオルを一枚挟むと安心です。
アイシングは炎症の広がりを抑えるだけでなく、痛みの軽減にもつながると言われています。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sever_disease.html
ストレッチで柔軟性を取り戻す
痛みが落ち着いてきたら、ふくらはぎ(下腿三頭筋)やアキレス腱のストレッチを少しずつ取り入れましょう。
壁に手をついて片足を後ろに伸ばし、かかとを地面につけたまま軽く体重をかけると、ふくらはぎがじんわり伸びます。
この動きを10〜20秒キープすることで、アキレス腱の柔軟性が改善され、かかとへの負担が軽減されると考えられています。
また、足裏の筋肉を緩めるためにゴルフボールやテニスボールを転がすセルフマッサージも有効です。
靴の見直しとテーピングの活用
シーバー病のケアでは、靴選びがとても重要です。
クッション性が高く、かかとをしっかり支える靴を選ぶことで、再発を防ぎながら回復をサポートできます。
靴底がすり減っている場合は、早めに買い替えることをおすすめします。
また、痛みが残る場合は、専門家の指導のもとでアキレス腱のテンションを調整するテーピングを行う方法もあります。
無理のない範囲で、日常生活の中にケアを取り入れることが回復の近道になります。
#シーバー病 #かかとの痛み #安静期間 #ストレッチ #アイシング
再発を防ぐためのトレーニングと生活習慣

シーバー病は、痛みが落ち着いたあとも再発しやすいスポーツ障害だと言われています。
特に、原因となった筋肉の硬さやフォームの乱れをそのままにしておくと、再びかかとに負担がかかり、痛みが戻ってしまうことがあります。
そこで大切なのが、回復後のトレーニングと生活習慣の見直しです。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/
ストレッチを習慣化して柔軟性をキープ
ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)やアキレス腱の硬さは、再発の大きな要因のひとつとされています。
痛みが改善した後も、毎日のストレッチを続けることが重要です。
壁押しストレッチやタオルストレッチを1日2〜3回行うことで、筋肉の柔軟性を維持できます。
また、入浴後など体が温まったタイミングで行うと、より効果的に筋肉がほぐれます。
「もう痛くないからやめる」ではなく、「予防のために続ける」意識が再発防止につながります。
正しいフォームと姿勢の見直し
成長期の子どもは、姿勢や動作のクセがかかとへの負担に影響することがあります。
たとえば、走るときにつま先重心になりすぎている、またはかかとを強く打ちつけるような着地をしていると、炎症が再発しやすいとされています。
フォーム指導を受ける、鏡の前で姿勢をチェックするなど、正しい体の使い方を意識することが予防の第一歩です。
さらに、デスクワークやゲームなどで長時間座りっぱなしになると、下肢の血流が悪くなり筋肉が硬くなりやすいため、日常の姿勢にも注意が必要です。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sever_disease.html
シューズ選びとインソールの工夫
再発防止には、靴のフィット感と衝撃吸収性が欠かせません。
かかとがしっかり支えられる構造で、クッション性の高い靴を選びましょう。
また、アーチサポートのあるインソール(中敷き)を使用することで、足裏全体で衝撃を分散できると言われています。
靴底がすり減っている場合は早めに交換し、成長に合わせてサイズを見直すことも大切です。
スポーツを再開する際は、必ず痛みのない状態を確認してから段階的に練習量を増やしていきましょう。
生活リズムと休息の質を整える
成長期は体の変化が大きいため、休息と栄養のバランスがとても重要です。
睡眠不足や偏った食事は、筋肉や骨の回復を妨げる可能性があるとされています。
カルシウム・ビタミンD・たんぱく質を意識的に摂り、しっかり眠る習慣をつけることが再発を防ぐ土台になります。
また、「練習したら休む」「週に1日は体をリセットする日を設ける」といったオフの時間の取り方も、ケガ予防に役立ちます。
#シーバー病 #再発予防 #ストレッチ習慣 #正しい姿勢 #子どものスポーツ障害








