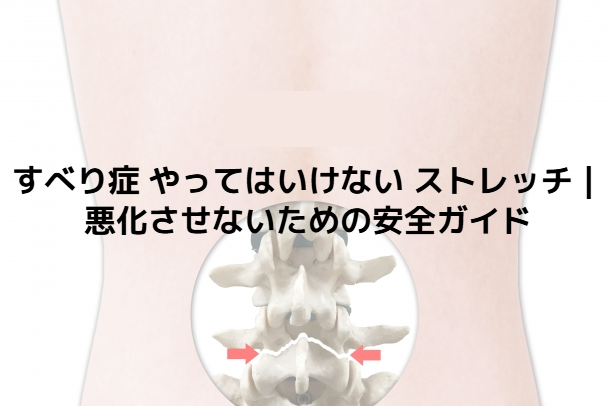すべり症とは何か?まず知っておきたい基礎知識

腰の骨がずれて起こる「すべり症」とは
「すべり症」とは、腰の骨(腰椎)が前後にずれてしまい、神経や周囲の組織に負担がかかる状態を指します。
特に中高年の女性に多く見られる傾向があり、加齢による骨や関節の変化、筋力の低下などが影響していると言われています。
人によっては腰の痛みだけでなく、お尻から太もも、ふくらはぎにかけてしびれを感じることもあります。
「腰が反ると痛い」「立ち上がるときにズキッとする」「歩くと腰が重くなる」といった症状が多く、日常生活の中で少しずつ違和感が増していくケースもあります。
無理なストレッチや姿勢のクセが悪化の引き金になることもあるため、まず“構造的に何が起きているのか”を理解しておくことが大切です。
引用元:https://koharu-jp.com/suberisho/suberisho-sitehaikenai
原因と背景にある「姿勢」「筋力」「生活習慣」
すべり症の原因は一つではなく、長年の姿勢や動作の積み重ねも大きく関係しています。
たとえば、長時間のデスクワークで背中が丸まる、立ち仕事で反り腰になっている、または腹筋や背筋が弱って骨を支えきれなくなっている——こうした状態が続くことで、骨のずれが起こりやすくなると言われています。
また、すべり症は急に発症することは少なく、少しずつ「腰に違和感がある」「朝起きると重い」と感じる段階から始まるケースもあるようです。
症状が軽いうちは筋肉のこわばりと勘違いしやすく、自己判断でストレッチをして悪化することもあるため注意が必要です。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_spondylolisthesis.html
早めに「体の変化」に気づくことが大切
腰の骨がずれることで神経の通り道が圧迫され、下半身にしびれや違和感が出ることもあります。
「ただの腰痛」と放っておくと、筋肉や姿勢のバランスがさらに崩れ、結果的に日常動作に支障が出る場合もあるとされています。
ストレッチや運動を始める前に、自分の体の状態を知り、負担の少ない動かし方を覚えることが、すべり症の予防にもつながると考えられています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/low-back-pain/
#すべり症とは
#腰痛の原因
#姿勢の悪化
#中高年女性の腰トラブル
#ストレッチの注意点
すべり症でやってはいけないストレッチとは?間違った動きが悪化を招く理由

腰を反らすストレッチは要注意
「腰が痛いなら、伸ばしたほうがいい」と思って、反り腰のように腰を大きく反らすストレッチをしていませんか?
実はこの動き、すべり症の人にはリスクが高いとされています。
腰椎が前方にずれる「前方すべり症」の場合、反る動作で神経がさらに圧迫され、痛みやしびれを強めてしまうことがあるのです。
特に、ヨガの「コブラのポーズ」や、うつ伏せで上体を起こすような動きは要注意です。
一見、気持ちよく伸びているように感じても、腰の関節や靭帯には大きな負担がかかっています。
痛みが強くなる前に、反らす動作は一旦控えることが大切だと言われています。
引用元:https://koharu-jp.com/suberisho/suberisho-sitehaikenai
ひねりを加えるストレッチも危険
腰を左右にねじる動作も、すべり症の方には不向きとされています。
「背骨の柔軟性を高めよう」と思ってツイスト系ストレッチを続けてしまうと、ずれた骨の部分にねじれの力が加わり、症状を悪化させる可能性があるからです。
座って体をねじる、寝転がって足を反対側に倒す、といったポーズも無理は禁物です。
実際、「ひねると腰がズキッとする」「朝起きたら痛みが強まっていた」という声も多いようです。
引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7660
「押す」「叩く」「刺激する」は逆効果に
痛みを和らげようとして、テニスボールやストレッチポールで腰を強く押す方もいますが、これも避けたほうが良い動作とされています。
骨や筋肉を直接刺激することで一時的にスッキリするように感じても、炎症を助長してしまうことがあるのです。
「筋肉を緩めたい」「血流をよくしたい」という気持ちはわかりますが、過度な圧迫はかえって回復を遅らせることにつながると言われています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/low-back-pain/
痛みを我慢して続けるのはNG
「少しくらい痛いけど、続けていれば慣れるはず」と我慢してしまう人もいます。
しかし、すべり症の痛みは筋肉の張りではなく、骨のずれや神経圧迫によるもの。
痛みを無視してストレッチを続けると、かえって症状が長引くことがあると指摘されています。
少しでも違和感があれば、無理に続けず、体を休めることを優先しましょう。
#すべり症ストレッチ禁止
#腰を反らさない
#ねじり動作注意
#テニスボールNG
#痛みを我慢しない
すべり症の人でも安全にできるストレッチと代替エクササイズ

痛みを出さない“動かし方”を意識する
すべり症の方がストレッチを行う際に最も大切なのは、「動かすこと」よりも「痛みを出さないこと」です。
「ストレッチは我慢して伸ばすもの」と思っている方も多いですが、すべり症の場合はその考え方が逆効果になることがあります。
筋肉や神経が炎症を起こしている状態では、無理な動きがさらなる負担になると言われています。
動かすときは、「少し気持ちいい程度」で止めるのがポイントです。
また、呼吸を止めずに“ゆっくり吸って吐く”を意識すると、筋肉が自然と緩みやすくなります。
無理に反る、ねじる動きは避け、腰を丸めるような姿勢を中心に取り入れるとよいでしょう。
引用元:https://koharu-jp.com/suberisho/suberisho-sitehaikenai
安全に行えるストレッチの例
比較的安全とされているのは、「背中を丸める」「股関節を軽く動かす」といったストレッチです。
たとえば、仰向けに寝た状態で両膝を抱える「抱え込みストレッチ」は、腰を反らさずに筋肉をゆるめることができると言われています。
また、座ったまま骨盤を前後にゆっくり揺らす動きも、腰回りの筋肉を無理なく刺激できるためおすすめです。
「ストレッチ=腰を伸ばす」ではなく、「体をやさしく動かして血流を促す」と考えると、より安全に取り組めます。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/low-back-pain/
体幹を支える“インナーマッスル”を鍛える
ストレッチと並行して、体を支える筋肉を少しずつ使うことも大切です。
特に腹横筋や骨盤底筋などの「インナーマッスル」は、腰椎を安定させる働きがあるとされています。
寝た状態でお腹を軽く引き締める「ドローイン」や、四つん這いで手足をゆっくり動かす「バードドッグ」などは、腰を大きく動かさずに体幹を整える運動として知られています。
ただし、痛みが強いときやしびれが出ている場合は、無理に行わず休息を優先してください。
“動かすことより守ること”が、すべり症を悪化させないコツだと言われています。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_spondylolisthesis.html
#すべり症ストレッチ
#安全な運動方法
#反らさない動き
#インナーマッスル強化
#痛みを出さない運動
すべり症を悪化させないために日常生活で注意したい動きとコツ

「反る」「ひねる」姿勢を減らす意識を持つ
すべり症を抱えている方にとって、日常の何気ない動作が悪化のきっかけになることがあります。
特に気をつけたいのが「反る」「ひねる」動きです。
例えば、洗濯物を高い位置に干すときに腰を反らせたり、振り向く動作で体をひねることなどが挙げられます。
こうした姿勢は腰の骨(腰椎)に過剰な負担をかけやすく、すべりの進行を助長してしまうことがあると言われています。
もしどうしても反る姿勢をとる必要がある場合は、片足を一歩前に出して腰の負担を分散させる工夫をしてみてください。
また、後ろを振り向くときは腰ではなく、できるだけ上半身全体で動かす意識を持つと良いでしょう。
引用元:https://koharu-jp.com/suberisho/suberisho-sitehaikenai
座り方と椅子の選び方を見直す
長時間のデスクワークや車の運転も、腰にとっては負担のかかる姿勢です。
背もたれに深く座り、骨盤を立てた状態を保つよう意識すると、腰への圧迫が軽減されるとされています。
また、やわらかすぎるソファや背中が丸まりやすい椅子は避け、腰の自然なカーブを支えるクッションなどを使うと良いでしょう。
1時間以上同じ姿勢が続くと血流も滞りやすくなるため、こまめに立ち上がって軽く体を伸ばすことも大切です。
「10分休むより、1分動く」の意識で、小さなリセットを繰り返すのがおすすめです。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/low-back-pain/
重いものを持つときのコツ
重い荷物を持つときは、腰からではなく「脚の力」を使うようにしましょう。
膝を曲げてしゃがみ、荷物を体の近くで抱えるように持ち上げると、腰の負担を減らせると言われています。
中腰の姿勢のまま持ち上げるのは最も危険で、ぎっくり腰の原因にもなりかねません。
また、買い物袋などは片側だけに持つのではなく、左右均等に分ける工夫もポイントです。
小さな意識の積み重ねが、すべり症の再発防止にもつながります。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_spondylolisthesis.html
冷えと疲労のケアも忘れずに
腰の筋肉は冷えると硬くなりやすく、血流の悪化が痛みを招くことがあります。
お風呂で温める、腹巻きを使う、冷房の風を直接浴びないなど、冷え対策を日常的に意識すると良いでしょう。
また、睡眠不足やストレスも筋肉の緊張を高める要因とされているため、十分な休息を取ることも大切です。
#すべり症悪化予防
#正しい姿勢
#腰に優しい座り方
#重い物の持ち方
#冷え対策と休息
すべり症を改善に導くための生活習慣とセルフケアのポイント

体を温めて「血流」を整える
すべり症の改善には、筋肉や関節を冷やさず、血流を整えることが大切だと言われています。
腰回りの筋肉が冷えると緊張が強まり、痛みやしびれが出やすくなる傾向があります。
入浴ではシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かって体の芯を温めましょう。
また、寝る前にホットタオルや湯たんぽで腰を温めるのもおすすめです。
冷たい飲み物の摂りすぎを控え、常温の水や白湯を選ぶと、内側からも血流をサポートできます。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/low-back-pain/
無理のないストレッチを「習慣化」する
すべり症の方でもできる軽いストレッチを、日常の中に少しずつ取り入れるのが理想です。
たとえば、朝起きたときに膝を軽く抱えて背中を丸めるストレッチ、椅子に座ったまま骨盤を前後に動かす運動などは、安全に筋肉を緩める方法として知られています。
重要なのは「毎日少しずつ」続けること。
短時間でも継続することで、腰の筋肉がこわばりにくくなり、再発予防にもつながると言われています。
引用元:https://koharu-jp.com/suberisho/suberisho-sitehaikenai
筋肉の“支え”を取り戻すトレーニング
痛みが落ち着いてきたら、腰を守るためのインナーマッスルを少しずつ使う練習を取り入れましょう。
腹横筋を鍛える「ドローイン」や、四つん這い姿勢で片腕と反対の脚をゆっくり伸ばす「バードドッグ」は、腰を大きく動かさずに体幹を支える効果があるとされています。
ただし、痛みが出る場合は無理をせず、呼吸を止めないことを意識して行うのがポイントです。
引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_spondylolisthesis.html
睡眠・姿勢・メンタルのバランスも大切
腰を休める時間=寝る時間の姿勢も意識してみましょう。
仰向けで膝の下にクッションを入れると腰のカーブが自然になり、負担が減ると言われています。
また、ストレスや睡眠不足は筋肉の緊張を高める要因にもなるため、心身をリラックスさせる時間を確保することも忘れずに。
毎日の小さな積み重ねが、結果的に「すべり症を悪化させない体づくり」につながると考えられています。
#すべり症セルフケア
#腰痛予防生活
#血流改善
#安全なストレッチ
#インナーマッスル強化