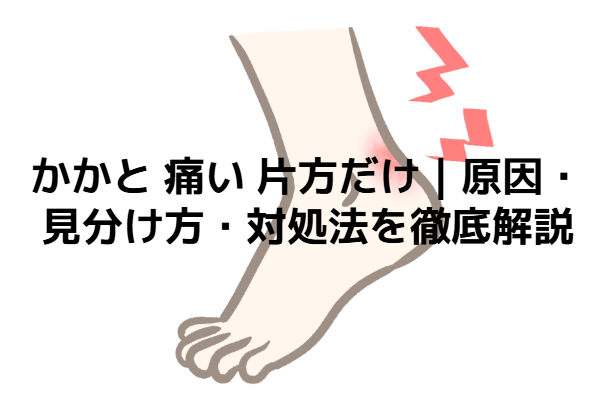かかとが片方だけ痛む人の特徴と注意点

片足だけに痛みが出るのはなぜ?
「右足のかかとだけ痛い」「歩くたびに片方だけズキッとする」――そんな経験はありませんか?
実は、かかとが片方だけ痛む場合、両足に負担のバランスが偏っていることが多いと言われています。たとえば、長時間の立ち仕事で無意識に片足に重心をかけている人や、靴のすり減り方が左右で違う人などが該当します。体全体の歪みや姿勢のクセが、かかとへの負荷の差につながるケースもあります。
また、足底腱膜炎(足底筋膜炎)やアキレス腱付着部炎などの炎症が、片方の足にだけ起こることも珍しくありません。これは、利き足側により強いストレスがかかるためと考えられています。特に、運動後や朝起きて最初の一歩を踏み出す瞬間に痛みを感じる人は、炎症や微細な損傷が進行している可能性があります。
引用元:くまのみ整骨院
日常動作と生活習慣が関係していることも
片足だけのかかと痛は、日常動作の積み重ねによって生じることもあります。
例えば、「片足立ちでズボンを履く」「階段を上るときいつも同じ足から踏み出す」といった些細なクセが、左右の筋肉バランスを崩し、結果的に一方のかかとに負担をかけてしまうことがあります。こうした習慣は自覚しづらいですが、鏡を見ながら立ち姿勢を確認すると、左右の重心差が見えてくることもあります。
また、靴のフィット感も見逃せません。インソールの片側が潰れている、ヒールが片減りしているなど、足裏のサポートが不均等だと、痛みが出やすくなる傾向があります。
スポーツをしている人では、ランニングフォームの左右差や足首の可動域の違いも関係しているとされています。
引用元:日本整形外科学会 足の痛みガイド
注意しておきたいサインと対処の目安
かかとの痛みが数日で軽くなる場合もありますが、「朝の一歩で強く痛む」「押すと鋭く痛い」「腫れや熱感を伴う」などの症状が続く場合は注意が必要です。無理に歩き続けると、炎症が広がることもあるとされています。
自宅ではまず、安静を保ち、足底やふくらはぎを軽くストレッチしてみましょう。痛みが強いときは冷やすことで炎症を和らげることがあるとも言われています。
数日経っても改善がみられない場合や、体重をかけるのが難しいほど痛いときは、整形外科や整体院での検査を受けておくと安心です。
引用元:日本足の外科学会
#かかと痛い片方だけ
#足底腱膜炎
#アキレス腱付着部炎
#重心バランスの崩れ
#靴の片減り対策
考えられる主な原因:疾患・損傷パターン別

足底腱膜炎(足底筋膜炎)
「朝起きて一歩目がズキッと痛む」「立ち仕事のあとにかかとがじんわり痛む」――そんな症状がある人は、『足底腱膜炎(足底筋膜炎)』の可能性があると言われています。足の裏にある膜状の組織が繰り返し引っ張られることで炎症を起こし、特にかかと付近に痛みが出やすいとされています。
片方だけに起こることも多く、立ち姿勢や歩き方の癖、靴の片減りなどが一因とされます。慢性的になると、朝だけでなく日中も痛みが続くことがあります。
引用元:くまのみ整骨院
アキレス腱炎・アキレス腱付着部炎
かかとの後ろ側が痛む場合、アキレス腱炎やアキレス腱付着部炎が関係していると言われています。走る・ジャンプする・階段を上るなどの動作で、アキレス腱に過度な負荷がかかることで炎症が生じるケースがあります。
特に、運動習慣のある人や急に運動を始めた人に見られやすく、片足だけに負担が集中した結果として痛みが出ることもあります。触れると熱を持っていたり、腫れを感じる場合もあるようです。
引用元:日本整形外科学会
踵骨疲労骨折・踵骨棘(しょうこつきょく)
長時間の歩行や立ち仕事、ランニングなどでかかとの骨(踵骨)に繰り返し負担がかかると、疲労骨折を起こすことがあります。初期段階では違和感程度ですが、進行するとピンポイントで痛みが強くなる傾向があると言われています。
また、『踵骨棘(しょうこつきょく)』と呼ばれる骨の突起が形成されることもあり、炎症を伴うと足底腱膜炎と似た痛みを感じる場合もあるそうです。X線やMRIによる検査で確認されることが多いとされています。
引用元:日本足の外科学会
踵部脂肪体障害・シーバー病(子どもに多い)
かかとの下部には衝撃を吸収する脂肪組織(脂肪体)があり、これが薄くなったり炎症を起こすと、クッション性が失われ痛みを感じやすくなることがあります。これを踵部脂肪体障害と呼ぶことがあります。
また、成長期の子どもに多い『シーバー病(踵骨骨端症)』も、片側だけ痛みが出るケースがあります。成長期特有の骨の未発達な部分に繰り返しの衝撃が加わることで発症するとされています。
引用元:整形外科疾患ナビ
炎症以外の要因(姿勢・靴・生活習慣)
炎症や損傷以外にも、姿勢の崩れや合わない靴などによって、かかとへの負担が片側に集中することがあります。特に、ヒールや底の薄い靴をよく履く人、インソールが片方だけ潰れている人は注意が必要です。
さらに、腰や骨盤の歪みが足元に影響し、片方の足に過剰な体重がかかることもあります。こうした日常の積み重ねが慢性的な痛みにつながることもあるため、まずは立ち方や歩き方を意識することが大切と言われています。
引用元:くまのみ整骨院
#かかと痛い片方だけ
#足底腱膜炎
#アキレス腱付着部炎
#踵骨疲労骨折
#シーバー病
セルフチェックと見分け方ガイド

痛みの場所とタイミングを観察する
「どの辺が痛いか」「いつ痛むか」を丁寧に観察することは、原因を見極めるうえでとても大切だと言われています。
例えば、朝起きて最初の一歩が特に痛い場合は、足底腱膜炎の初期サインであることが多いとされています。一方で、運動後や長時間の立ち仕事のあとに痛みが出るケースでは、アキレス腱炎や踵骨疲労骨折など、負荷の蓄積による炎症の可能性が指摘されています。
痛みの位置にも注目してみましょう。かかとの「裏側」が痛い人は足底腱膜炎、「後ろ側」が痛い人はアキレス腱や踵骨の障害が関係していることがあるとされています。左右差や押したときの痛み方の違いを記録しておくと、検査の際にも役立ちます。
引用元:くまのみ整骨院
押してみる・動かしてみるチェック
自宅で簡単にできるセルフチェックとして、「押して痛い場所」を確認する方法があります。
指でかかとの中央から内側・外側・後方をそれぞれ軽く押してみて、どの部分に強い痛みを感じるかを確かめてみましょう。
また、足首を上下に動かしたときの痛みも目安になります。動かすたびにズキッと響くような場合は、筋肉や腱の炎症が進んでいる可能性があると言われています。
ただし、無理に力を入れて押したり、ストレッチを繰り返すのは逆効果になることもあるため、強い痛みを感じる場合は安静を保つことが大切です。
引用元:日本整形外科学会
痛みの強さと続く期間をチェック
「何日続いているか」「痛みの強さが変化しているか」も重要な判断ポイントです。
数日で落ち着くようなら一時的な炎症の可能性もありますが、1週間以上続く・夜もズキズキする・腫れや熱を伴うなどの場合は、専門的な検査が推奨されています。
こうした症状は、単なる疲労ではなく、組織の損傷や骨への負担が進行しているサインである可能性もあると言われています。
また、両足を比べて立ってみたときに「片足だけ体重をかけづらい」「左右の高さが違う」などを感じる場合は、重心バランスが崩れていることも考えられます。その場合は、骨盤や姿勢のチェックもあわせて行うとよいとされています。
引用元:日本足の外科学会
痛みを悪化させないためのセルフ観察のコツ
痛みを軽減させるためには、「どんなときに痛むか」を日記のようにメモしておくのもおすすめです。
・立ち上がる瞬間の痛み
・歩行中の場所(かかと、土踏まずなど)
・仕事後や運動後の変化
こうした情報は、来院時に伝えることで原因の特定がしやすくなるとされています。
また、痛みが強いときは無理に歩かず、できる範囲で安静を心がけましょう。過度なマッサージやストレッチは避け、冷却や軽いストレッチなど“優しいケア”を意識することがポイントです。
引用元:整形外科疾患ナビ
#かかと痛い片方だけ
#セルフチェック
#足底腱膜炎見分け方
#アキレス腱炎のサイン
#痛みの記録と観察
日常でできる対処方法・セルフケア

まずは安静と負荷の見直しから
かかとが片方だけ痛むときは、まず安静を保ち、負荷を減らすことが基本と言われています。
特に、朝や運動後の痛みが強い場合は、足底腱膜やアキレス腱に炎症が生じている可能性があるため、無理に歩き続けないよう注意が必要です。
「少し痛いけど歩けるから大丈夫」と思って動き続けると、炎症が悪化しやすくなるケースもあるため、できる範囲で体重をかけないよう意識するのがポイントです。
立ち仕事の人は、こまめに足を休めたり、同じ姿勢を長時間続けないようにしましょう。
引用元:くまのみ整骨院
ストレッチと筋膜リリースで血流を促す
炎症が落ち着いてきたら、ふくらはぎや足底の筋肉を軽くストレッチすることで血流が促され、負担を減らせる場合があるとされています。
たとえば、壁に手をついてアキレス腱をゆっくり伸ばす、足裏をゴルフボールで優しく転がすなどの方法です。
このとき、「痛気持ちいい」程度の強さを意識し、強く押しすぎないことが大切です。
また、足首をぐるぐる回すだけでも、足底の血流をサポートできます。冷えを感じる場合は、ぬるめのお湯で温めてから行うのも効果的だと言われています。
引用元:日本整形外科学会
靴の見直しとインソールの活用
意外と見落とされがちなのが、「靴」の影響です。
靴底が片減りしている、サイズが合っていない、クッション性が低い靴を履いていると、左右の負担バランスが崩れて痛みを招くことがあります。
特に、片方の靴だけ擦り減っている場合は、歩行中に無意識に体重が片側にかかっているサインかもしれません。
クッション性のある中敷きや、足の形に合わせたインソールを取り入れると、かかとへの衝撃をやわらげられるとされています。靴を選ぶときは、かかと部分がしっかりフィットして安定するタイプを選ぶのが理想的です。
引用元:整形外科疾患ナビ
冷却と温熱の使い分け
痛みが強い・熱っぽい場合は、まず”冷却(アイシング)”を行うことで炎症を落ち着かせられるとされています。
一方で、慢性的な張り感や血行不良による重だるさには、”温熱(ホットタオルや足湯)”が効果的だとされています。
症状によって使い分けることで、過度な炎症や冷えを防ぐことができます。
ただし、冷やしすぎや温めすぎは逆効果になることもあるため、10〜15分を目安に行いましょう。
引用元:くまのみ整骨院
無理をせず、体全体のバランスを整える
片方のかかとだけが痛むとき、その原因が足だけでなく体全体のバランスにあることも多いとされています。
骨盤の歪みや猫背、歩行フォームのクセなどを改善することで、再発を防げる可能性があります。
ストレッチや軽い体幹トレーニングを取り入れると、左右の負担差を減らす効果が期待できるとも言われています。
「痛みが軽くなったからもう大丈夫」と油断せず、日常の姿勢や動き方を見直していくことが長期的な改善につながります。
#かかと痛い片方だけ
#セルフケア
#ストレッチ
#インソール対策
#温冷ケア
受診の目安と専門的な検査・施術の流れ

どんなときに来院を考えるべき?
かかとの痛みが数日でおさまる場合もありますが、”「朝の一歩で強い痛みが出る」「腫れや熱を感じる」「1週間以上続いている」”などの症状がある場合は、早めに専門機関での検査を受けることが推奨されています。
特に、片方のかかとだけ強く痛む場合は、炎症や骨のトラブルが進行しているケースもあるため、早期対応が重要だと言われています。
「様子を見ていたら悪化して歩けなくなった」という例も少なくないため、我慢せず専門家に相談しておくと安心です。
また、痛みが強いのに外見上の腫れが少ない場合でも、骨や腱の深部で炎症が起きていることがあります。整形外科、もしくは足の専門的な整体院での検査が有効とされています。
引用元:日本整形外科学会
検査で行われる主なチェック内容
来院時には、まず問診と触診で痛みの部位や経過を確認します。どのタイミングで痛みが強いのか、どんな靴を履いているかなど、生活背景のヒアリングも重要な情報になります。
その後、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を行うことがあります。骨の異常や筋・腱の炎症を確認し、どの程度負担がかかっているかを見極めるためです。
痛みの原因がはっきりすれば、適切な施術方針を立てやすくなります。検査で骨や腱の異常が見られない場合でも、姿勢や歩行バランスの乱れが原因のことも多く、理学療法的なアプローチが有効だと言われています。
引用元:日本足の外科学会
主な施術とリハビリの流れ
かかとの痛みが強い場合、整形外科や整体院では、物理療法(超音波・電気刺激・温熱)やストレッチ指導を組み合わせて施術を行うことがあります。
また、足底への負担を軽減するためのインソール作製やテーピングサポートを勧められるケースもあります。
急性期(痛みが強い時期)は安静を優先し、痛みが落ち着いた段階で筋肉の柔軟性を取り戻すリハビリを行うのが一般的です。
特に、ふくらはぎ・アキレス腱・足底筋膜のストレッチは、再発防止の観点からも重要とされています。
引用元:くまのみ整骨院
改善までの期間と再発予防
かかとの痛みの改善期間は個人差がありますが、一般的には軽症で数週間、慢性化すると数か月かかることもあると言われています。
痛みが軽くなった後も、同じ姿勢や靴を使い続けると再発する可能性があるため、根本的な負担要因の見直しが欠かせません。
再発予防としては、
- 立ち方や歩行フォームを意識する
- かかと周りのストレッチを続ける
- 靴底のすり減りをこまめに確認する
- 無理な運動を避ける
といった習慣づけが有効とされています。
痛みが落ち着いたあとも、「もう大丈夫」と思わず、体全体のバランスを整えるケアを続けることが再発防止のカギです。
#かかと痛い片方だけ
#整形外科検査
#理学療法
#インソール作製
#再発予防