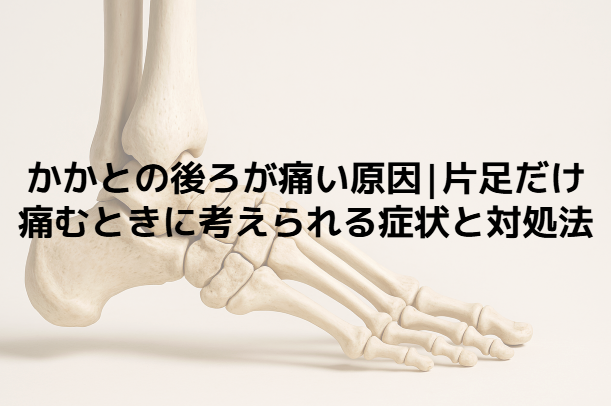かかとの後ろが痛いとは?症状の特徴と仕組み

かかとの後ろに痛みを感じるメカニズム
「歩くときにかかとの後ろがズキッと痛む」「片足だけ違和感がある」──そんな経験をしたことはありませんか?このような痛みは、アキレス腱やその周辺組織に負担がかかることで炎症が起こるのが一般的な原因だと言われています。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/
かかとの後ろには、アキレス腱がふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)と踵骨(しょうこつ/かかとの骨)をつなぐように走っています。ジャンプや階段の上り下りなど、足首を大きく動かす動作を繰り返すと、腱がこすれて炎症を起こしやすくなるとされています。特に片足に体重をかけるクセがある人は、左右どちらか一方に痛みが出る傾向があるようです。
痛みの特徴とよくある訴え
かかとの痛みの感じ方にはいくつかのパターンがあります。
- 歩き始めるとズキズキするが、動いているうちに軽くなる
- 靴のかかと部分が当たるとチクチクする
- 朝起きて一歩目に強い痛みがある
- 運動後や長時間の立ち仕事のあとに痛みが増す
これらの症状は、**アキレス腱炎やアキレス腱付着部炎、滑液包炎(かつえきほうえん)**などが関係していることが多いと言われています。中でも滑液包炎は、アキレス腱とかかとの骨の間にある小さなクッション(滑液包)が炎症を起こすことで痛みを感じる仕組みとされています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/heelpain/
片足だけに痛みが出るケースも多い
「右足だけ痛い」「左足のかかとだけ違和感がある」という相談も多く見られます。これは、姿勢のクセや体重のかけ方の左右差によって、片側のアキレス腱や筋肉に過度な負担がかかるためだと言われています。
たとえば、立っているときに片足重心になっていたり、片側の靴底がすり減っていたりする人は要注意です。日常生活の中の“わずかな癖”が、片足だけの痛みにつながることがあるのです。
靴や地面との摩擦も原因になる
かかとの後ろが痛いとき、実は靴との相性も大きく関係しています。かかとのカウンター(靴の後部)が硬い、サイズが合っていない、あるいは新しい靴を履き始めたばかりなどの場合、摩擦が起きて炎症を引き起こすことがあります。
特に運動靴や革靴で長時間歩く人は、素材やクッション性を見直すことで痛みを軽減できる場合もあるとされています。足元の環境を整えることが、思わぬ予防につながるのです。
引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp
まとめ
かかとの後ろが痛いときは、アキレス腱や滑液包などの炎症が関係していることが多いと言われています。片足だけ痛む場合は、姿勢や靴の影響も見逃せません。早い段階で生活動作を見直すことで、慢性化を防ぐ手助けになるとされています。
#かかとの痛み #アキレス腱炎 #片足の違和感 #滑液包炎 #靴の摩擦
片足だけ痛む場合に考えられる原因

片側のみに痛みが出るのはなぜ?
「右足のかかとだけ痛い」「左足だけズキッとする」――このように片足だけに痛みが出る場合、全身のバランスや使い方の偏りが関係していることが多いと言われています。人は無意識のうちに、立つ・歩く・階段を上るなどの日常動作の中で、どちらか一方に体重をかけるクセがあります。その結果、片側のアキレス腱や筋肉、かかと周辺に負担が集中してしまうのです。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/
たとえば、長時間立ち仕事をしている人で「いつも同じ足に重心を置く」傾向がある場合や、スポーツ中に利き足ばかり使う習慣がある場合などは、片側に炎症が起きやすいとされています。
よく見られる主な原因①:アキレス腱炎
片足のかかとの後ろが痛むとき、最も多いのがアキレス腱炎です。特にランニングやバスケットボール、サッカーなどジャンプや走行を繰り返す動作を続けていると、片側のアキレス腱に過剰なストレスがかかります。
アキレス腱炎は、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)の硬さが影響するとも言われています。筋肉が硬くなることで腱が引っ張られ、炎症が起きやすくなるのです。最初は運動後の軽い違和感程度でも、放置すると慢性的な痛みに発展することがあるため、早めのケアが大切です。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/heelpain/
よく見られる主な原因②:滑液包炎(アキレス腱滑液包炎)
かかとの後ろには「滑液包(かつえきほう)」という小さな袋状のクッションがあります。これが繰り返しの摩擦や圧迫によって炎症を起こすのが「滑液包炎」です。特に、靴のかかとが硬い場合やサイズが合っていないと、片足だけに炎症が出やすくなることがあります。
「靴を履くと痛い」「素足では痛くない」などの症状がある場合は、靴との摩擦が主な原因と考えられています。靴の形状を見直すことが、痛み軽減の第一歩になるでしょう。
引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp
よく見られる主な原因③:姿勢・歩き方のクセ
姿勢の歪みや歩き方のクセも、片側だけ痛みを引き起こす大きな要因だと言われています。たとえば、猫背や骨盤の傾きがあると、重心が左右どちらかに偏り、片方のかかとへの負担が増します。また、X脚やO脚など脚のラインの影響も無視できません。
このような場合、痛みの根本的な原因は「かかと」ではなく、**全身のアライメント(姿勢バランス)**にあることが多いとされています。ストレッチや姿勢改善の意識が、再発防止につながります。
成長期の痛みにも注意
中高生など成長期の年代では、**シーバー病(踵骨骨端症)**が原因となるケースもあります。これは、成長過程で骨の付け根が炎症を起こしやすくなる症状で、特にサッカーや陸上などを頑張っている子どもに多い傾向があると言われています。
「片足だけ痛がっている」「運動後に泣くほど痛い」といった場合は、早めに整骨院や専門機関に相談することが大切です。無理に運動を続けず、痛みの程度に合わせて休息を取ることが改善への第一歩とされています。
まとめ
片足だけかかとの後ろが痛い場合、その原因はアキレス腱炎・滑液包炎・姿勢のクセ・靴の摩擦など、多岐にわたります。痛みの背景には、体の使い方の左右差が隠れているケースも多いため、日常の姿勢や歩行を見直すことが大切だと言われています。
#かかとの痛み #片足だけ痛い #アキレス腱炎 #滑液包炎 #姿勢のクセ
自分でできるチェックとセルフケア

まずは痛みの位置とタイミングを確認する
「かかとのどの部分が痛いか」「いつ痛みが出るか」を確認することが、原因を見極める第一歩と言われています。
たとえば、アキレス腱のすぐ下がズキズキする場合はアキレス腱炎の可能性があり、靴が当たる部分が赤く腫れている場合は滑液包炎の傾向があると言われています。
また、「朝起きて一歩目が痛い」「運動後にだけ痛む」など、痛みの出るタイミングを記録しておくと、改善策を立てやすくなります。症状を放置せず、早めに体のサインを把握することが大切です。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/
自宅でできるセルフチェック方法
自分でできるチェックとして、以下の3つを試してみましょう。
- 押してみるチェック:かかとの後ろやアキレス腱の付け根を軽く押してみて、どの場所に痛みがあるか確認。
- 動かしてみるチェック:つま先立ちをしたり、足首を上下に動かしたりして痛みが強くなるかどうか確認。
- 靴のチェック:靴のかかと部分が硬すぎたり、片側だけ擦れていたりしないかを確認。
このセルフチェックで、痛みが出る動きや摩擦の原因を把握できる場合があります。強く押したり、無理に動かしたりしないよう注意しながら行うことが大切です。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/heelpain/
痛みが軽い場合のセルフケア
軽度の痛みであれば、自宅でのケアで落ち着くこともあると言われています。
たとえば、運動後にアイシング(冷却)を15〜20分程度行うと、炎症を和らげやすいとされています。また、ふくらはぎのストレッチも効果的で、アキレス腱への引っ張りを軽減し、血流を促す役割があると考えられています。
簡単なストレッチ方法:
- 壁に手をつき、痛みのある足を後ろに伸ばしてかかとを床につける
- そのまま10〜15秒キープし、ふくらはぎが伸びる感覚を感じる
- 1日に2〜3セットを目安に行う
無理せず、気持ちいい範囲で続けることが大切です。
引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp
靴や生活習慣の見直しも大切
痛みを繰り返す場合、靴のサイズや素材、インソールの形が合っていないこともあります。
特にかかとの部分が硬い靴や、ヒールの高い靴を長時間履く習慣は、炎症を悪化させる要因になることがあるため、柔らかくフィットするものに変えるのがおすすめです。
また、片足重心の立ち方や、座っているときに足を組むクセも、体のバランスを崩す原因になります。日常の「姿勢のクセ」を見直すことが、痛みの再発を防ぐ重要なポイントです。
注意したいセルフケアの限界
もし、セルフケアを続けても痛みが3日以上引かない場合や、腫れ・熱感・歩行時の強い痛みがあるときは、無理せず専門家に相談することがすすめられています。
早い段階で原因を明確にし、適切な施術を受けることで、慢性化を防げるケースが多いと言われています。
まとめ
かかとの後ろが痛いときは、まず自分で痛みの場所とタイミングをチェックし、アイシングやストレッチなどのセルフケアを試してみることが大切です。靴や姿勢を見直しつつ、痛みが続くようなら早めの相談を心がけましょう。
#かかとの痛み #セルフチェック #ストレッチ #アイシング #靴選び
改善のための対応策と再発予防

まずは「痛みを悪化させないこと」が第一歩
かかとの後ろが痛いとき、最初に意識すべきなのは無理をせず炎症を広げないことだと言われています。痛みを感じながら運動や長時間の立ち仕事を続けると、アキレス腱や滑液包に負担がかかり、慢性化するリスクが高まるためです。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/
まずは**安静とアイシング(冷却)**を中心に行い、痛みが強いときは1日数回、15〜20分を目安に冷やすとよいとされています。冷却によって炎症の拡大を抑えやすくなり、違和感の軽減につながるケースもあると考えられています。
ストレッチでアキレス腱周囲をやわらかく保つ
痛みが落ち着いてきた段階では、ふくらはぎのストレッチを取り入れることがすすめられています。アキレス腱はふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)と直接つながっているため、筋肉をほぐすことで腱への引っ張りを軽減できると言われています。
簡単な方法としては、壁に手をついてかかとを床につけたまま体を前に傾ける「カーフストレッチ」がおすすめです。これを1回10〜15秒、1日数セット続けるだけでも、柔軟性の維持に役立つとされています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/heelpain/
靴の見直しとインソールの活用
再発を防ぐためには、靴の形状やサイズを見直すことも重要です。かかと部分が硬すぎる靴や、足に合っていないインソールを使っていると、摩擦や圧迫が続き、再び炎症を起こすことがあります。
柔らかくクッション性のある靴を選び、足首を安定させるインソールを使用すると、衝撃を分散しやすいと言われています。また、靴紐の締め方や靴下の厚みを変えるだけでも、接触部分の刺激を減らすことができます。
引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp
体の使い方を整えるトレーニング
かかとの痛みは、体全体のバランスの崩れから生じることもあると考えられています。特に、片足重心のクセや、足首・膝・股関節の連動がうまくいかない場合、かかとへの負担が増しやすいと言われています。
そのため、再発予防には体幹やお尻の筋肉を鍛えるトレーニングも有効です。プランクやヒップリフトなど、体を安定させる筋肉を使う運動を日常に取り入れると、姿勢が安定し、片足だけに負荷が集中しにくくなります。
生活習慣の見直しで再発防止を
普段の生活の中で、同じ姿勢を長く続ける習慣を減らすこともポイントです。立ちっぱなしや座りっぱなしの時間が長いと血流が滞り、筋肉が硬くなりやすくなります。1時間に1度は足を動かしたり、つま先立ちをしたりして、ふくらはぎの血流を促す習慣を持つと良いでしょう。
また、睡眠不足や栄養バランスの乱れも、回復を遅らせる要因とされています。たんぱく質・ビタミンC・ミネラルなど、筋肉や腱の修復に必要な栄養を意識して摂取することも大切です。
まとめ
かかとの後ろの痛みを改善するには、安静・冷却・ストレッチを基本に、靴の見直しや体の使い方の改善を組み合わせることが効果的だと言われています。再発を防ぐためには、日々の動き方や姿勢を意識し、体をケアする習慣を持つことが何より大切です。
#かかとの痛み #ストレッチ #靴の見直し #体幹トレーニング #再発予防
放置しないほうがいいサインと相談の目安

「そのうち治るだろう」は危険なケースも
かかとの後ろが痛いとき、多くの人は「少し休めばそのうち良くなるだろう」と思いがちです。ところが、痛みを我慢して放置すると、炎症が慢性化したり、歩行バランスの崩れにつながったりすることがあると言われています。特に、立ち仕事や運動を続けている場合、自然に改善することは少ないとされています。
引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/
痛みが続くことで、無意識に片足をかばって歩くようになり、腰や膝にまで負担が広がるケースもあります。こうした「二次的な痛み」は、早期に対応することで防げる場合が多いと言われています。
こんな症状が出たら早めの相談を
以下のようなサインがある場合は、自分で判断せず、整骨院や専門機関に相談することがすすめられています。
- 痛みが3日以上続く、または徐々に強くなっている
- 腫れや熱感があり、触れるとズキズキする
- 歩行時に痛みでびっこを引いてしまう
- 朝起きたとき、足をつけるだけで痛みが走る
- かかと部分が赤く腫れ、靴を履くのが難しい
このような場合、アキレス腱炎や滑液包炎などの炎症が進行している可能性があります。早めに相談することで、悪化を防ぎ、回復を早めることができると考えられています。
引用元:https://rehasaku.net/magazine/heelpain/
成長期の子どもの場合は特に注意
小中学生の年代で片足のかかとが痛む場合は、**シーバー病(踵骨骨端症)**の可能性もあると言われています。これは成長期特有の症状で、骨の成長スピードに筋肉や腱が追いつかないことが原因と考えられています。
「運動後に痛がる」「踵を押すと強く痛む」などのサインがあれば、無理に運動を続けずに休ませることが大切です。適切なケアを行えば改善するケースが多いとされているため、早めの判断が重要です。
引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp
痛みの背景に隠れた要因を見逃さない
痛みの原因がかかとそのものではなく、姿勢や骨盤のゆがみ、筋膜の癒着といった全身の問題にある場合もあります。そのため、局所だけのケアでは一時的に良くなっても、再発するケースも少なくありません。
整骨院などでは、触診による全身のバランス確認や、歩行のクセのチェックを行い、根本的な原因を探ることがあると言われています。自分では気づきにくい体のゆがみを整えることで、痛みの再発を防ぐ手がかりになるでしょう。
相談のタイミングは「違和感のうちに」
「歩けないほどではないから大丈夫」と思っているうちに、慢性的な炎症へ進行してしまう人もいます。専門家による早期ケアを受けることで、施術回数や回復期間を短縮できるケースもあると言われています。
目安としては、「痛みが3日続く」「朝の一歩がつらい」「腫れや熱を感じる」などが現れた段階で相談するのがよいとされています。違和感のうちに行動することで、長期的なトラブルを防ぎやすくなるのです。
まとめ
かかとの後ろの痛みを放置すると、炎症の悪化や他部位への影響を招くことがあります。痛みが続く・腫れる・熱を持つといったサインが出たら、早めに相談することが重要だと言われています。違和感のうちにケアを始めることで、再発防止にもつながります。
#かかとの痛み #放置は危険 #シーバー病 #早期相談 #違和感サイン