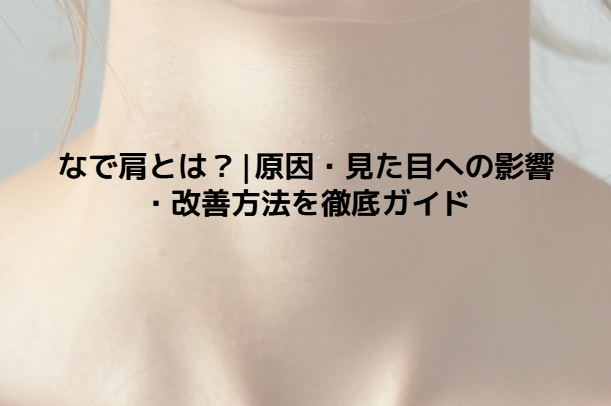なで肩とは?見た目と定義

肩がなだらかに下がって見える状態
「なで肩」とは、肩のラインが外側に向かって緩やかに下がって見える状態のことを指します。
一般的には、首から肩先にかけての角度がなだらかで、衣服を着たときに襟元が下がったり、バッグの肩紐がずれやすいといった特徴が見られます。
肩の形は人によって異なりますが、なで肩の人は肩甲骨の位置がやや下がっており、首が長く見える傾向があります。
見た目としては「華奢に見える」「上半身が小さく見える」といった印象を与える一方で、筋肉の支えが弱くなることで肩こりや姿勢の崩れにつながることもあると言われています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本整形外科学会)
正常な肩ラインとの違い
では、なで肩はどのように見分けられるのでしょうか?
目安として、立った状態で鏡を見たときに「首から肩先までのラインが約15度以上下がっている」場合、なで肩傾向があると言われています。
一方、肩のラインが水平またはやや盛り上がっているタイプは「いかり肩」に分類されます。
なで肩は骨格的な特徴に加えて、姿勢や筋力のバランスも影響します。
特に、長時間のデスクワークやスマホ操作などで背中が丸くなると、肩甲骨が外側に広がり、さらに肩のラインが下がって見えることがあります。
このように、「骨格+生活習慣の組み合わせ」によって、見た目の印象が変化すると考えられています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
なで肩の見た目による印象と悩み
なで肩の方は、見た目の印象で悩むケースも少なくありません。
肩紐が落ちやすい、スーツやシャツの肩にしわが寄るなど、日常の中で不便を感じることがあります。
また、首と肩の角度が広がるため、姿勢が悪く見えたり、疲れやすいと感じることもあります。
「肩の形だけの問題ではなく、筋肉の使い方にも関係している」と整骨院などでは説明されることが多く、
肩周りの筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋など)の働きが弱まると、重力によって肩が下がりやすくなると言われています。
つまり、見た目の“形”だけでなく、体のバランス全体が関わる現象なのです。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本整形外科学会)
生まれつきの骨格か、生活習慣による後天的な変化か
なで肩には、大きく分けて**先天的(生まれつきの骨格)と後天的(生活習慣による変化)**の2つのタイプがあると言われています。
生まれつき骨格が細い人や、鎖骨が長い人はなで肩に見えやすい傾向があります。
一方で、猫背や巻き肩などの姿勢不良が続くと、筋肉のバランスが崩れて後天的になで肩のように見えることがあります。
この違いを理解することで、自分の状態に合ったケア方法を選びやすくなります。
「見た目を整えたい」「肩こりを改善したい」といった目的に応じて、ストレッチや筋トレを取り入れるとよいと考えられています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
#なで肩とは
#肩のラインの違い
#見た目の特徴
#骨格と筋肉の関係
#生活習慣による影響
なで肩になる原因・要因

筋力のバランスが崩れることで肩が下がる
なで肩の主な原因の一つとして、肩周りの筋肉のバランスの乱れが挙げられます。
肩を支える筋肉は「僧帽筋(そうぼうきん)」「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」「菱形筋(りょうけいきん)」などが中心で、これらが弱くなると、肩甲骨を正しい位置に保つことが難しくなると言われています。
特に、上部僧帽筋がうまく使えていない場合、肩甲骨が下方へ引っ張られ、肩のライン全体が下がって見えることがあります。
このような筋力の低下は、デスクワークやスマートフォン操作などで前かがみの姿勢を続けている人に多い傾向があるとされています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本整形外科学会、Medical Note)
姿勢の乱れや猫背との関係
「なで肩」と「猫背」は深い関係があると言われています。
猫背になると背中が丸まり、肩甲骨が外側へ開くため、肩が下方向に引かれた状態になります。
その結果、見た目として肩が下がり、なで肩が強調されることが多いのです。
また、スマホやパソコンを長時間使うことで、頭が前に出た「ストレートネック」姿勢になる人も増えています。
この姿勢は首や肩の筋肉に負担をかけるため、結果的に肩が下がりやすい形になります。
日常的に姿勢を意識することが、なで肩の予防につながると言われています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本姿勢教育協会)
バッグや荷物の持ち方のクセ
片方の肩にだけバッグを掛ける、重たいリュックを背負うなどの習慣も、なで肩の原因になると考えられています。
特に肩から滑り落ちやすいタイプのバッグを無理に支えるように持つことで、肩を下げる動きが癖づいてしまうことがあります。
左右どちらか一方に負担が偏ると、肩の高さや筋肉の使い方に差が生じ、片側だけなで肩が目立つケースもあります。
荷物を持つときは、両肩や腕にバランスよく負担を分ける意識が重要です。
(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)
遺伝や骨格的な特徴によるもの
生まれつきの骨格も、なで肩の見え方に大きく関わっています。
鎖骨が長く水平に伸びている人や、肩甲骨の位置が低い人は、もともと肩が下がって見える傾向があると言われています。
このようなタイプは、筋力トレーニングなどである程度の改善は可能ですが、完全に形を変えることは難しい場合もあるとされています。
整骨院や姿勢専門の施設では、個人の骨格バランスを見ながら、
「筋肉で支える方向に調整する施術」を行うこともあり、日常生活での姿勢改善と並行してケアするのが理想的です。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
ストレスや生活リズムの乱れも影響
意外に思われるかもしれませんが、ストレスや睡眠不足も、なで肩を悪化させる一因になると言われています。
ストレス状態では、無意識に首や肩の筋肉が緊張し、血流が悪くなりやすいのです。
この状態が続くと、肩甲骨まわりの動きが制限され、姿勢がさらに崩れやすくなります。
深呼吸や軽いストレッチ、リラックスできる時間をとることで、筋肉のこわばりが和らぎ、肩の位置を正常に保ちやすくなると考えられています。
(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、くまの実整骨院ブログ)
#なで肩の原因
#筋力低下と姿勢不良
#片方の肩の負担
#骨格や遺伝の影響
#ストレスによる筋緊張
なで肩がもたらす見た目・体への影響

見た目の印象に与える変化
なで肩は、体のバランスや印象に大きく関係しています。
一見すると「首が長く見える」「華奢に見える」など、柔らかく上品な印象を与えることもありますが、角度が強すぎると「姿勢が悪く見える」「服が合わない」といった悩みにつながるケースもあります。
たとえば、スーツやブラウスを着たときに肩のラインが合わず、シルエットが崩れることがあります。
また、肩紐がずり落ちやすく、何度も直す必要があるなど、日常の中で小さなストレスを感じる方も少なくありません。
ファッション面だけでなく、なで肩の方は姿勢が前かがみになりやすいため、全体の立ち姿が疲れて見えると言われています。
見た目の印象は、筋肉の使い方や姿勢のクセによっても左右されるため、鏡で自分の肩の傾きや姿勢バランスを確認することが大切です。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
肩こり・首こりなどの不調との関係
なで肩は見た目の問題だけでなく、体の不調につながることがあるとも言われています。
肩の位置が通常より下がることで、首や背中の筋肉に余計な負担がかかり、肩こり・首こりを感じやすくなるのです。
特に僧帽筋の上部が常に引っ張られた状態になるため、筋肉がこわばり、血流が悪くなりやすい傾向があります。
この状態が続くと、頭痛や腕のだるさなど、全身に影響が広がることもあります。
また、デスクワーク中の姿勢も関係しており、長時間パソコンに向かっていると、さらに肩が前方へ引き出され、悪循環を招くケースも少なくありません。
「肩こりが慢性的に続く」「ストレッチをしても軽くならない」という場合は、なで肩の影響が潜んでいる可能性もあると考えられています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本整形外科学会)
神経・血流への影響
なで肩によって肩が下がると、鎖骨下の神経や血管が圧迫されやすくなることもあると報告されています。
これにより、「胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)」と呼ばれる症状が起こる場合があります。
胸郭出口症候群とは、鎖骨の下を通る血管や神経が圧迫されることで、腕や手のしびれ、冷え、脱力感などが現れる状態を指します。
特に女性や細身の体型の方、なで肩の人に多い傾向があるとされており、
「最近、肩から腕にかけて違和感がある」「腕を上げるとしびれる」といった場合は、専門機関への相談がすすめられています。
(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)
呼吸や姿勢のバランスにも影響
なで肩は、肩甲骨の位置が下がり、背中が丸くなる「巻き肩」とセットで見られることが多いです。
この状態では、胸が閉じてしまい、呼吸が浅くなる傾向があります。
呼吸が浅いと酸素の取り込みが減り、疲れやすさや集中力の低下を招くと考えられています。
また、肩の位置が前に出ることで、腹圧(お腹の支え)も弱まり、体幹の安定性が落ちることがあります。
結果的に「猫背」「骨盤のゆがみ」「姿勢の悪化」へとつながり、見た目だけでなく体全体のバランスが崩れていくとされています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)
メンタル面にも影響することがある
姿勢が前かがみになることで、呼吸が浅くなり、無意識のうちに気分が落ち込みやすくなるという研究報告もあります。
なで肩や猫背が続くと、自律神経のバランスが乱れ、リラックスしづらい状態が続く場合もあると言われています。
姿勢を整えることは、見た目の印象を良くするだけでなく、気持ちの安定にもつながると考えられています。
そのため、なで肩のケアは「肩だけの問題」ではなく、「体全体と心の調和」を整える第一歩になるのです。
(引用元:Medical Note、くまの実整骨院ブログ)
#なで肩の影響
#見た目の印象と姿勢
#肩こりと首こりの関係
#胸郭出口症候群に注意
#姿勢とメンタルのつながり
自宅でできる改善ストレッチ・筋トレ法

なで肩改善の基本は「肩甲骨を正しい位置に戻す」こと
なで肩を改善するためには、肩甲骨まわりの筋肉をしっかり動かし、正しい位置に戻すことがポイントと言われています。
特に、背中の中央にある「僧帽筋(そうぼうきん)」や「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」などの筋肉を刺激して、肩を引き上げる力を取り戻すことが大切です。
デスクワークやスマホ操作が多い人は、肩甲骨が外に広がりやすく、肩が下に引かれる姿勢が癖になっています。
そのため、「肩を上げる」「背中を寄せる」動きを日常的に取り入れることで、なで肩の印象をやわらげる効果が期待できるとされています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
肩まわりを温めながら動かすストレッチ
ストレッチは、無理に強く伸ばすよりも「呼吸に合わせてゆっくり行う」ことが大切です。
次のようなシンプルな動きを朝や入浴後に続けることで、肩甲骨の動きが徐々にスムーズになると言われています。
▪ 肩甲骨よせストレッチ
- 背筋を伸ばして座るか立つ
- 両肘を軽く曲げ、肩甲骨を背中の中心に寄せるように引く
- 5秒キープして戻す(10回×2セット)
この動きを行うと、背中の筋肉が目覚め、肩の位置を自然に引き上げやすくなります。
▪ 肩回し運動
- 両肩をすくめるように持ち上げる
- ゆっくりと後ろへ回す
- 大きな円を描くように10回×2セット
肩まわりの血流を促し、肩甲骨の可動域を広げる効果があるとされています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、日本整形外科学会)
肩を支える筋肉を鍛えるトレーニング
ストレッチと併せて、肩を上げる筋肉を強化するトレーニングもおすすめです。
特に「上部僧帽筋」や「三角筋(さんかくきん)」を意識的に使うことで、肩が下がりにくくなると言われています。
▪ シュラッグ(肩すくめ運動)
- ダンベルまたはペットボトルを両手に持つ
- 肩を真上にすくめ、2秒キープ
- ゆっくり下ろす(10〜15回×2セット)
軽い負荷でも構いません。ポイントは**「首をすくめず、肩だけ動かす」**ことです。
▪ タオルローイング
- 背筋を伸ばして座り、両手でタオルを前に持つ
- 肘を後ろに引きながら、肩甲骨を寄せる
- 背中を意識してゆっくり戻す
この動きは、デスクワークで凝り固まった肩甲骨まわりの血流を促す効果があると言われています。
(引用元:Medical Note、くまの実整骨院ブログ)
胸を開くストレッチで姿勢をリセット
なで肩の人は、胸の筋肉(大胸筋)が硬くなりがちです。
そのため、胸を開くストレッチを行い、前側の緊張をゆるめることが重要です。
▪ 壁ストレッチ
- 壁に手をつき、胸を少し前に押し出す
- 肩の前側が伸びているのを感じながら、20秒キープ
- 反対側も同様に行う
デスクワーク中のリフレッシュとしても効果的で、呼吸が深くなり、自然と姿勢が整いやすくなります。
(引用元:日本姿勢教育協会、くまの実整骨院ブログ)
続けることで得られる変化
こうしたストレッチや筋トレを2〜3週間続けると、**「肩が上がりやすくなった」「肩こりが減った」**と感じる方も多いと言われています。
継続することで筋肉が正しく働き、重力に負けない姿勢が定着しやすくなります。
ただし、急に強い負荷をかけると逆に筋肉を痛めることがあるため、無理をせず、心地よい範囲で行うことが大切です。
毎日の習慣として取り入れれば、少しずつ肩の位置が整い、見た目の印象にも変化が現れる可能性があります。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
#なで肩改善ストレッチ
#肩甲骨の位置を整える
#僧帽筋トレーニング
#胸を開く姿勢改善
#続けやすいセルフケア
注意点・改善しづらいケース・専門家を頼るタイミング

自己流のストレッチやトレーニングに注意
なで肩を自分で改善しようとするときに気をつけたいのが、やり方を間違えると逆効果になる場合があるという点です。
特に、「強く引っ張る」「無理な姿勢で動かす」といったストレッチは、肩甲骨まわりの筋肉や関節を痛めるリスクがあると言われています。
また、動画やSNSで紹介されている方法の中には、骨格や筋肉の特徴を無視した動きが含まれていることもあります。
人によって筋肉のつき方や関節の可動域は異なるため、他人のやり方をそのまま真似るのではなく、自分の体に合わせて行うことが大切です。
「ストレッチ中に痛みやしびれを感じた」「動かすと肩が重くなる」といった場合は、すぐに中止して体を休ませましょう。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note、日本整形外科学会)
改善しづらいケースもある
なで肩には、生まれつきの骨格によるタイプと、姿勢や筋力低下による後天的なタイプがあります。
骨格的になで肩が強い人は、完全に形を変えることは難しい場合もあると言われています。
しかし、骨格が原因であっても、筋肉を鍛えたり姿勢を整えたりすることで「見た目の印象を改善する」ことは可能です。
特に、肩を支える僧帽筋や三角筋をしっかり使えるようになると、肩の位置が自然に引き上がり、全体のラインが整うことがあります。
一方で、猫背やストレートネックなどが強く出ている人は、肩だけでなく首や背中全体のバランスを見直す必要があります。
根本的な改善を目指すなら、体全体の姿勢矯正を意識することが大切だと言われています。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
痛みやしびれを感じたら専門家に相談を
ストレッチやトレーニング中に「腕がしびれる」「肩から首にかけて痛みが出る」といった症状がある場合は、
**胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)**など、神経や血管の圧迫が関係していることがあります。
このような症状を放置すると、腕の力が入りにくくなったり、日常動作に支障をきたすこともあるため注意が必要です。
整形外科や整骨院などで、触診や姿勢のチェックを受けることで、自分の肩の位置や筋肉の状態を正確に把握できます。
整骨院では、肩甲骨や鎖骨の動きを見ながら、個人の状態に合わせたストレッチや筋肉の調整を行うことが多く、セルフケアだけでは難しい改善をサポートしてくれます。
(引用元:日本整形外科学会、くまの実整骨院ブログ)
改善を継続させるためのコツ
なで肩の改善は、一度のストレッチや筋トレで変わるものではありません。
**「日常動作を意識的に変えること」**が、最も大切なポイントです。
例えば、次のような工夫を取り入れるだけでも、肩の位置をキープしやすくなります。
- スマホを目線の高さに上げて使う
- デスクの高さを調整して、背中が丸まらないようにする
- 通勤や買い物で、肩を大きく回す習慣をつける
- 重たい荷物は左右交互に持つ
「今日だけ頑張る」よりも、「1日1回だけでも姿勢を整える時間をつくる」方が、体にとっては継続的な変化を生みやすいとされています。
(引用元:Medical Note、日本姿勢教育協会)
専門的な施術を取り入れる選択肢
セルフケアで限界を感じた場合は、整骨院や姿勢専門の施術院で相談してみるのもよい方法です。
プロによる姿勢チェックでは、肩甲骨の位置や骨盤の傾き、背中の筋肉バランスなどを総合的に確認してくれます。
また、なで肩の根本的な原因が「肩の下がり」ではなく、「背中や骨盤のゆがみ」から来ているケースもあるため、
全身のバランスを見ながら調整することが改善への近道と言われています。
継続的に正しい姿勢を保つことで、見た目の印象だけでなく、肩こりや首こりといった不調の軽減にもつながる可能性があります。
(引用元:くまの実整骨院ブログ、Medical Note)
#なで肩改善の注意点
#セルフケアの限界
#専門家への相談タイミング
#日常動作の見直し
#姿勢矯正で全身バランス改善