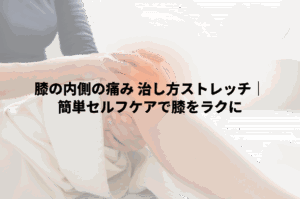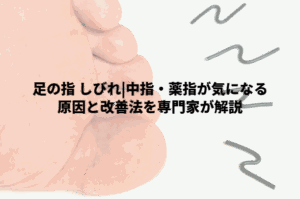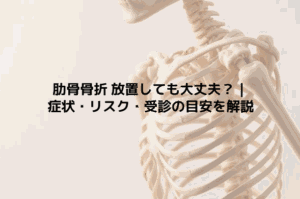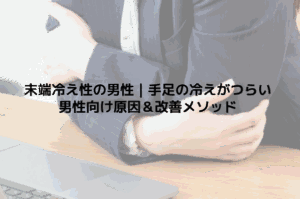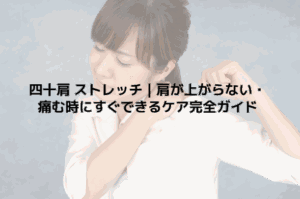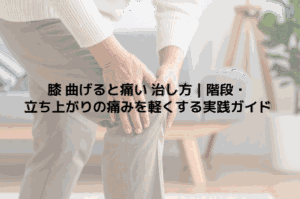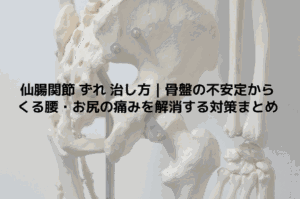肩甲骨 筋肉とは?構造と肩甲骨まわりの筋肉の基本を整理

肩甲骨はどんな位置にあるのか
「肩甲骨って、実際どこにあるんですか?」
こう聞かれることがあります。肩甲骨は背中の上側にある三角形の平たい骨で、胸郭に直接くっついているわけではなく、周囲の筋肉によって支えられていると言われています。
そのため、肩甲骨の動きは筋肉の働きに大きく影響を受け、姿勢の崩れが続くと位置が変わりやすいと紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3212/ )。
浮いているような位置関係が特徴で、腕の動きの土台として重要な役割を担っているとされています。
肩甲骨につながる代表的な筋肉
「肩甲骨 筋肉って、どの筋肉のことを指すんでしょう?」
実際には複数あり、特に僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋・前鋸筋は欠かせない存在と言われています。
僧帽筋は首から背中の上部まで広がり、肩甲骨を寄せたり下げたりする働きがあると紹介されています。
菱形筋は肩甲骨を内側に引き寄せ、姿勢を安定させる筋肉として知られています(引用元:https://nagomi-medical-group.com/1057 )。
そして前鋸筋は肩甲骨を外へ滑らせる働きを持ち、腕を前に出す動作と深く関わっていると言われています。
肩甲挙筋は肩甲骨を持ち上げる筋肉で、首の張りと関係しやすいと紹介されています。
多くの筋肉が連動して肩甲骨を動かしている
「一つの筋肉だけで動いているわけじゃないんですね?」
その通りで、肩甲骨の動きは複数の筋肉が協力して成り立っていると言われています。
寄せる・下げる・前に押す・持ち上げるなど、動作によって担当する筋肉が変わるため、どれか一つが硬くなるだけでも動き全体に影響が出ると紹介されています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/ )。
たとえば、前鋸筋が弱まると肩が内巻きになりやすく、菱形筋が働きにくいと背中が丸まりやすいと言われています。
姿勢との関係も深い
肩甲骨 筋肉は姿勢の影響を受けやすく、猫背が続くと肩甲骨が外へ開きっぱなしになることがあるとされています。
反対に胸を張りすぎても筋肉の緊張が高まり、背中の張りにつながると紹介されています。
日常の姿勢が肩甲骨周辺にどんな負担を与えるかを知ることで、対策を立てやすくなると言われています。
#肩甲骨
#僧帽筋
#菱形筋
#前鋸筋
#肩甲骨と姿勢
肩甲骨 筋肉の働き・動き別に見る役割

肩甲骨を「寄せる」動きに関わる筋肉
肩甲骨を内側へ寄せる動きを意識してみると、背中の中心あたりでスッと力が入る感覚が出ます。
この動きでは、菱形筋と僧帽筋中部が大きく関わると言われています。
背中が軽く伸びるように感じる時は、これらの筋肉がうまく働いている状態だと紹介されています。
逆に、肩甲骨が外に開いたまま戻りにくい時は、菱形筋の働きが弱くなっている可能性があるとされています(引用元:https://nagomi-medical-group.com/1057 )。
肩甲骨を「下げる」「安定させる」動き
肩が自然と上がってしまう感覚がある時は、僧帽筋下部がうまく働いていない場合があると言われています。
肩甲骨を下げる動きは、この僧帽筋下部が中心となって支えていると紹介されています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/ )。
肩の位置が高いままだと首に力が入りやすく、緊張が抜けにくい状態になりやすいとされています。
肩甲骨を「前へ押し出す」動き
腕を前に伸ばすとき、肩甲骨がスムーズに外へ滑っていく感覚があります。
この動きを支えているのが前鋸筋と言われています。
前鋸筋が弱くなると肩が内巻きになりやすく、肩甲骨が十分に動かない状態になりやすいと紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3212/ )。
スポーツの動作では特に重要で、前鋸筋が働くほど腕の軌道が安定するとされています。
肩甲骨を「上げる」動き
肩をすくめるような動きでは、肩甲挙筋と僧帽筋上部が主に使われると言われています。
首の横が張りやすい人は、このあたりの筋肉が緊張し続けているケースがあると紹介されています。
寒さやストレスで肩がすくみ、筋肉が硬くなることもあるとされています。
動きの特徴が連動して肩甲骨を支える
肩甲骨の動きは、一つの筋肉だけで成り立つものではないと言われています。
寄せる・下げる・押し出す・持ち上げるなど、どの動作も複数の筋肉が協力し、連動することで滑らかに動くと紹介されています。
どこか一つが硬くなると連鎖的に動きが悪くなり、肩周囲の負担が高まりやすいとされています。
動作ごとの特徴を理解しておくと、コリや姿勢変化の理由を整理しやすくなる点が大きなメリットと言われています。
#肩甲骨の動き
#僧帽筋
#菱形筋
#前鋸筋
#肩甲挙筋
肩甲骨 筋肉が硬くなると起こる不調・姿勢のクセ

首や肩の重さにつながりやすい理由
肩甲骨 筋肉が硬くなると、首の付け根や肩の広い範囲に重さが広がりやすくなると言われています。
肩甲骨まわりには僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋など、首と背中をつなぐ筋肉が多く走っており、どこか一箇所が張るだけで連動して負担がかかると紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3212/ )。
首が引っ張られるように感じたり、肩が上がりやすくなるのは、この連動性が影響しているとされています。
肩甲骨が開きっぱなしになる“巻き肩”
肩が前へ出やすい人は、肩甲骨が外へ広がって戻りにくくなる状態が続いていることがあります。
このクセは「巻き肩」と呼ばれ、前鋸筋が弱くなったり、菱形筋の働きが十分でなかったりする時に起こると言われています(引用元:https://nagomi-medical-group.com/1057 )。
巻き肩が続くと胸が縮こまり、呼吸も浅くなりやすいと紹介されています。
背中が丸く見えるだけでなく、肩甲骨の滑らかな動きも失われやすいとされています。
腕が上がりづらくなる原因
肩甲骨は腕の動きを支える土台と言われています。
肩甲骨の可動性が落ちると、腕を上げるときに肩だけで頑張る形になり、途中でつっぱるような感覚が出やすくなると紹介されています。
特に、僧帽筋下部や前鋸筋が十分働かない時は、肩甲骨がうまく引き下がらず、可動域が狭く感じることがあるとされています。
スポーツや日常の動作でも「腕が重い」「引っかかる感じがある」などにつながる点が特徴です。
背中の張りが長引きやすい
肩甲骨 筋肉が固まってくると、背中の奥に重く張るような感覚が出ることがあります。
菱形筋が縮んだまま緊張すると、肩甲骨が寄りにくくなり、背面のバランスが崩れやすいと言われています。
姿勢を保つために別の筋肉が補おうとするため、広い範囲が張りやすくなると紹介されています。
全身の姿勢に影響することも
肩甲骨の動きが悪くなると、胸郭の動きも制限され、呼吸が浅くなることがあると言われています(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/246.html )。
呼吸が浅くなると体がこわばりやすく、首・腰・腕のどこかに負担が移るケースも紹介されています。
肩甲骨は体の中でも影響範囲が広く、硬さが全身の姿勢バランスにまで波及しやすい点が特徴とされています。
#肩甲骨の不調
#巻き肩
#首肩の張り
#腕の可動域低下
#姿勢の乱れ
肩甲骨 筋肉を整えるためのセルフケア・トレーニング

肩甲骨の状態をその場で確かめる方法
腕をゆっくり上げ下げしてみると、肩甲骨が背中でどう動いているかが意外と分かりやすいと言われています。
スッと滑るように動く日もあれば、奥で引っかかるように感じる日もあり、その差が筋肉の状態を知るヒントになると紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3212/ )。
左右差が大きい場合は、どちらかの肩甲骨まわりが硬くなっている可能性があるとされています。
背中のコリをゆるめるストレッチ
背中の真ん中が張りやすい人には、菱形筋や僧帽筋をやさしく伸ばすストレッチが合うことがあると言われています。
腕を前に伸ばし、背中を丸くするように呼吸を合わせると、肩甲骨が外へ開いて筋肉がほぐれやすいと紹介されています。
勢いよく伸ばすより、息を吐きながらゆっくり行う方が負担が少ないとされています。
前鋸筋を働かせる“押し出し”トレーニング
肩が内側へ巻きやすい人は、前鋸筋がうまく働いていない場合があると言われています。
壁に手をつき、肩をすくめず胸を軽く押し出すようにすると、肩甲骨が外へ滑りやすくなり、前鋸筋が使われる感覚が出ると紹介されています(引用元:https://nagomi-medical-group.com/1057 )。
前鋸筋が働くと、肩の位置が自然に整いやすいとされています。
肩甲挙筋をやさしく緩めるケア
首の横が常に張りやすい場合、肩甲挙筋の緊張が関わることがあると言われています。
片側の首をゆっくり倒し、反対の手で肩を軽く下げるようにすると、この筋肉が伸びやすいと紹介されています。
呼吸と合わせて力を抜きながら行うと、張りが和らぎやすいとされています。
姿勢を整えて肩甲骨への負担を減らす
肩甲骨 筋肉は日常の姿勢に左右されやすいため、ケアと同時に姿勢の見直しをすることがすすめられることがあります。
画面が低い位置にあると首が前に出て、僧帽筋上部に負担が集中すると紹介されています(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/246.html )。
背中を反らしすぎず、胸も張りすぎない“中間の姿勢”を意識することで、肩甲骨の動きが安定しやすいと言われています。
#肩甲骨ケア
#僧帽筋ストレッチ
#前鋸筋トレーニング
#肩甲挙筋
#姿勢改善
まとめ:肩甲骨 筋肉を理解するとケアの方向性がつかみやすい

肩甲骨まわりを知ると不調の整理がしやすい
肩甲骨 筋肉の特徴を整理してみると、首・肩・背中の不調がどうつながっていくのかが見えやすくなると言われています。
肩甲骨は胸郭に直接つかず、複数の筋肉だけで支えられているため、僧帽筋・菱形筋・前鋸筋などのバランスが崩れると動きがぎこちなくなると紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3212/ )。
日常生活の中で起こるクセが、肩甲骨の位置や動きに影響することもあるとされています。
姿勢と筋肉の関係が深い
姿勢が少し変わるだけで肩甲骨周辺の筋肉の使い方が変わることがあり、巻き肩・猫背・反り腰など、どの姿勢のクセが強いかによって負担のかかる場所が変わると紹介されています(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/246.html )。
胸が縮こまる姿勢が続くと前鋸筋が働きにくくなり、背中側の筋肉に負担が寄りやすいと言われています。
「硬さ」だけでなく「働きの弱さ」もポイント
肩甲骨 筋肉は、硬くなるだけでなく働きが弱くなることでも動きの制限が出るとされています。
菱形筋が弱いと肩甲骨が外へ開きやすく、僧帽筋下部が働かないと肩が上がりやすくなるなど、筋肉のバランスが肩の動きに直結すると紹介されています(引用元:https://nagomi-medical-group.com/1057 )。
硬いのか、弱いのか、その両方なのかを見極めるとケアの方針が決めやすくなると言われています。
日常の小さな動きがケアにつながる
大きなストレッチをしなくても、立ち方・座り方・画面の位置など、ほんの少しの変化が肩甲骨の負担を減らすことがあると紹介されています。
「無理なく続けられること」を積み重ねる方が筋肉のバランスが整いやすいとされています。
呼吸を深くするだけでも胸郭の動きが出て、肩甲骨の動きやすさにつながることがあると言われています。
変化を感じたら次のステップへ
肩甲骨 筋肉の状態は、日によって変わりやすいとされています。
腕の動きが軽くなる日があったり、背中の張りが和らぐ瞬間があったり、その変化を覚えておくと、自分に合うケアが見つかりやすくなると言われています。
焦らず、体の反応を確認しながら取り組むことで、肩周囲の動きが整うきっかけになると紹介されています。
#肩甲骨まとめ
#筋肉バランス
#姿勢のクセ
#前鋸筋と菱形筋
#肩のセルフケア